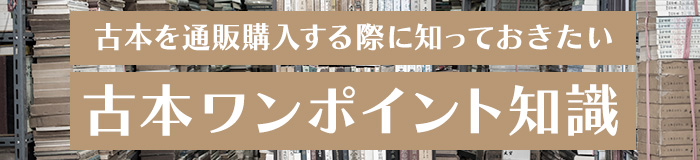日本では「新刊本屋/古本屋」という区別が一般的に浸透していますが外国では曖昧です。ここでは歴史的に古本に関する言及された資料をご紹介します。古本の歴史を知ることで現代の古本を取り巻く状況を理解する一助としてください。
このページの内容は「東京古書組合百年史」(2021年発行)から引用しています。
「東京古書組合百年史」(2021年発行)を日本の古本屋で検索する
平安時代「古本の始まり」
古本屋が確認された初めての資料
平安時代に藤原定信が書籍を入手した由来のメモが、古本売買に関する最も古い記述とされています。メモを書き込んだタイミングは不明ですが、西暦1100年〜1150年頃と考えられます。
メモは、藤原定信に経師の妻と思われる女が古本を売りに来たという内容でした。
経師は書籍を写字し巻子に仕立てるのが仕事のため、写字し終えて不要になった書籍を古本として販売する中で書籍の転売もしていたと考えられています。そのためこの経師が、書籍を取り扱う古本屋の起源であると考えられています。
「江戸の古本屋 近世書肆のしごと」(平凡社)誠心堂書店主人・橋口候之介氏著より引用部分
「白楽天詩巻」の巻末に、四代後の藤原定信がこの本を入手した由来を書き込んだメモ(テクスト)
「保延六年(一一四◯)庚申十月二十二日の朝、物売りの女が蓬門より入ってきて手本二巻、一巻は小野道風の『屏風土代』、一巻はこの本を売りに来た。一目で行成の筆とわかったので価格として××(個々の値段が入っていたと思われるが、二行消ししてある)を与えたら女は大いに喜んで帰って行った」
<「白楽天詩巻」とは?>
平安時代(1018年)藤原行成が筆を取ったとされている書籍。
<藤原定信とは?>
藤原行成の四代後、生誕は寛治2年(西暦1088年)、死没は保元元年1月18日(西暦1156年2月10日)。
<経師とは?>
写経に従事するもの一般。
筆写、写字用の紙を用意、写字済みの紙を巻子に仕立てる作業を担当していた。
不要になった古書の転売先を探したりすることもあった。
印刷所、本屋(本屋の起源)
江戸時代「昔から人気だった古本」
広い意味での「本屋」が登場
江戸時代、古本屋は新刊書の出版・販売、古本の販売の両方を行っていたと考えられています。
そのような広い意味での本屋が登場したのは、江戸時代の初期(慶長年間(1596年から1615年)・元和年間(1615年から1624年))頃のようです。この頃、書籍に発行所の名称と住所を表記した「刊記」(奥付)が付き始めたため古本屋の数が推定できるようになりました。
このような本屋は「物本屋(ものほんや)」「物之本屋(もののほんや)」と呼ばれていたことが、この頃に作られた仮名草子「祇園物語」に記載されています。
やがてこれらは「書林」と総称されるようになります。
享保年間(1716年から1736年)頃には京都で「書林」は200軒程あったとされています。
江戸時代にも開催された「古本市」
古本の「市」「市場」の起源は享保年間(1716年から1736年)頃だとされ、その後に徐々に整備されて宝暦年間(1751年から1764年)に「市屋株」という市場開催権を本屋に与える仕組みも作られました。
「市」は問屋としての機能も持ち、古本屋が成立する上で重要な要素となりました。
「市」は古本を交換するだけなく、価格の形成をする機能もありました。
その中で、本屋仲間以外に「売子」「世利衆」「世利子」などと呼ばれる者が、正規の本屋の下に付き販売、取次、仕入れ、貸本業務などを行っていました。そういった様々な粒度の取引の中で、価値がある書籍や珍しい書籍が流通することとなり「市」は勢いを保っていました。
明治時代「大きな転換点、古本(古本屋)の仕組み」
| 明治初期まで | 書籍の出版・販売事業に参画するためには、問屋組合に加入する必要があった。 |
|---|---|
| 明治8年 | 「出版条例」によって、問屋組合に加入は不要となり認可世が届出制に変わった。(「出版条例」第一条) 誰でも届出すれば出版業を始められるようになった。 |
| 明治16年 | 「古物商取締条例」が布告され違反者に対する罰則を設けて古書取引を方の網の元に置いた。 |
| 明治22年 | 大日本帝国憲法が発布され、「古物商取締条例」は「古物商取締法」へと変更された。 |