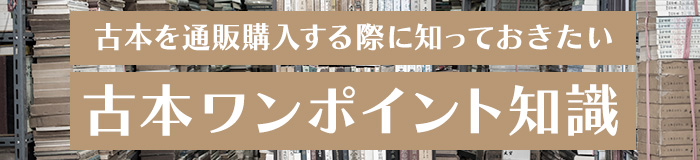古本の歴史は長く、古本を取引するための用語や、数え方や本の種類など、古本に関する用語・キーワードは数多く存在します。
ここでは、古本、和本、洋書に関する用語・キーワードを広くリストアップしました。
古本の用語
付属品の用語
カバ /帯 /函 /夫婦箱 /輸送箱 /ビニカ /元パラ /帙 /たとう /題箋 /月報 /
状態に関する用語
美本 /極美 /書込 /少書込 /線引 /記名 /蔵印 /ムレ /シミ /切れ /欠 /ヤケ /ワレ /開き癖 /コワレ /ツカレ /ラミネート /貸本上がり /イタミ /経年劣化 /落丁 /乱丁 /
プラスの特徴
初版 /署名 /献呈署名 /識語 /落款 /オリジナル /書影
古本屋の符牒
即売会 /クロッポイ本 /キキメ /マンジュウボン /宅買 /ガラ /ボー /ツブシ /ナタ /カズモノ /ノリ /
古書組合
その他
書店用語
和本 /和綴じ本 /洋本 /文庫本 /新書 /ムック /全集 /叢書 /雑誌 /単行本 /重版・増刷 /限定版 /私家版 /
澄田喜広著『古本屋になろう!』、青弓社、2014より引用
和本の用語
あいはん[相板] /あおほん[青本] /あかほん[赤本] /あとずり[後刷] /いしょくじはん[異植字版] /いたかぶ[板株] /いなかばん[田舎版] /いれほん[入本] /うきよぞうし[浮世草子] /うめき[埋め木] /えまきもの[絵巻物] /おうらいもの[往来物] /おおほん[大本] /おくがき[奥書] /おりじょう[折帖] /おりほん[折本] /かいはん[開板] /かすがばん[春日版] /カナしょう[カナ抄] /かなぞうし[仮名草子] /かんいんしゅう[刊印修] /かんえいばん[寛永版] /かんき[刊記] /かんすぼん[巻子本] /かんぱん[官版] /かんぽん[完本] /ぎはん・ぎこく[偽板・偽刻] /きびょうし[黄表紙] /きょうかく[匡郭] /きょうせつそう[経折装] /ぎょび[魚尾] /くさぞうし[草双紙] /くろほん[黒本] /げだい[外題] /げてん[外典] /ごうかん[合巻] /こうやばん[高野版] /こかつじばん[古活字版] /ござんばん[五山版] /こちょうそう[胡蝶装] /こっけいぼん[滑稽本] /こひつぎれ[古筆切] /こひつてかがみ[古筆手鑑] /こほん[小本] /さいかくぼん[西鶴本] /さいはん[再板] /さがぼん[嵯峨本] /しかばん[私家版] /しゃほん[写本] /しゃれぼん[洒落本] /じゅうはん[重板] /しゅびき[朱引き] /じょうるりぼん[浄瑠璃本] /すきかえし[漉き返し] /するがぱん[駿河版] /せいはん[整版] /せんそうぼん[線装本] /ぞう・ぞうはん[蔵・蔵版] /そうし[草紙・双紙] /そうてい[装訂] /ぞうび[象鼻] /だいせん[題簽] /たてながぼん[縦長本] /たとう[套] /ちつ[帙] /ちゅうほん[中本] /ちょくはん[勅版] /つぎがみ[継ぎ紙] /つのがき[角書] /てつようそう[綴葉装] /でっちょうそう[粘葉装] /とうしょ[頭書] /とくしょうぼん[特小本] /とくだいぼん[特大本] /とめいた[留板] /とりのこ[鳥の子] /ないだい[内題] /ないてん[内典] /ならえほん[奈良絵本] /にんじょうぼん[人情本] /はしらだい[柱題] /ばつ・ばつぶん[跋・跋文] /はつだ[発兌] /はっそう[八双] /はなしぼん[咄本] /はんしぼん[半紙本] /はんしん[版心] /はんづら[版面] /はんぽん[版本] /はんもと[板元] /ふくもの[幅物] /ふくろとじ[袋綴じ] /ふしみばん[伏見版] /ぶんげんえず[分間絵図] /ほうじょう[法帖] /ほんこく[翻刻] /ますがたぼん[枡形本] /みのばん[美濃判] /むかんきぼん[無刊記本] /もくかつじ[木活字] /もののほん[物之本] /もんじょ[文書] /よこほん[横本] /よみほん[読本] /りょうし[料紙] /れっちょうそう[列帖装] /れんめんたい[連綿体] /わこく・わこくぼん[和刻・和刻本] /わそうぼん[和装本] /
和本などの数え方(助数詞)の一例
[帖] 折帖(法帖、書画帖など)、折本 /[面] 書画額、扇面額、色紙額 /[舗] 地図(折り畳んだもの) /[冊] 冊子本 /[巻] 巻子本、巻物 /[幅] 幅物、掛け軸、軸物 /[枚] 草稿、短冊、色紙 /[通] 書状 /
橋口侯之介校閲/川村光郎編『古書手帳』、「和本の作法」、東京都古書籍商業協同組合中央線支部、2013より引用
洋書の用語
abridged edition /abstract /affecting (the text…) /age-toned /A.H., Anno Hegirae /all edges gilt (a.e.g.) /ALS /anonym (anonymous) /appendix /armorial binding /as issued /as new /as usual /association copy /back /back cover /back loose /back page /backstrip /back title /bastard title /beveled edge /Bible paper /binding copy /black letter /bleaching /blind stamp /block-book /boards (bound in) /book jacket /book label /book-plate /boxed /bright /brochure /bumped /cancel leaf /catalogue raisonne /catch words /chipped /cloth (cloth binding) /cocked /cockled /collectible /contemporary /corrigendum /covers bound in /cracked /creased /crimped /cropped /damaged /dampstain(-ed) /darkened /dd. /deckie edges /defect /device /diagram /ding /disbound /discol’d /double-page plate /dog-eared /dulled /dust cover /dust-soiled /edition princeps /else /endpaper (endleaf) /engraving /even page /ex-library copy /facing pages /facsimile /fading /fascicle (F=fascicule) /figure /first edition thus /flap /fleuron /fly leaf /folding plate /fore-edge painting /foxing, foxed /fraying /free endpaper /frontispiece /gilt /gnawed /gutter /half-binding /half title /headband /high spot /highlighting /hinge /hors texte(F) /illuminated /impression /incunabula /inscribed /intact /jacket /joint /juvenilia /lack(ing) /leaf, leaves , lvs /loose, loosened /made-up copy /marred /mint (copy) /mounted /no date (n.d.) /no paging, /no place (n.p.) /notes /offset /oblong (obl.) /open tear /opera (>opus) /original wrappers /page missing /paging disorder /panel /paperback grading /plate, pl., pls. /preliminary pages /rare /readng copy /re-backed /rehinged, rejoined /remainder (mark) /re-set /residue /rubbed /scuffed /set-off /shaken /shelfwear /signed book (copy) /signature /soiled /sound copy /spine /spot, spotted /sprinkled edges /square /stained /tall copy /tanning /tarnished /tear (torn) /t.e.g. (top edge gilt), /tipped in /tirage (F) /trimmed /trivial /turn-ins /uncommon /uncut /underlining /used copy /vignette /waterstained /woodcut /wood engraving /worm hole, wormed /worn (wear) /w.a.f. /wrappered, /wrappers , wraps /
洋書に関するその他のキーワード
本の状態を示す表現(一例)
洋書の判型
用語・キーワード関連コンテンツ

江戸から伝わる古書用語 1 セドリ (シリーズ古書の世界第4回)
セドリは、各地の本屋を回って本を仕入れ、それを古書市場や専門店に持っていって利ざやを稼ぐことをいう。これを「背取り」と書いて、本の背を見ながら抜いていくことからきているという解釈がまかり通っている。しかし、これは誤っており、一種の都市伝説である。この用語は江戸時代からあり、当時の本は和本であり、背中なるものは見えないのだから。このセドリがいつから始まったかは定かではないが、少なくとも18世紀には確認できる商慣習である。曲亭馬琴の書いた『近世物之本江戸作者部類』によれば人情本の人気作家・為永春水は、「柳原土手下小柳町の辺に処れり。旧本の瀬捉といふことを生活に…
もっと見る

江戸から伝わる古書用語 2 本の市場 (シリーズ古書の世界第5回)
競り市場というのは、一つのアイテムを複数の買い手が競争することで一定の値が付くことにある。これを相場といい、次回以降の取引に参照される。この関係は江戸時代には早くから金銀や米の取引で確立されており、きわめて現実的な価格形成が為されてきた。大坂の堂島では18世紀初頭の宝永・正徳頃に米の先物取引が始まったとされ、それが全国に影響を与えた。金銀銅貨の交換も取引所があって大坂では毎日レートが発表されていた。この方法を本屋たちも早速取り入れている。享保の頃には(1720年代)には京都で本と板木の市が立ったことが確かめられているのだ。当初は私的な市場だった…
もっと見る
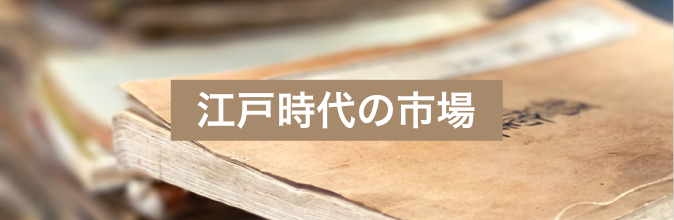
江戸から伝わる古書用語 3 江戸時代の市場 (シリーズ古書の世界第6回)
前回、江戸時代にも古書の市場があったことを述べた。河内屋和助こと三木佐助の懐古談『玉淵叢話』によれば、「糶市(せりいち)と申すものでござりました。……伊丹屋善兵衛で市の定日が二、七の日、外に内々の市屋、柏原屋儀兵衛のが四、九の日、播磨屋太助のが三、八の日でありまして此等の糶市が私共若年者には誠によい参考になりましたのでござります。凡て書籍と云ふ書籍は御経浄瑠璃本まで悉く此市で売買されたものであります」とその盛況ぶりが描かれている。今回はその実態をもう少し明らかにしておこう。江戸・京・大坂では本屋仲間が株を与える公式な市場があったことを紹介したが、…
もっと見る

江戸から伝わる古書用語 4 江戸時代の本屋の日記から (シリーズ古書の世界第7回)
寛永期から続く伝統ある京都の本屋・風月庄左衛門(ふうげつしようざえもん)が書いた明和9年9月(1772)から1年3ヶ月分の日記が残っている。弥吉光永編『未刊史料による日本出版文化1』(昭和63年、ゆまに書房)で見ることができる。基本的には業務日誌のようなものだが、中を読んでいくと、仕事の様子はもちろん、同業者とのつきあい、長男の出産を始め家庭内のことなどが細かく書かれている。業務もプライベートも飾ることなく書かれた二十代後半と思われる若い店主の個人的な日記である。他人に見せる目的の記録ではないので、使用されている言葉は当時の業界用語そのままであり、わかり…
もっと見る
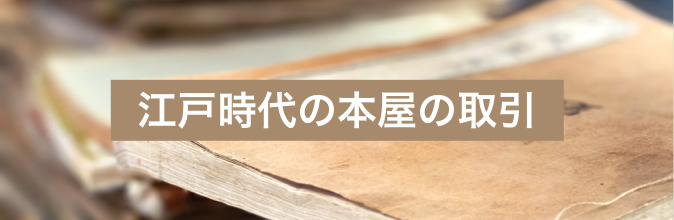
江戸から伝わる古書用語 5 江戸時代の本屋の取引 (シリーズ古書の世界第8回)
京都の本屋・風月庄左衛門の日記からもう少し紹介しよう。これは業界用語そのまま書かれたいわば業務日誌である。例えばこんな表現がある。「万歳講丸源、若州買物出ス」というのは丸屋源兵衛方で行われた万歳講に、若狭からの買い物品を出した、ということである。本屋仲間公式の市場のほかに私的な市もあった。そのひとつである万歳講の場で若狭方面から仕入れた一口物を出品したのだ。「買物」といえば仕入れのことだと古本屋ならすぐわかるが、一般の人にはピンとこないだろう。ある日の一文にこういうのもある。「松岡本ニフ帖打蔵…
もっと見る

江戸から伝わる古書用語 6 江戸時代の本屋の終焉 (シリーズ古書の世界第9回)
江戸時代の本屋の仕組みはよくできていた。それを整えた本屋仲間への信頼度も高く、安心して代々継承していた。業界への参入の門戸が広いために個人単位でも末端に入り込むことができた。しかし、そうした体質は明治に入ると外堀を埋められるような形で変貌を余儀なくされてしまう。そこには現代に通ずる問題があるので私たちもじっくり考えなくてはならない。江戸の仕組みは別の意味では進化しすぎていた。そこにどっぷりと浸かっていたため、新しい時代についていけなかった。明治に入ってもしばらくは江戸的な方法でやっていけたのだが…
もっと見る