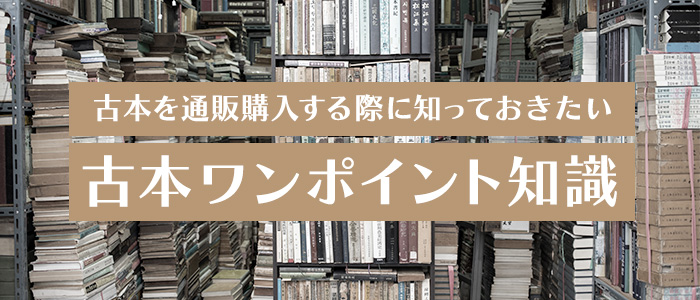
はじめて古本を購入する方に向けた古本の基礎知識を得ていただくための情報ページです。
「古本」と言っても多くのさまざまな定義があり一言では語り尽くすことはできませんが、一般的な情報をまとめています。
多くの人に古本に興味を持っていただき、古本を購入する一助になることを目的としています。
古本に関する用語・キーワード
ここでは、古本、和本、洋書に関する用語・キーワードを広くリストアップしました。
歴史から見る古本
古本を知るための関連コンテンツ

ズレて、ズラして、ズラされて――時代と価値観からのスピン・オフ(古本の読み方1)(シリーズ古書の世界)
古本の買い方ならぬ読み方/古本読書術というお題は成立するだろうか。古本の「買い方」本には意外と「読み方」が書かれていない。それらは、買い方+自分がオモシロいと思った古本の紹介、というパターンがほとんどで、「なんで自分がその本をオモシロいと思えたか」「どうしてその本がユニークだと気づけたか」といったメタな記述、つまり、購書術ならぬ読書術はあまり見当たらないのだ。気づいた結果は書いてあるのに、なぜ気づけたのか、プロセスがないのは、無意識的な動作だからだろう。そこで改めて考えてみた。古本とは、時代のズレを楽し…
もっと見る
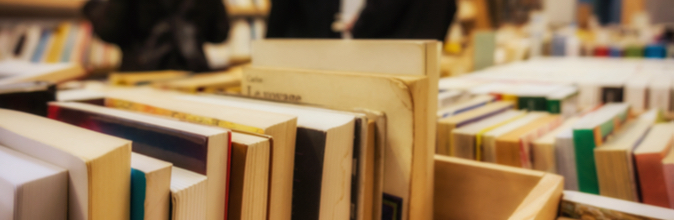
古書組合の役割と古書業界の仕組み(シリーズ古書の世界)
メルマガ読者の皆様ごきげんよう。皆様にはあまり興味が湧かない話題かもしれませんが、私としては少しでも多くの方々に古書業界の仕組みを知って頂き、その流通形態の一端と業者の不断の努力をご理解願うことで、古書店を見る視点が変わり、これまでより一層親しく古書ワールドをご利用頂くようになれば、たいへん有難く思っております。さて、東京古書組合は、正式には東京都古書籍商業協同組合と言い、本年、百周年を迎えます。大企業でも百年もの年月にわたり会社を存続させることは、大変難しいことだと言われています。では、なぜ消費経済の規模が比較的小さいと言われる古書業界が百年も存…
もっと見る
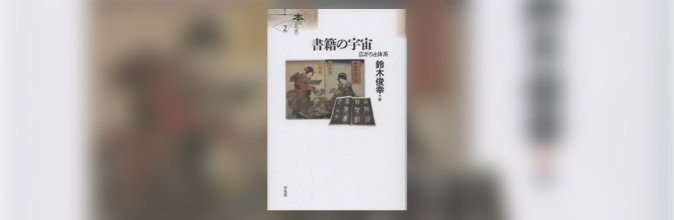
『シリーズ本の文化史2 書籍の宇宙−広がりと体系』(自著を語る)
このシリーズは、「書物・出版と社会変容」研究会を母体としている。2015年7月現在、すでに98回続いているこの研究会に参集してきた面々による蓄積、またそこから広がる人脈に基づいて発想された企画で、今のところ6巻までの原稿が出そろい(つつあり)、順次刊行の予定、本書はその第2巻である。内容は以下のとおり。/鈴木俊幸「書籍の宇宙」(総論)、堀川貴司「歴史と漢籍―輸入、書写、和刻―」、高木浩明「古活字版の世界―近世初期の書籍―」、岩坪充雄,「「書」の手本の本―法帖研究の意義と方法―」、佐藤貴裕「辞書から近世をみるために―節用集を中心に―」、柏崎順子「江戸版からみる一七世…
もっと見る
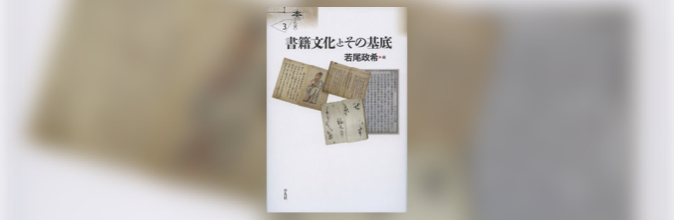
『シリーズ本の文化史3 書籍文化とその基底』(自著を語る)
平凡社創業100周年記念出版<シリーズ本の文化史>の第3巻として、『書籍文化とその基底』が刊行されました。1、2巻の配本が5月でしたので、お待たせしてしまいました。自己紹介を申しますと、私は一橋大学で日本史を教えるかたわら、「書物・出版と社会変容」研究会の呼びかけ人をしております。この研究会は、日本史研究とか文学研究といった専門分野の垣根を越えて、書籍・出版に関心をもつ者が集まるいわば「寄合」です。2003年8月から月例で開催し、2015年11月に100回を迎えました。10年以上も続いている理由は、何よりも楽しい(苦にならない)からなのですが、最近では、書籍や蔵書を散逸…
もっと見る
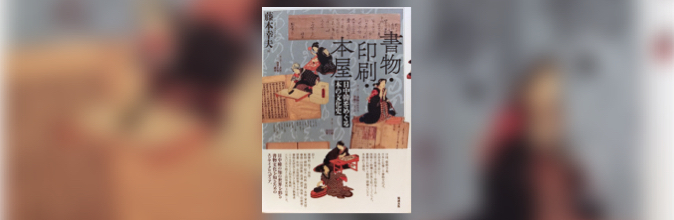
『書物・印刷・本屋 日中韓をめぐる本の文化史』(自著を語る)
本書は中国・朝鮮・日本の坊刻本、即ち民間の営利出版(日本では「町版」)を対象とし、その具体的な諸相を明らかにしようとするものである。坊刻本は庶民の擡頭と共に内容・意匠それぞれに工夫を凝らしつつ、深淵且つ絢爛たる出版文化を形成してきた。従来書籍を対象とする類書では、文学史的意義・理論的研究や内容分析、或いは版種や文字の異同等が中心であった。このような研究が高踏的とされ、今回のテーマのような分野は、ややもすれば低く見られ勝ちであったように筆者には思われる。敢えて申せば、全体として機能する人体の頭部だけを重んじ、日常生活を支える下半身を軽んじるに近い。…
もっと見る
今後公開予定のコンテンツ(準備中)
- ・古本の価格はどう決まる?
- ・古本を購入する際の注意点
- ・古本の扱い方、手入れなど
- ・古本の魅力


















