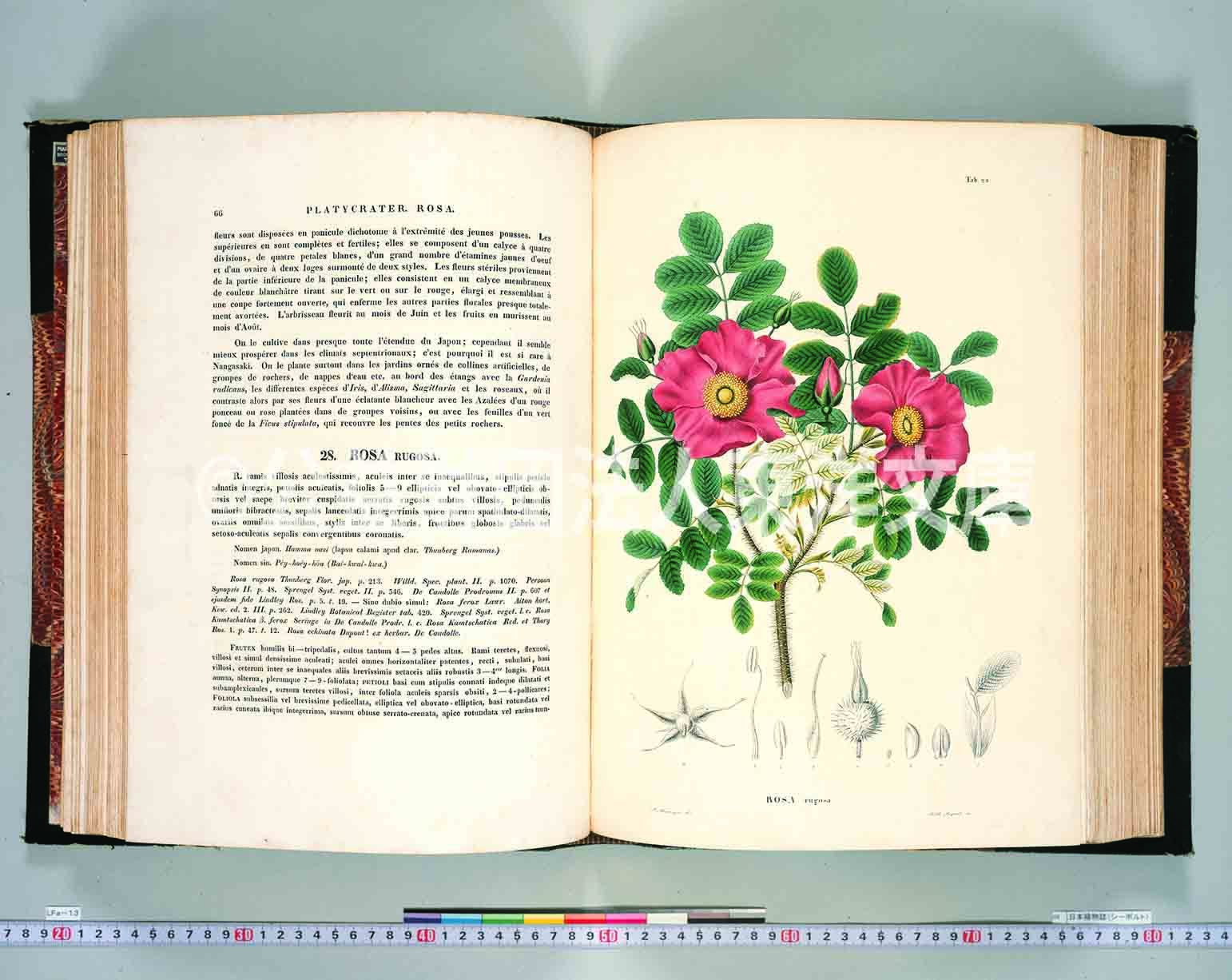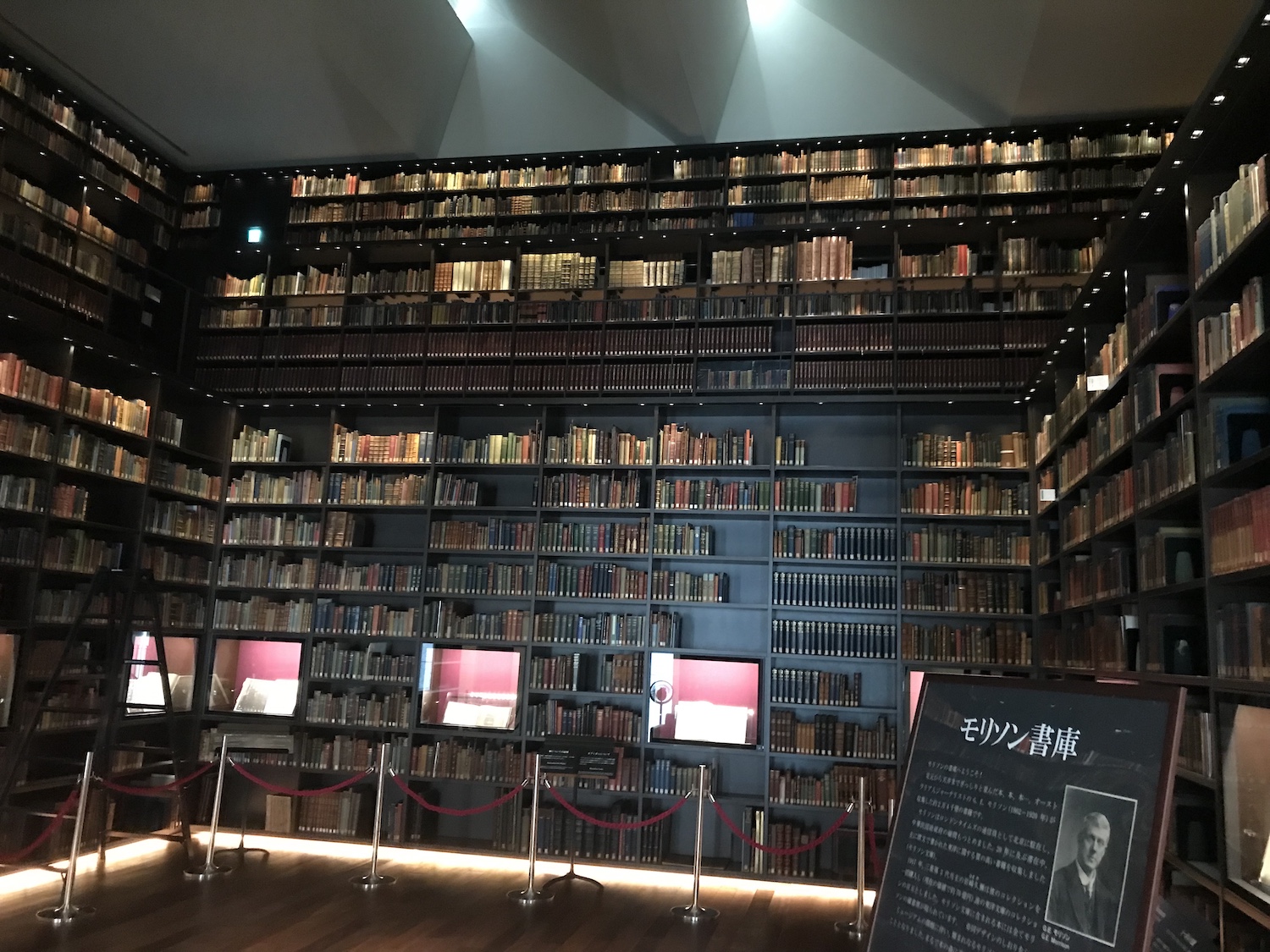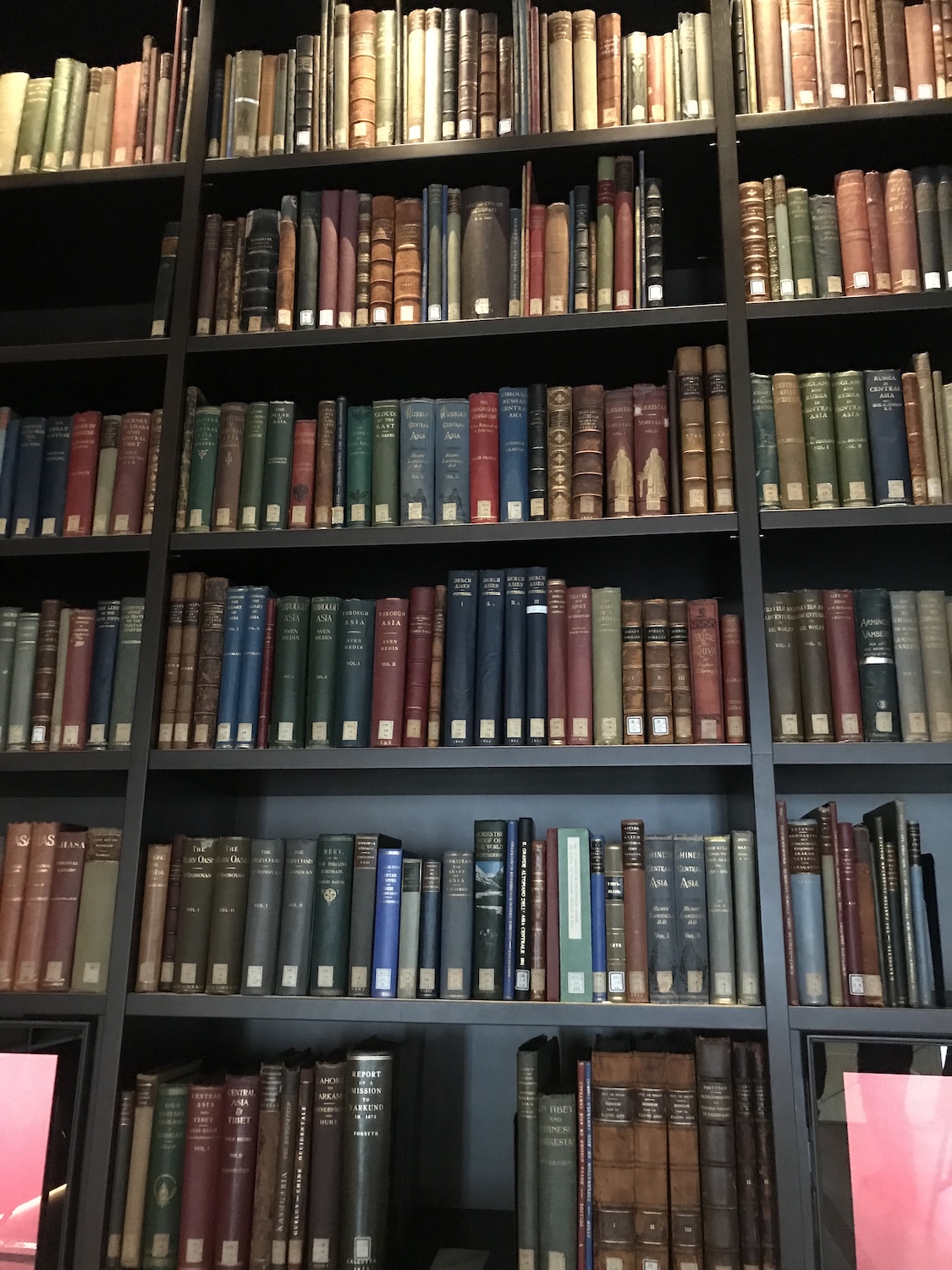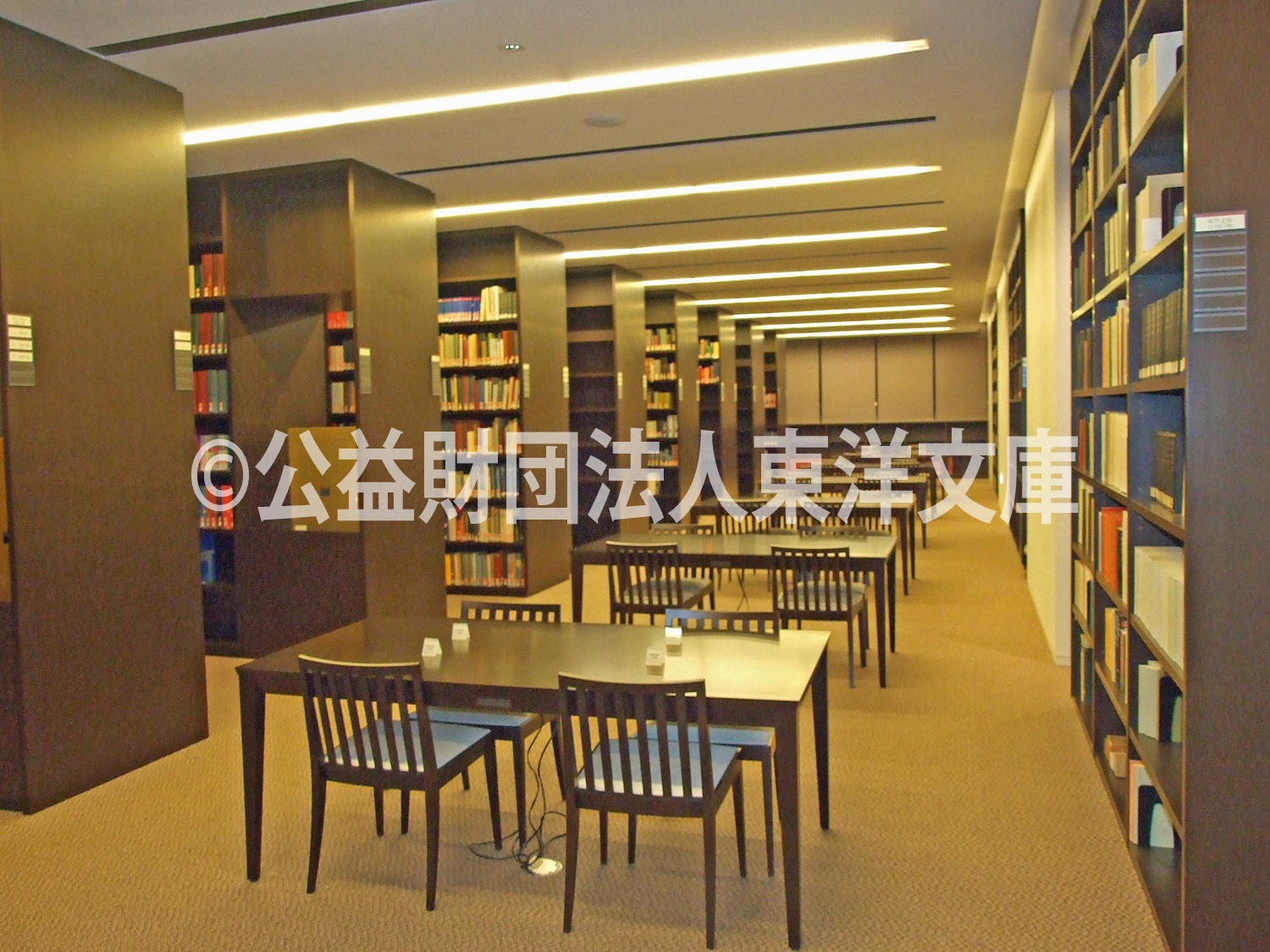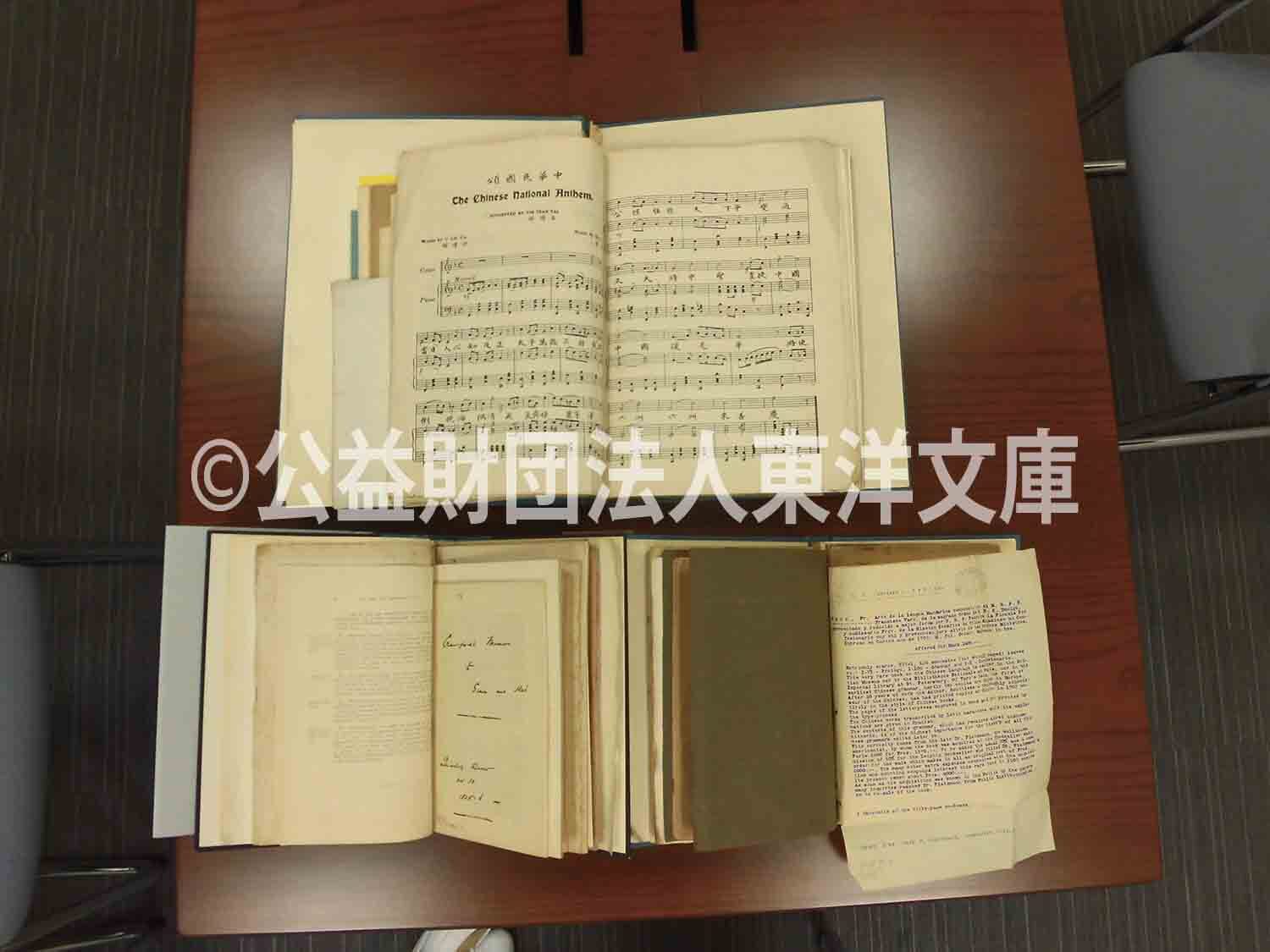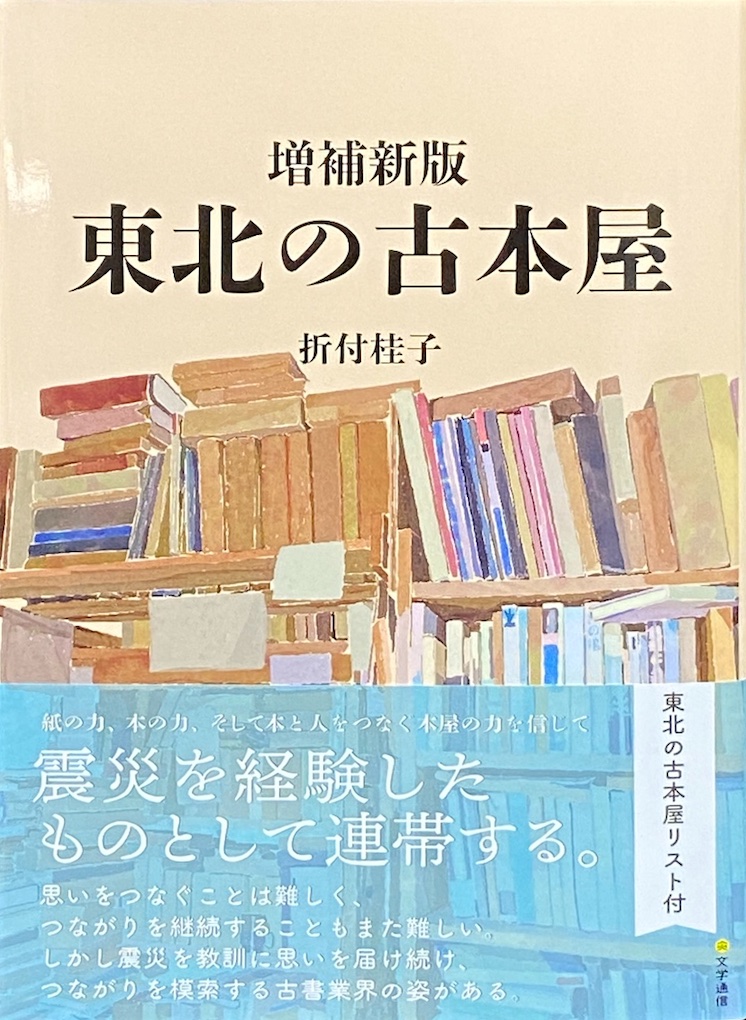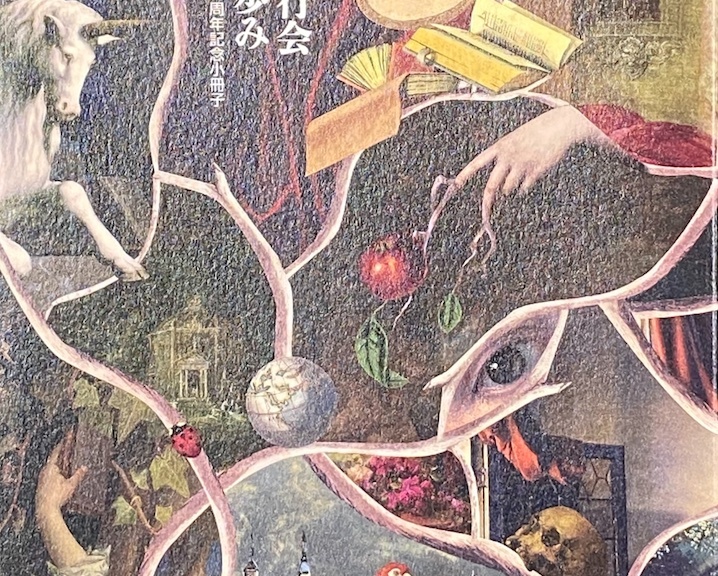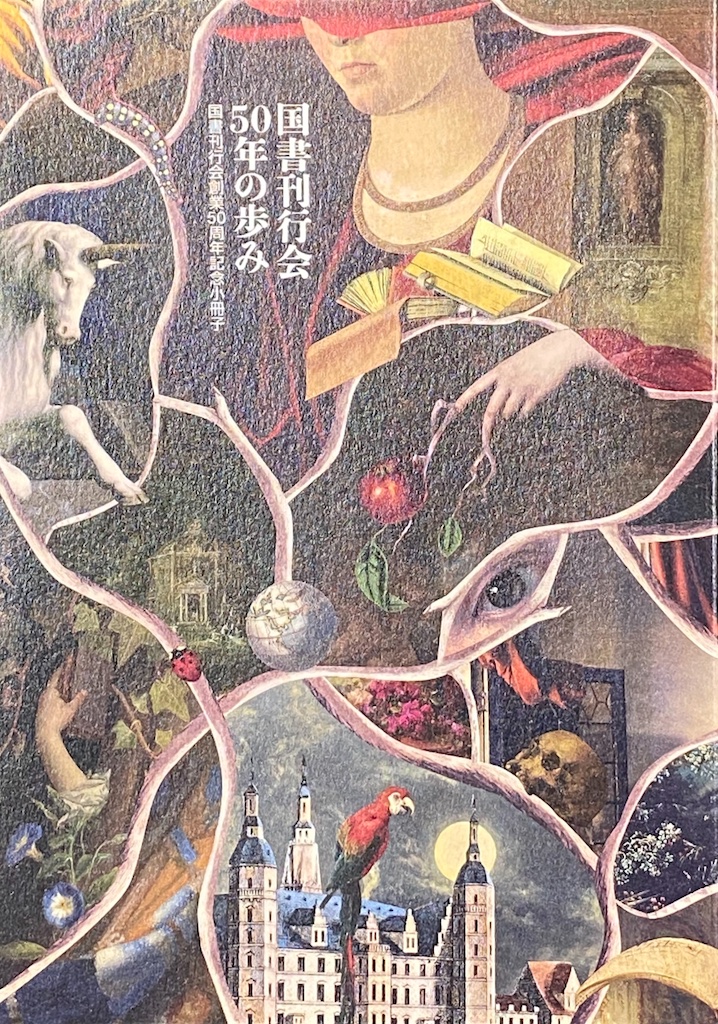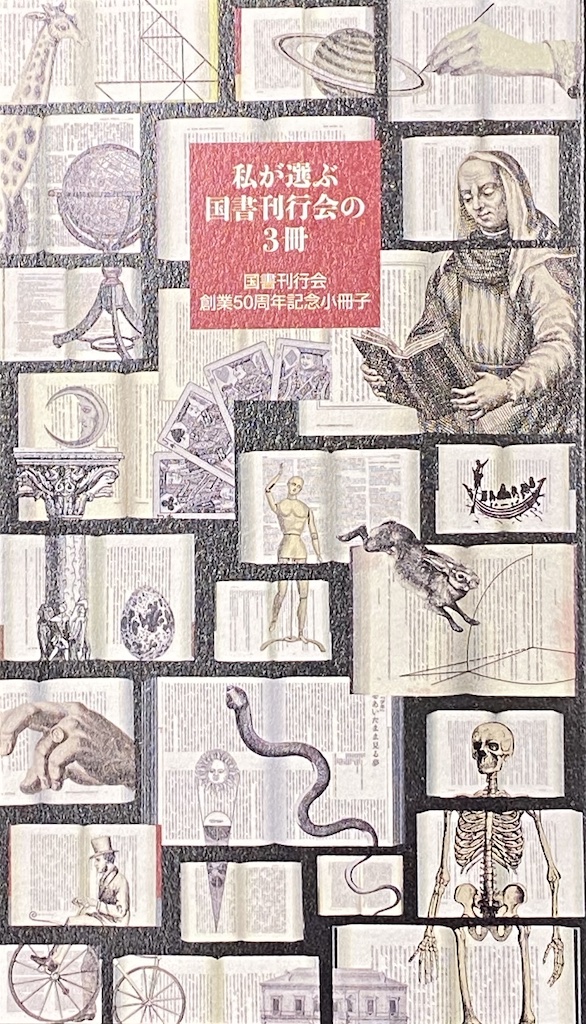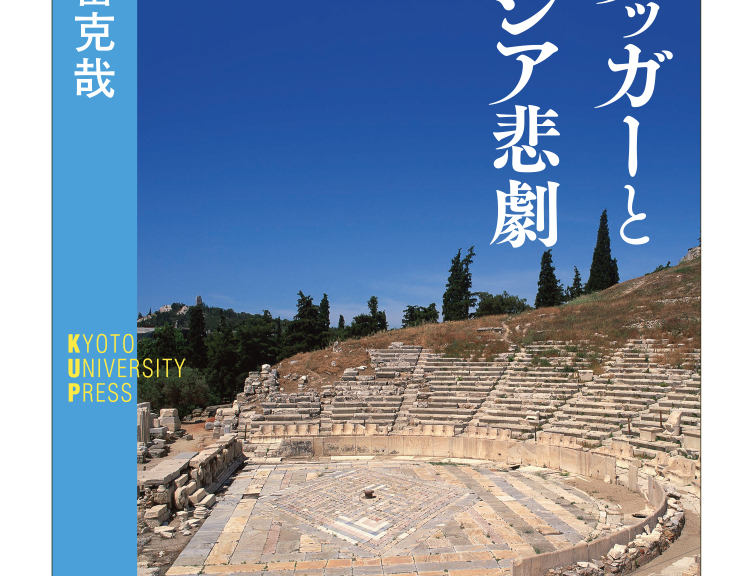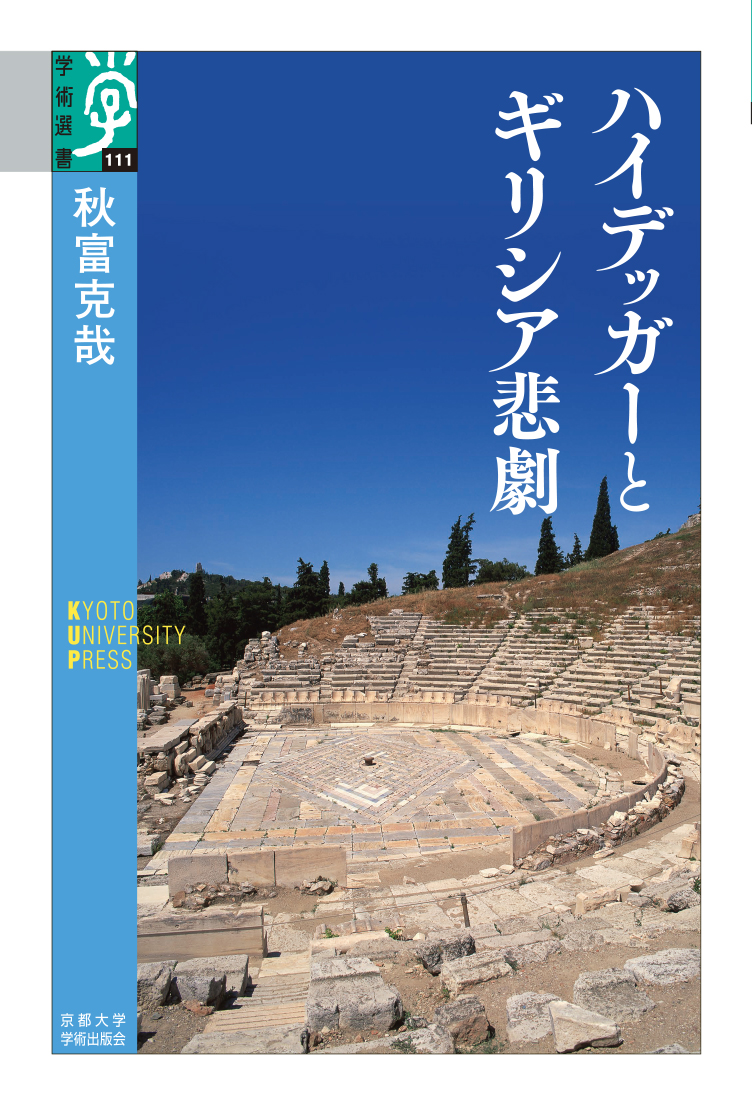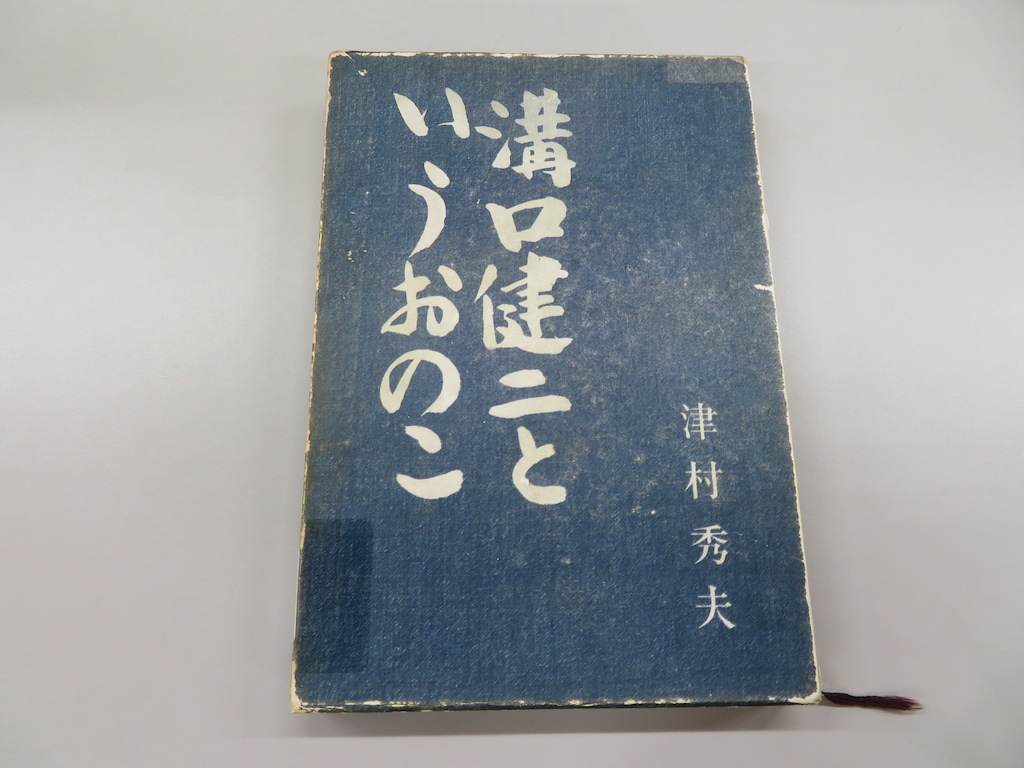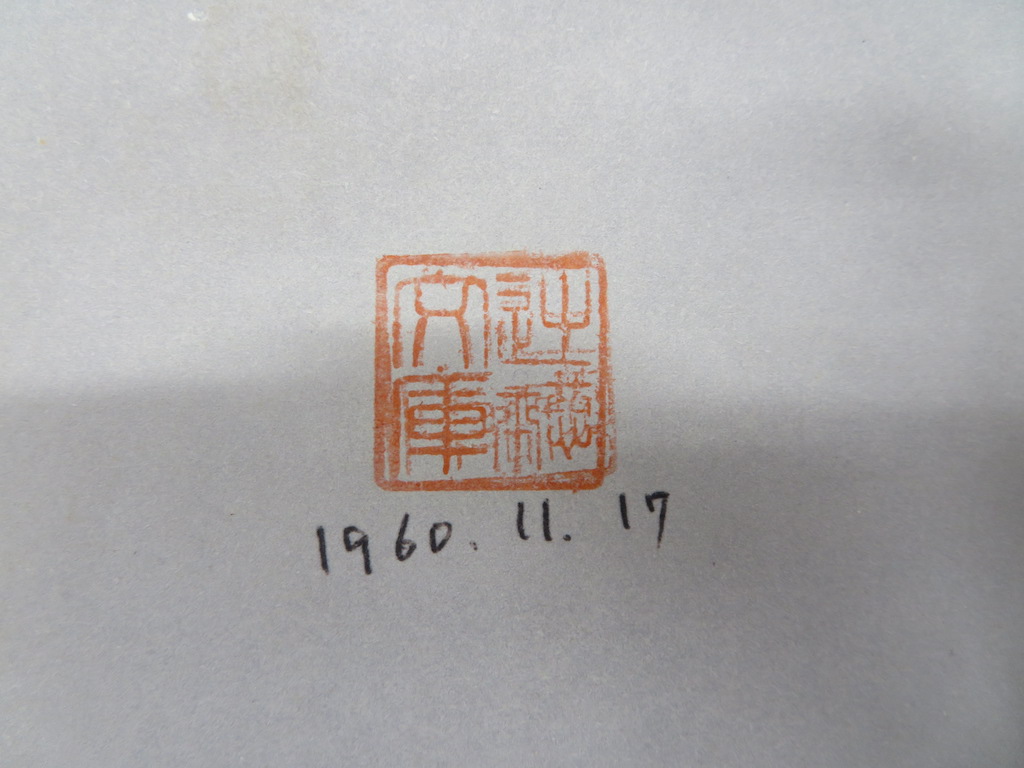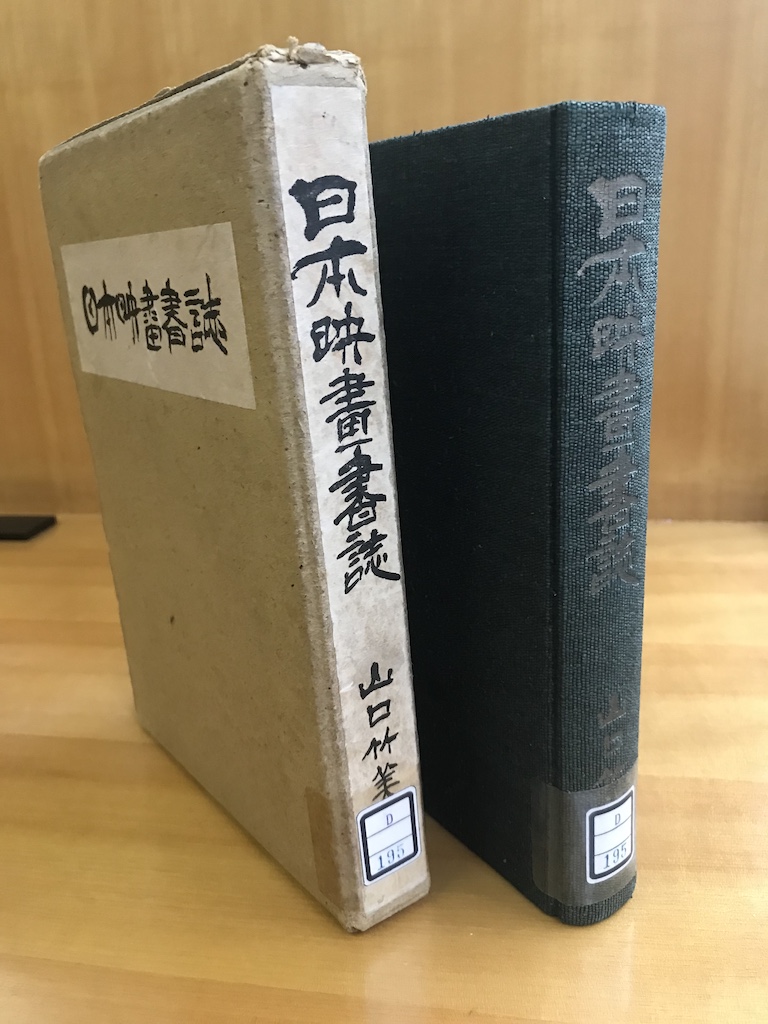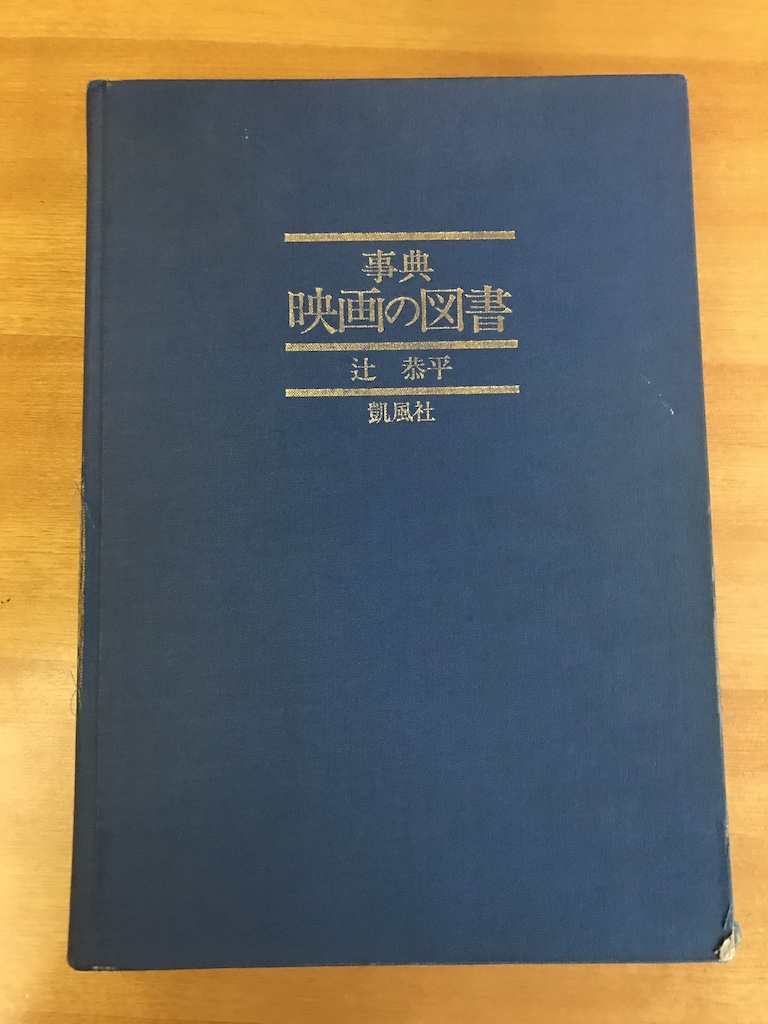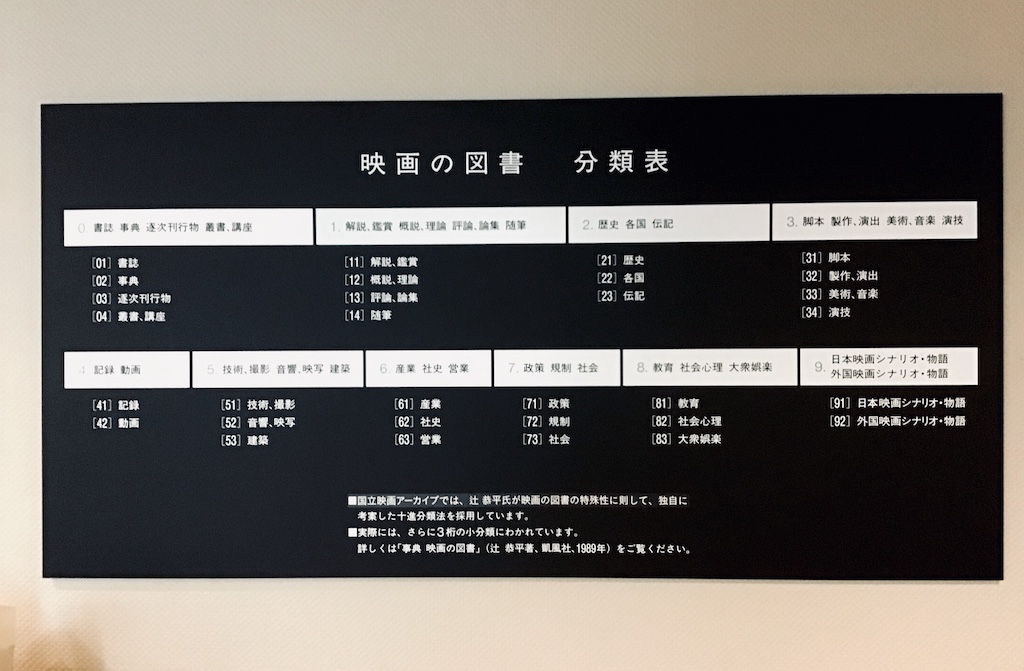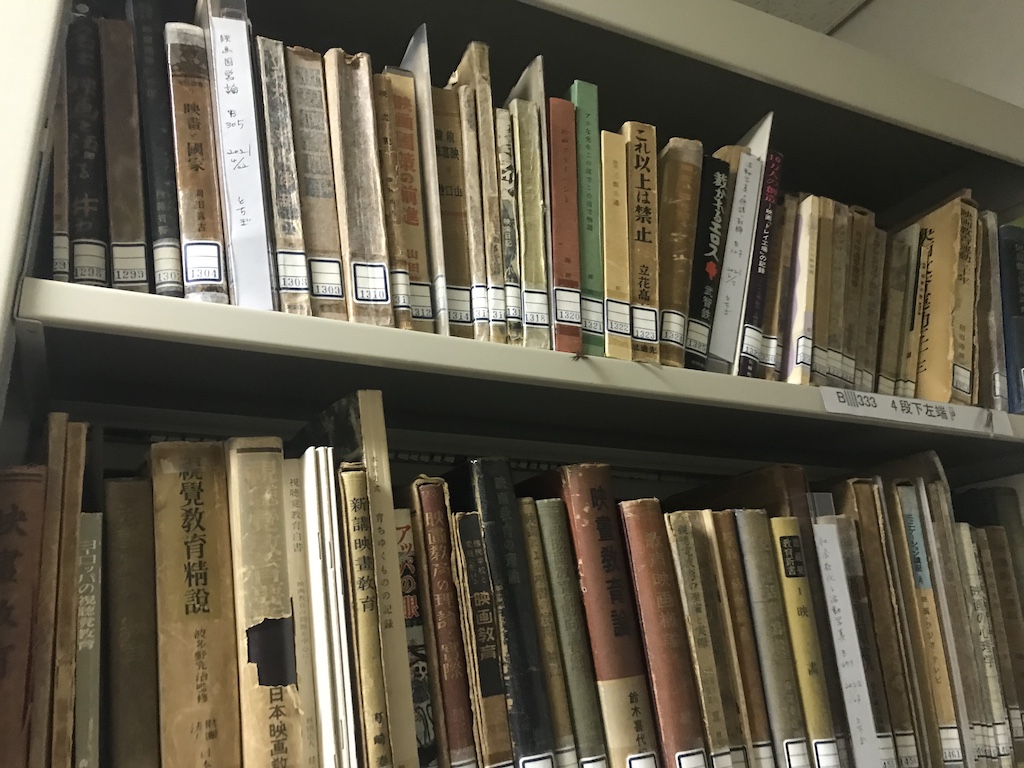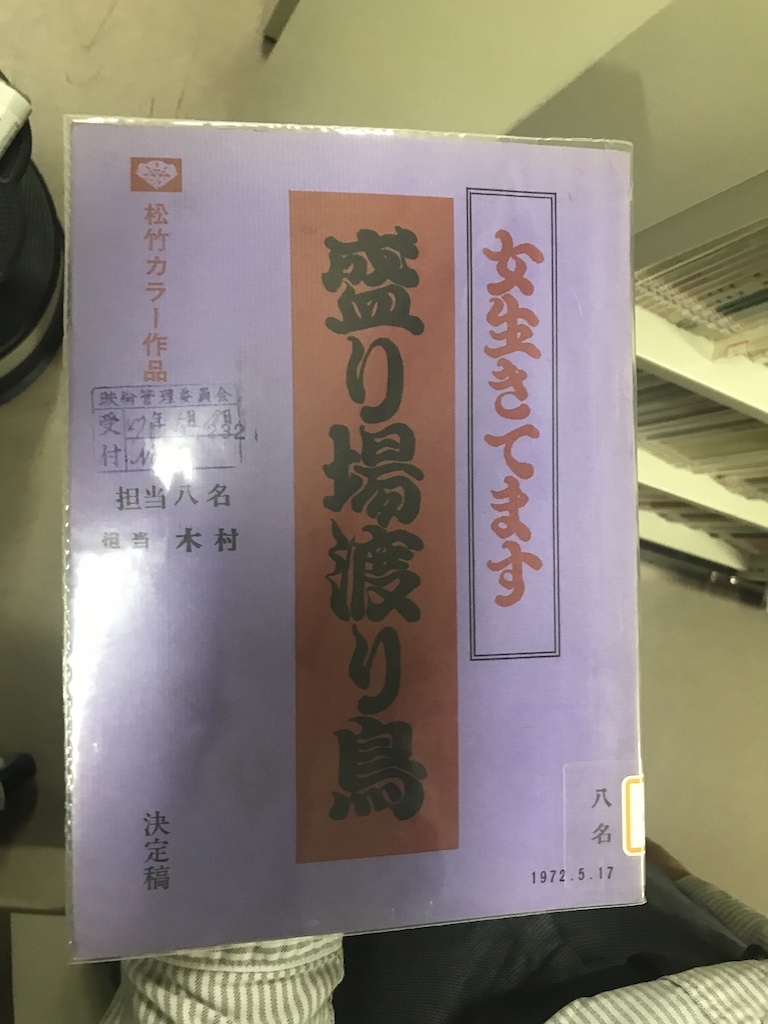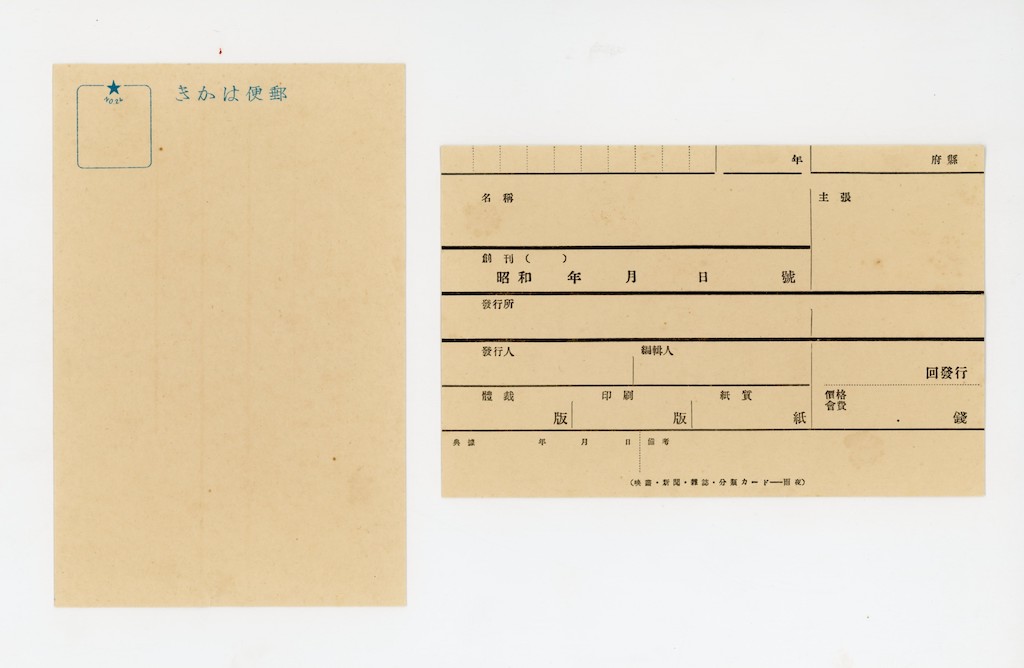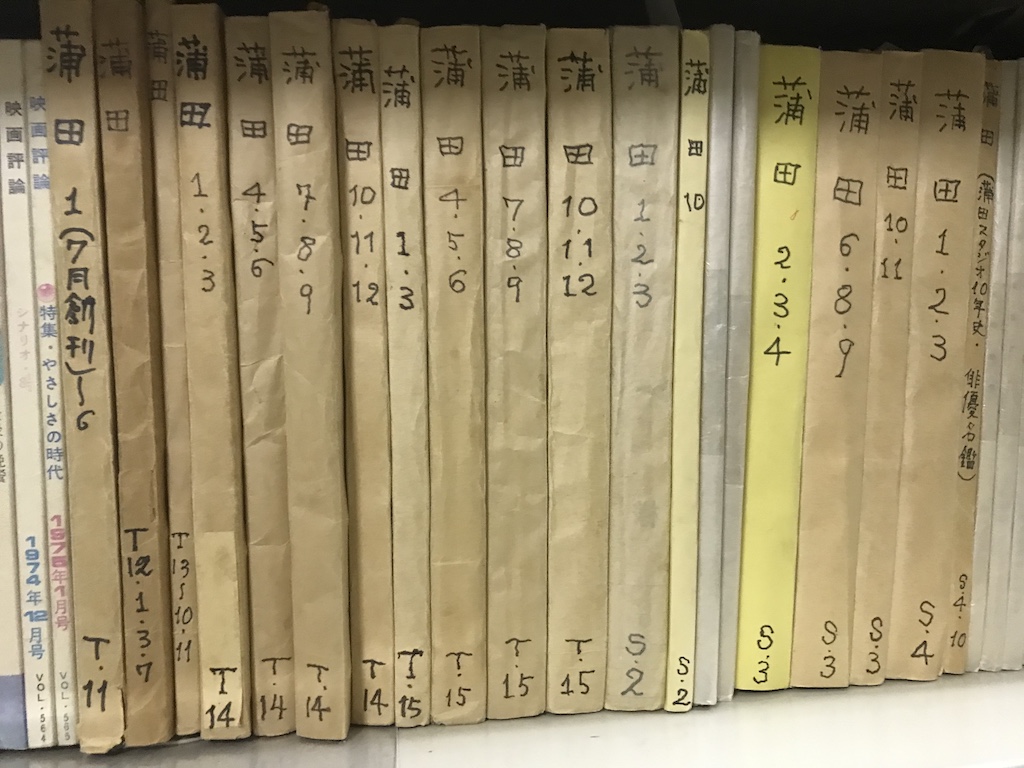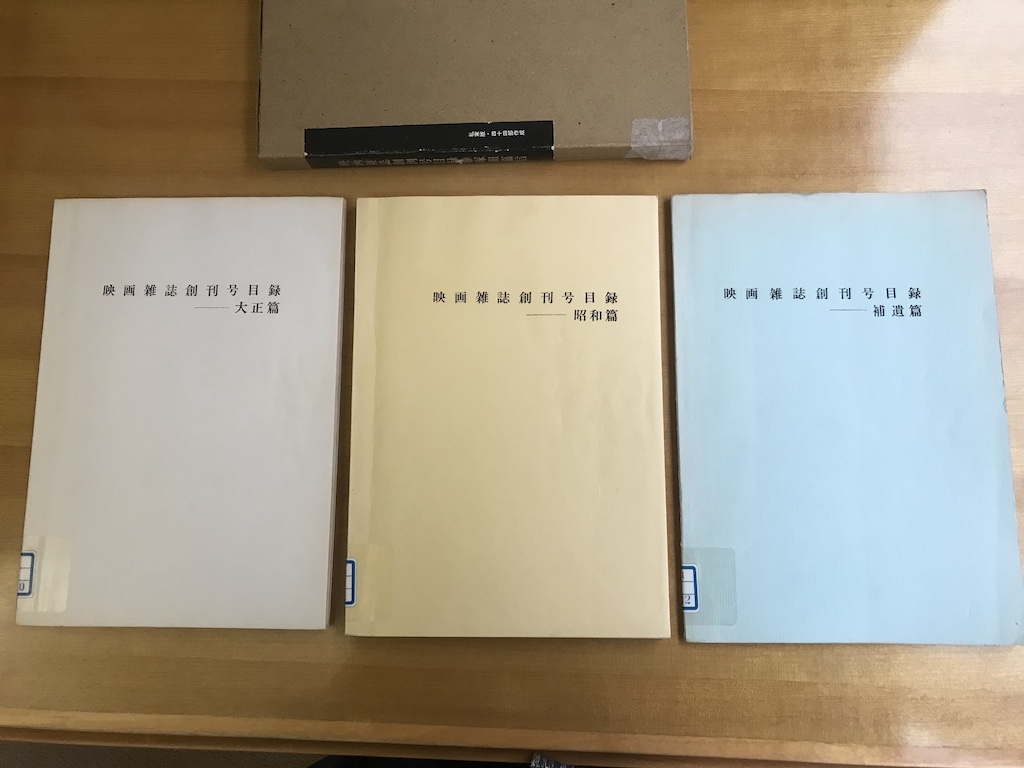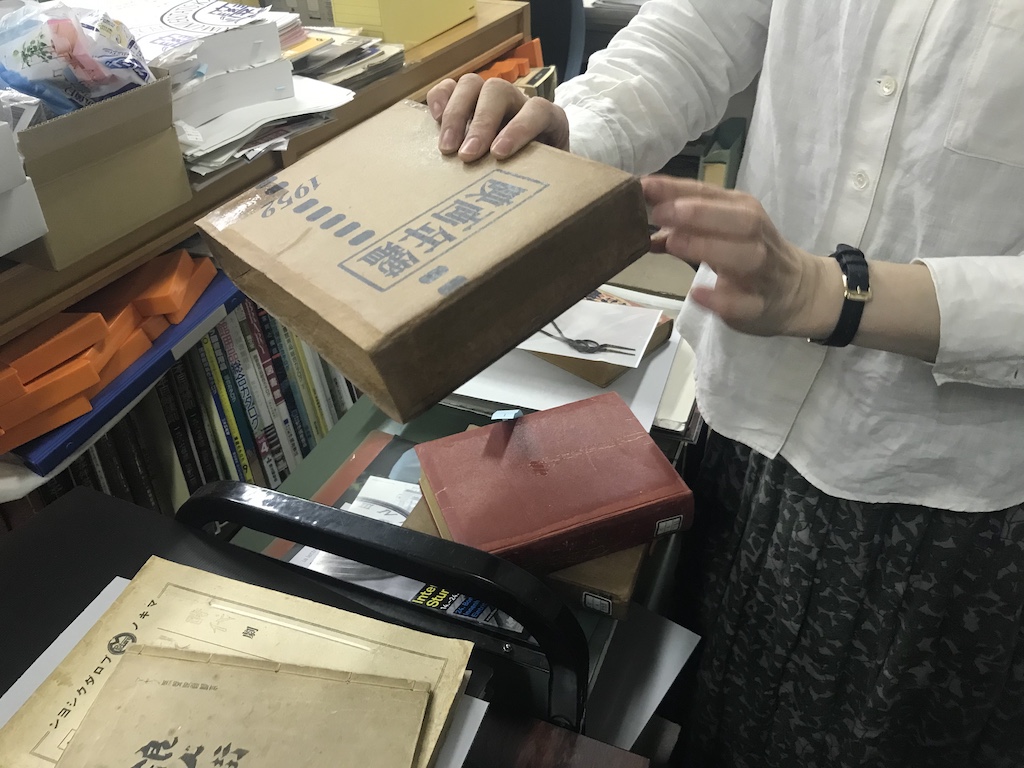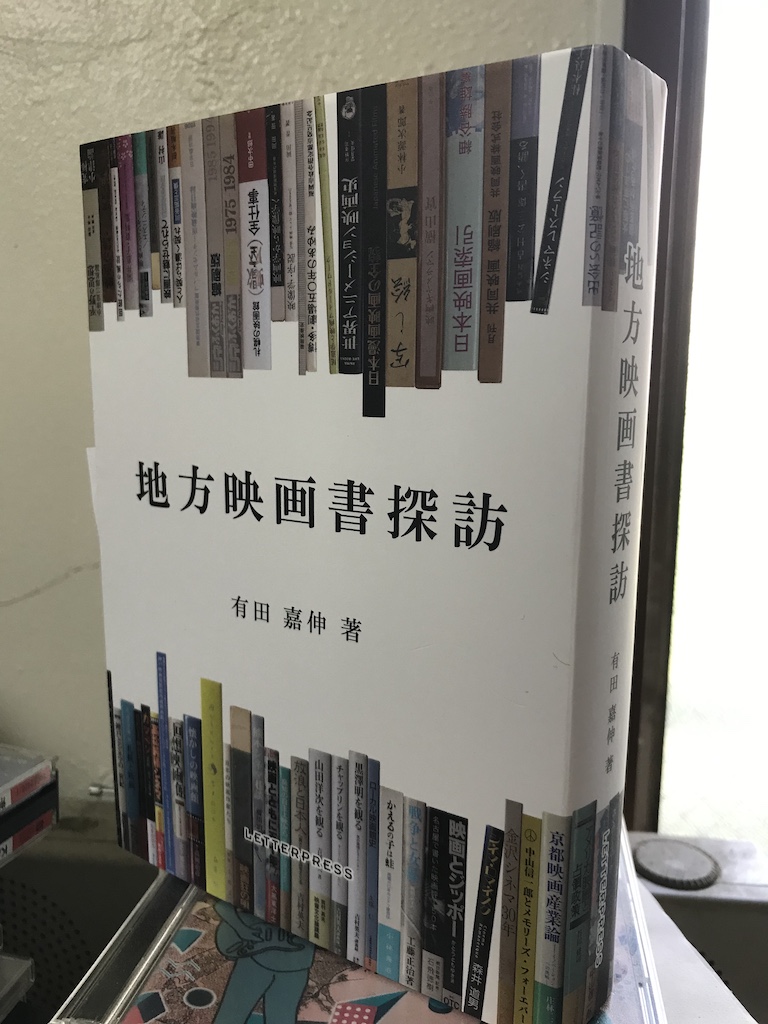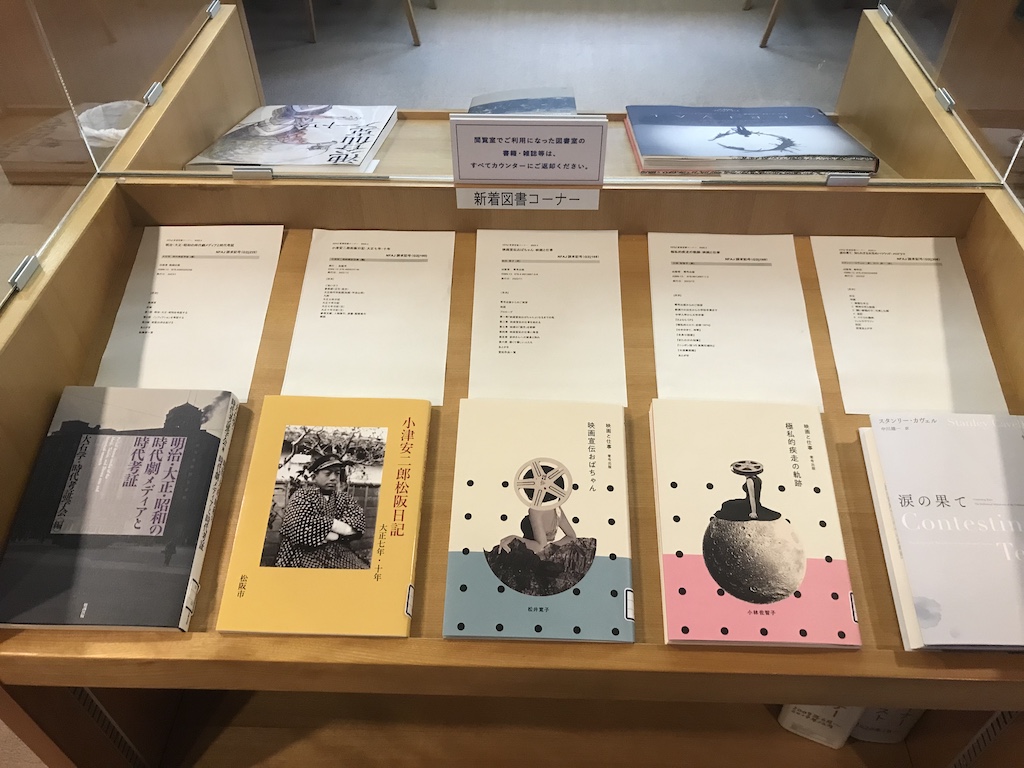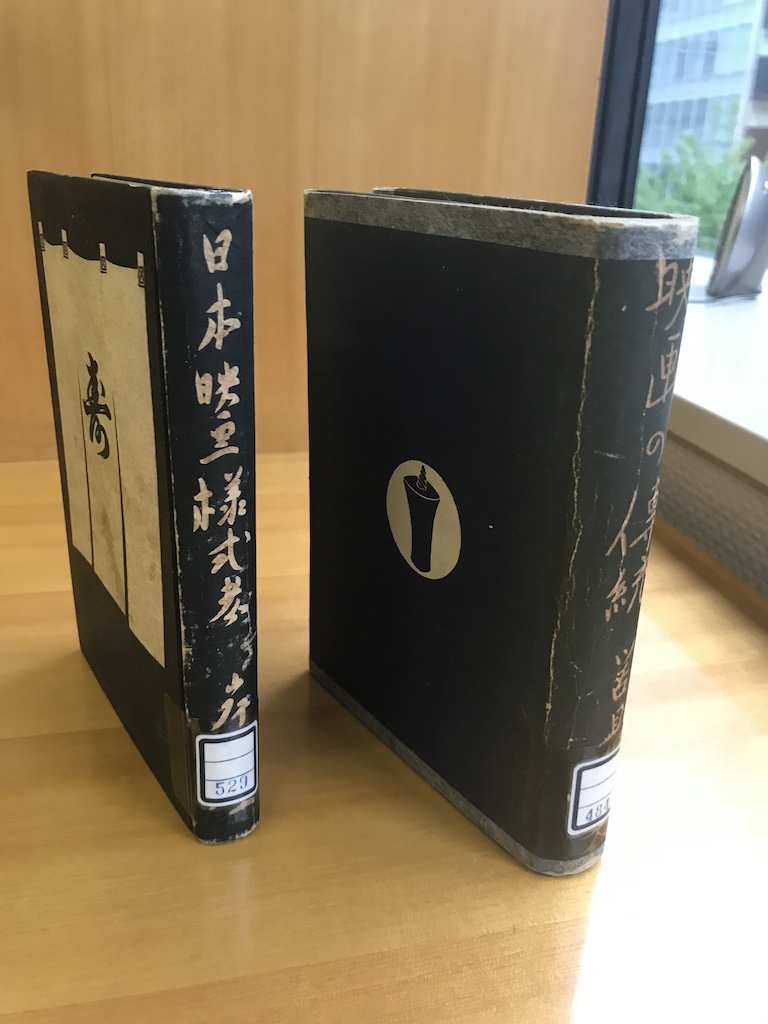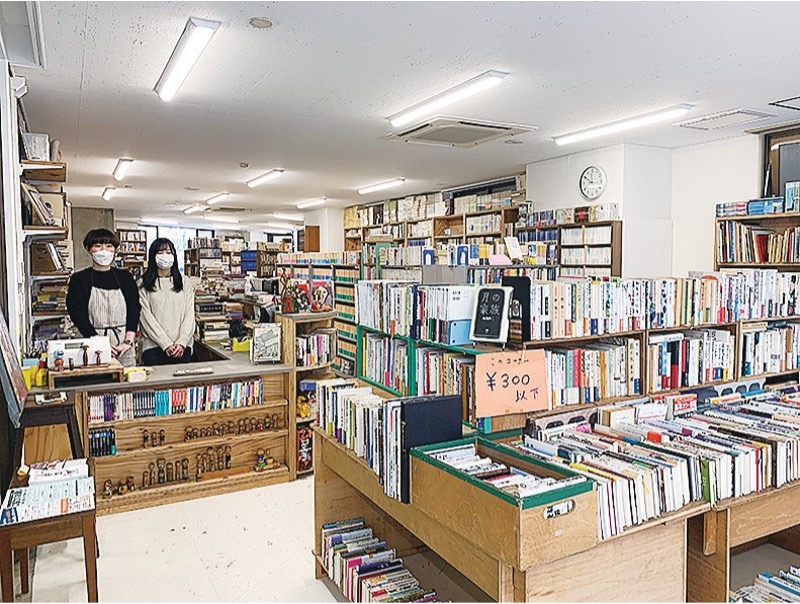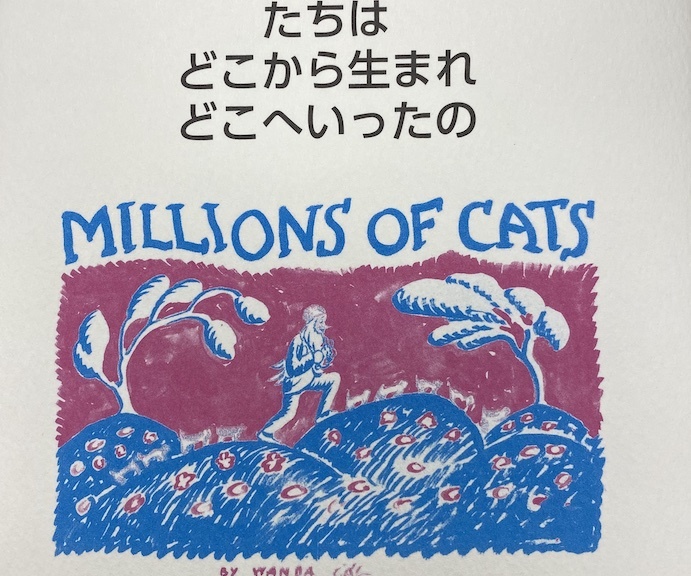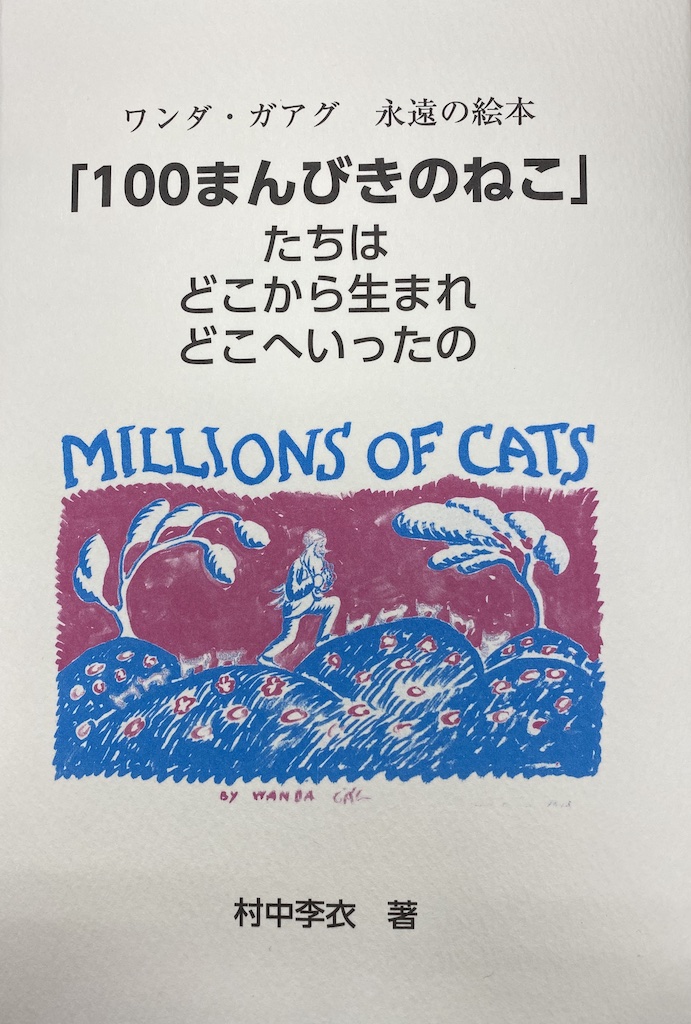。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。
古書市&古本まつり 第125号
。.☆.:* 通巻372・6月9日号 *:.☆. 。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━【古本屋でつなぐ東北(みちのく)余話】━━━━━━
東北の古本屋―広がる古本の裾野
(日本古書通信社)折付桂子
「古本屋でつなぐ東北」は『日本古書通信』二〇二二年八月~二〇二
三年二月号に連載した、東北の若い古本屋さんによるリレーエッセイで
す。自らの針路を決めた古本屋との出会い、一度読まれた本ならではの
想いを込めた売り方の工夫、地方の雄である古本屋三代目の覚悟、古本
屋仲間と交流し情報交換する休日、細々(こまごま)とした地元資料を
整理し伝える難しさ、震災と原発事故を乗越え被災地で頑張る日々、そ
して東北の古本屋として生きることはどういうことか、などについて七
人の店主が胸の内を語ってくれました。そこには、古本屋という仕事に
向き合う真摯な姿勢、地域に対する熱い思いが感じ取れます。一方で、
葛藤もあります。東北はいわば辺境の地。食品でも何でも良い物が中央
へと流れる中で、古本の世界でも同様の状況はあり、地元の資料を地元
で繋いでゆくことの厳しさを阿武隈書房さんが指摘していました。ただ、
そうした悩みを抱えつつも、地域と繋がり、仲間と繋がり、そして地元
の文化を伝えてゆこうという思いは、東日本大震災を経て、より強く
なったように感じます。
続きはこちら
https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=11660
━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見14】━━━━━━━━━
東洋文庫 本の旅の果てに
南陀楼綾繁
急に気温が上がった5月10日の午後、私は自転車で坂を上っていた。
目的地は本駒込の「東洋文庫」だ。岩崎久彌が1924年(大正13)に設
立した、東洋学の研究図書館である。
入り口の巨大な「MUSEUM」という文字を眺めて中に入る。入ってす
ぐがミュージアムショップになっており、その奥に展示室がある。
「フローラとファウナ 動植物の東西交流」という企画展が開催中で、
多くの人が訪れていた。
「新型コロナウイルス禍以来、来場者が落ち込んでいましたが、いまは
元に戻ってきました」と、普及展示部研究員・学芸員の篠木由喜さんは
話す。
続きはこちら
https://twitter.com/kawasusu
東洋文庫
http://www.toyo-bunko.or.jp/
※当ブログの全てまたは一部の無断複製・転載を禁じます
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「コショなひと」始めました
東京古書組合広報部では「コショなひと」というタイトルで動画
配信をスタート。
古書はもちろん面白いものがいっぱいですが、それを探し出して
売っている古書店主の面々も面白い!
こんなご時世だからお店で直接話が出来ない。だから動画で古書
店主たちの声を届けられればとの思いで始めました。
お店を閉めてやりきったという店主、売り上げに一喜一憂しない
店主、古本屋が使っている道具等々、普段店主同士でも話さない
ことも・・・
古書店の最強のコンテンツは古書店主だった!
是非、肩の力を入れ、覚悟の上ご覧ください(笑)
※今月の新コンテンツはありません。
YouTubeチャンネル「東京古書組合」
https://www.youtube.com/@Nihon-no-Furuhon-ya
━━━━━【6月9日~7月15日までの全国即売展情報】━━━━━
⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init
------------------------------
第2回 戸田書店やまがた古本まつり(山形県)
期間:2023/05/02~2023/07/02
場所:戸田書店山形店 特設会場
〒990-0885 山形市嶋北4丁目2-17
------------------------------
八文字屋書店SELVA店 第1回泉中央セルバ古書市(宮城県)
期間:2023/06/03~2023/06/20
場所:SELVA 2F センターコート
〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-4-1
------------------------------
書窓展(マド展)
期間:2023/06/09~2023/06/10
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
https://www.kosho.ne.jp/?p=571
------------------------------
好書会
期間:2023/06/10~2023/06/11
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
https://www.kosho.ne.jp/?p=620
------------------------------
アクロスモール新鎌ヶ谷古本市(千葉県)
期間:2023/06/10~2023/06/22
場所:アクロスモール新鎌ヶ谷 1F 中央エレベーター前
千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-12-1
------------------------------
『BOOK DAY とやま駅』(富山県)
期間:2023/06/10~2023/06/10
場所:富山駅南北自由通路(あいの風とやま鉄道中央口改札前)
https://bookdaytoyama.net/
------------------------------
新興古書大即売展
期間:2023/06/16~2023/06/17
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
https://www.kosho.ne.jp/?p=569
------------------------------
第103回シンフォニー古本まつり(岡山県)
期間:2023/06/21~2023/06/26
場所:岡山シンフォニービル1F 自由空間ガレリア
------------------------------
浦和宿古本いち(埼玉県)
期間:2023/06/22~2023/06/25
場所:さくら草通り(JR浦和駅西口 徒歩5分 マツモトキヨシ前)
https://twitter.com/urawajuku
------------------------------
フジサワ古書フェア(神奈川県)
期間:2023/06/22~2023/07/19
場所:有隣堂藤沢店4階ミニ催事場 JR藤沢駅南口フジサワ名店ビル4階
http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm
------------------------------
オールデイズクラブ古書即売会(愛知県)
期間:2023/06/23~2023/06/25
場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12
https://hon-ya.net/
------------------------------
ぐろりや会
期間:2023/06/23~2023/06/24
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
http://www.gloriakai.jp/
------------------------------
高円寺優書会 ※催事が変更になりました(「古書愛好会」からの変更」)
期間:2023/06/24~2023/06/25
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
https://www.kosho.ne.jp/?p=726
------------------------------
フィールズ南柏 古本市(千葉県)
期間:2023/06/27~2023/07/18
場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場 柏市南柏中央6-7
------------------------------
東京愛書会
期間:2023/06/30~2023/07/01
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
http://aisyokai.blog.fc2.com/
------------------------------
大均一祭
期間:2023/07/01~2023/07/03
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
https://www.kosho.ne.jp/?p=622
------------------------------
西部古書展書心会
期間:2023/07/07~2023/07/09
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
https://www.kosho.ne.jp/?p=563
------------------------------
趣味の古書展
期間:2023/07/14~2023/07/15
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
https://www.kosho.tokyo
------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信
を希望された方にお送りしています。
ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。
【日本の古本屋】は全国998書店参加、データ約656万点掲載
の古書籍データベースです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
見逃したメールマガジンはここからチェック!
【バックナンバーコーナー】
https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=43
┌─────────────────────────┐
次回は2023年6月下旬頃発行です。お楽しみに!
└─────────────────────────┘
*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*
全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です
https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner
==============================
日本の古本屋メールマガジンその372 2023.6.9
【発行】
東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋」事業部
東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館
URL https://www.kosho.or.jp/
【発行者】
広報部・編集長:藤原栄志郎
==============================
・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら
https://www.kosho.or.jp/mypage/
・このメールアドレスは配信専用です。
返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。
・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。
・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は
melma@kosho.ne.jp までお願い致します。
・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い
いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に
遅れる場合もございます。ご了承下さい。
============================================================
☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・
============================================================