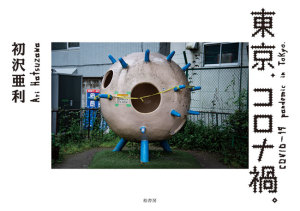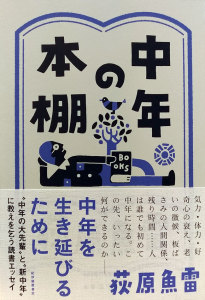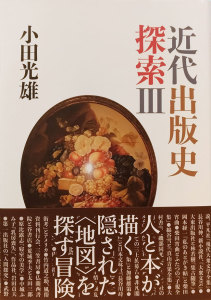第21回 三原宏元さん 「昭和40年代」を追い求めるひと南陀楼綾繁 |
| 新型コロナウイルスが拡大し、自宅で過ごさざるを得ない日々が続いた時期、フェイスブックに「7日間ブックカバーチャレンジ」というものが現れた。好きな本の表紙画像を1日1冊、7日間投稿するというもので、私自身は誘われることも自分から参加することもなかったが、流れていく表紙を眺めていた。その中で、一番面白かったのが、三原宏元さんの投稿だった。 三原さんは7日間という期間を無視して、ご自身が集めてきた片山健やロバート・クラムに関する本や雑誌、レコードの画像を延々とアップしていた。次々に出てくる画像に圧倒された。どうやってこれだけのコレクションになったのか、話を聞きたいと思った。 三原さんは港区南青山で〈ビリケン商会〉という、古いおもちゃを扱う店を営んでいる。その奥には〈ビリケンギャラリー〉があり、画家や漫画家の展示を行う。また、ビリケン出版として絵本などを刊行している。この小さな場所は、いくつもの顔を持っているのだ。 1952年、福岡県八幡市(現・北九州市)に生まれる。父は地元企業である安川電機に勤めていた。「父は絵が上手かったです。会社の作業場でこっそり軍艦をつくってくれたこともあります」。両親と祖父、叔父、5歳下の弟と小さな家で暮らしていた。大家族であり、母は洋裁の内職をしていたため、絵本を読んでもらった記憶はないという。 小学6年生のとき、埼玉県の入間市に引っ越す。「北九州は都会だったから、いきなり何もない茶畑のなかに来た感じだったね」と三原さんは笑う。中学校に入ると、サッカー部、テニス部、美術部などに属する。レーシングカーや鉄道模型が好きで、自分で改造したりした。 それからの三原さんは、サブカルチャーまっしぐら。池袋や新宿で映画を観て、ビートルズのレコードを聴く。『平凡パンチ』『メンズクラブ』などの雑誌を読み、横尾忠則、伊坂芳太郎、柳生弦一郎らのイラストレーションに魅かれる。 そんな三原さんが古本を集めるようになったのは、片山健がきっかけだった。 一方、ロバート・クラムを知ったのは、雑誌『宝島』の記事だった。 そうやって集めた本は、この部屋だけでおさまらず、自宅と倉庫にあふれている。「下手に整理すると見つからない。積み重なった山のままにしておく方が見つかりやすいんです」と云うが、ホントだろうか? 最後に三原さんは、幸せだった日のことを話してくれた。 南陀楼綾繁 ツイッター
|
|
Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |
2020年9月25日号 第307号
■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■
。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。
。.☆.:* その307・9月25日号 *:.☆. 。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信
を希望された方にお送りしています。
ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。
【日本の古本屋】は全国930書店参加、データ約600万点掲載
の古書籍データベースです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆INDEX☆
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
1.転ばぬ先の『中年の本棚』 荻原魚雷
2.『東京、コロナ禍。』について 初沢亜利
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
━━━━━━━━━━━【自著を語る(247)】━━━━━━━━━
転ばぬ先の『中年の本棚』
荻原魚雷
一九八九年、大学在学中の十九歳のときからフリーライターの仕
事をはじめ、三十余年になる。これまでは主に古本のエッセイを書
いてきたが、最近は街道や宿場町の本の蒐集に追われている。
「中年の本棚」は二〇一三年の春、四十三歳から『scripta』で連載
をはじめた。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6177
『中年の本棚』 荻原魚雷 著
紀伊國屋書店出版部 定価 1,700円+税 好評発売中!
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784314011754
文壇高円寺
http://gyorai.blogspot.com/
━━━━━━━━━━━【自著を語る(248)】━━━━━━━━━
『東京、コロナ禍。』について
初沢亜利
2020年頭から街に出てスナップ写真を撮り始めた。オリンピック
イヤーの東京を撮ってみよう、という動機からのスタートだった。
様々な変化が予測できた。春くらいからはメディアの煽りを食っ
て、表向きオリンピックムード一色になっていただろう。その影
で白けている人々の日常もあったはずだ。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6302
『東京、コロナ禍。』
柏書房 定価:1,800円+税 好評発売中!
http://www.kashiwashobo.co.jp/book/b517597.html
━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━
『浮世絵の解剖図鑑』 牧野 健太郎 著
エクスナレッジ刊 定価 1,600円+税 好評発売中!
https://www.xknowledge.co.jp/book/9784767827841
『活動写真弁史』 片岡一郎 著
共和国刊 予価:7500円+税 10月25日発売予定
https://www.ed-republica.com/
『谷崎潤一郎と書物』 山中剛史 著
秀明大学出版会刊 2800円+税 10月1日発売予定
http://shuppankai.s-h-i.jp/
━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━
9月~10月の即売展情報
※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている
即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。
お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
見逃したメールマガジンはここからチェック!
【バックナンバーコーナー】
https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33
┌─────────────────────────┐
次回は2020年10月中旬頃発行です。お楽しみに!
└─────────────────────────┘
*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*
全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です
https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner
==============================
日本の古本屋メールマガジンその307 2020.9.25
【発行】
東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」
東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館
URL http://www.kosho.or.jp/
【発行者】
広報部:志賀浩二
編集長:藤原栄志郎
==============================

『東京、コロナ禍。』について
『東京、コロナ禍。』について初沢亜利 |
| 2020年頭から街に出てスナップ写真を撮り始めた。オリンピックイヤーの東京を撮ってみよう、という動機からのスタートだった。様々な変化が予測できた。春くらいからはメディアの煽りを食って、表向きオリンピックムード一色になっていただろう。その影で白けている人々の日常もあったはずだ。これまで以上に様々な国からの来訪者も景色に加わっただろう。1月は武漢のニュースに終始し、国内への感染流入を食い止めるべく政府の対応が求められた。すでに雲行きは怪しかった。 2月19日に横浜港に停泊していたダイヤモンド・プリンセス号から、陰性と認められた人々が下船を開始し、公共交通機関を使い全国に帰った乗客から、その後次々と陽性反応が出た。この辺りがコロナ禍のスタートであろうか? 学生時代から飲んでいた新宿ゴールデン街の変化は忘れがたい。威勢よく自由や個人主義、反権力を語っていた無頼派気取りの記者やジャーナリストが一瞬にして消え去り、多くは国による国民の行動規制を待望し、自由を呆気なく手放してしまった。緊急事態宣言下においても連日街へ出て写真を撮り続けたのは、そのような風潮への異議申し立てでもあった。 一方で、コロナ禍などと言う実体の摑みにくいテーマを掲げた写真家は少なかったようだ。不謹慎かつ無責任な写真家が少なかった、と言うことか。しかし、コロナ禍の風景、人間模様は、誰かが記録しておくべきではないか。不要不急とは言い切れない。報道的な視点だけではない、ささやかな日常を記録することは後世に意味をもつはずだ。都市の感情の記録、東京人の自画像として。 スナップ写真一枚一枚について撮影者自らが語ることは実に難しい。なぜなら、絵画や現代美術、小説などと違い、作品の隅々まで統制不可能であり、意図以外のものを多分に含むことが、表現の前提になっているからだ。その場で起きたことの真相が判らぬままシャッターを切り、立ち去ることも多い。写真を見た人に、状況について質問されても、答えようがない。そのような余白や余韻を見る側同様に撮影者自身も楽しんでいたりする。 自身が拠点する東京を写すことは楽ではなかった。ここ10年、被災地東北、北朝鮮、沖縄、香港と外部を写してきたが、幼少期から住み慣れており、いつでも目の前に「見えている」東京を改めて「見る」ことは、他の地域以上に想像力と集中力を必要とした。カメラ越しに見える東京景は漠然としていたが、2020年上半期、一層モヤモヤとした不安に覆われていた。ロックダウンすることもなく、「自粛」という名の国民の自由意思に任されたため、受け止め方や行動に誤差が生じた。写真集「東京、コロナ禍。」は誤差の幅を写した、曖昧さを多く含んだ日本の首都ならではの光景を写す一冊となった。他国のコロナ禍写真との比較において、その意味はいずれ顕著になるだろう。 写真を鏡として使うか、窓として使うか?という定番の議論がある。私の内面の投影としての写真か、人や社会を私とはなるべく切り離して掬い取り定着させる写真か。両者は明確に線引きできるものではないが、私はこれからも、社会を写す窓として写真表現を継続して行く。そして自らの意思の反映とは言い切れない、偶然写るスナップ写真を追求し精度を高めていきたい。 写真家自身が、半年間で何を見てもコロナに引き付けて事象を見てしまう癖がついてしまった。時間と共に、それも洗い流されていくだろう。焦らず淡々と歩き続ける日々はまだまだ続く。 ▼3月29日 日曜日の上野恩賜公園 前々日より桜並木が閉鎖された。 ▼三軒茶屋の公園 また舞台で踊れる日まで、と黙々と練習に励んでいた。 ▼5月29日 医療従事者への敬意と感謝をしめすため、ブルーインパルスが東京上空を飛行した。 『東京、コロナ禍。』 |
|
Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |
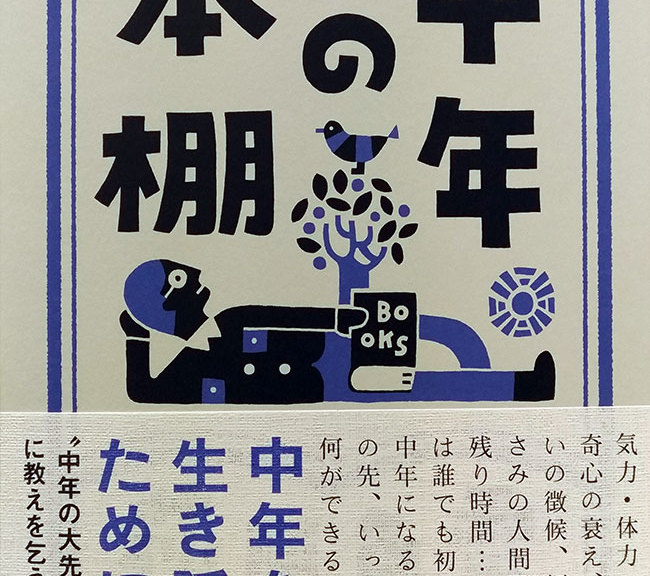
転ばぬ先の『中年の本棚』
転ばぬ先の『中年の本棚』荻原魚雷 |
| 一九八九年、大学在学中の十九歳のときからフリーライターの仕事をはじめ、三十余年になる。これまでは主に古本のエッセイを書いてきたが、最近は街道や宿場町の本の蒐集に追われている。 「中年の本棚」は二〇一三年の春、四十三歳から『scripta』で連載をはじめた。 今から八年前、東京・高円寺のコクテイル書房のトークショーに出席したとき、「三十代の半ばくらいから中年本を集めているんですよ」といったところ、この日、店に来ていた紀伊國屋書店のOさんに「中年本の連載をしませんか」と声をかけられた。 第一回目は野村克也と扇谷正造と吉川英治と源氏鶏太の本について書いた。題して「『四十初惑』考」。彼らの書物の中で「四十不惑」ではなく「四十初惑」という言葉をつかっている。中年になっても、迷い、戸惑うことがわかり、安心した。 目先の問題が片づけても片づけても次の問題が浮上する。連載中、郷里の三重にいる父の死や母の入院による遠距離介護を経験したり、腰痛になったり、五十肩になったりもした。 そのあたりも中年期の読書の面白さだろう。 こうした自分の心身の小さな変化を愉しむくらいの気持でいたほうがいい。 『中年の本棚』 荻原魚雷 著 |
|
Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |
2020年9月10日 第306号
■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■
。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。
古書市&古本まつり 第92号
。.☆.:* 通巻306・9月10日号 *:.☆. 。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━
古書店開業記3(コロナ禍の中で)
古本&カフェ じゃらん亭 内山武明
実家の19号台風の後片付けが済んでから、平常の営業に戻し、
年が明けて、2月頃からレコード寄席や浮世絵に関するイベントな
どを行いました。徐々にお客さんや買取りも増えてきました。季節
も暖かくなってきて、これからという時に、コロナの流行が始まり、
来客数の低下、古書組合の交換会(市場)の休止、催事などのイベ
ントの中止が相次ぎました。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6168
古本&カフェ じゃらん亭 ツイッター
https://twitter.com/igveuuxvqdwzjpt
━━━━━━━━━【シリーズ 古本マニア採集帖】━━━━━━
第20回 伊藤嘉孝さん 古本から新刊を生み出すひと
南陀楼綾繁
私自身もそうであるように、編集者には古本好きであることが結
果として仕事につながっている人がいる。なかでも、会社じたいが
古本マニアの巣窟ではないかと疑われるのが国書刊行会だ。絶版に
なった本や稀覯本を資料として、復刊、アンソロジー、全集などを
刊行している。
今回はその国書刊行会の若手代表(?)として、伊藤嘉孝さんに
話を聞いた。同社で武術、民俗学、考古学などの本を企画し、新し
い路線をつくっている。
「これまでの古本との付き合いが、すべて仕事につながっている気
がします」と語る伊藤さんに古本遍歴を聞いた。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6141
南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)
1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一
文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、
図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年
から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」
の代表。各地で開催される多くのブックイベントにも関わる。
「一箱本送り隊」呼びかけ人として、石巻市で本のコミュニティ
・スペース「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。本と町と人を
つなぐ雑誌『ヒトハコ』(書肆ヒトハコ)編集発行人。著書に
『ナンダロウアヤシゲな日々』(無明舎出版)、『一箱古本市
の歩きかた』(光文社新書)、『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、
『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』
(ちくま文庫)などがある。
ツイッター
https://twitter.com/kawasusu
『蒐める人 情熱と執着のゆくえ』 南陀楼綾繁 著
皓星社刊 価格:1,600円(+税) 好評発売中!
http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/atsumeruhito/
━━━━━【9月10日~10月15日までの全国即売展情報】━━━━━
⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init
※現在、新型コロナウイルスの影響により、各地で予定されている
即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。
お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
--------------------------
--------------------------
書窓展(マド展)【会場販売あります】
期間:2020/09/11~2020/09/12
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
--------------------------
第40回古本浪漫洲 Part 4
期間:2020/09/11~2020/09/13
場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)
新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111
--------------------------
柏モディ古本まつり(千葉県)
期間:2020/09/11~2020/09/26
場所:モディ柏店 3F 千葉県柏市柏1-2-26
--------------------------
好書会【会場販売あります】
期間:2020/09/12~2020/09/13
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
--------------------------
east TOKYO BOOK PARK
期間:2020/09/12~2020/11/08
場所:錦糸町パルコ3階特設会場
墨田区江東橋4丁目27番14号
--------------------------
第22回 紙屋町シャレオ古本まつり(広島県)
期間:2020/09/14~2020/09/20
場所:紙屋町シャレオ中央広場
広島県広島市中区基町地下街100号
--------------------------
第40回古本浪漫洲 Part 5 全品300円均一
期間:2020/09/14~2020/09/16
場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場)
新宿区歌舞伎町1-2-2 TEL03-3354-6111
--------------------------
趣味の古書展【会場販売あります】
期間:2020/09/18~2020/09/19
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
--------------------------
第53回 鬼子母神通りみちくさ市 ※中止となりました
期間:2020/09/20~2020/09/20
場所:雑司が谷 鬼子母神通り
--------------------------
93回シンフォニー古本まつり(岡山県)
期間:2020/09/23~2020/09/28
場所:岡山シンフォニービル1F 自由空間ガレリア
--------------------------
浦和宿古本いち(埼玉県)
期間:2020/09/24~2020/09/27
場所:さくら草通り
JR浦和駅西口下車 徒歩5分 マツモトキヨシ前
--------------------------
和洋会古書展
期間:2020/09/25~2020/09/26
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
--------------------------
五反田遊古会※中止となりました
期間:2020/09/25~2020/09/26
場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4
--------------------------
中央線古書展【会場販売あります】
期間:2020/09/26~2020/09/27
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
--------------------------
新橋古本市※中止となりました
期間:2020/09/28~2020/10/03
場所:新橋駅前 SL広場
--------------------------
西部展【会場販売あります】
期間:2020/10/02~2020/10/04
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
--------------------------
第20回 四天王寺 秋の大古本祭り(大阪府)
期間:2020/10/02~2020/10/07
場所:大阪 四天王寺
大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-11-18
--------------------------
第17回 上野広小路古本まつり
期間:2020/10/05~2020/10/11
場所:永谷お江戸上野広小路 ギャラリー+スペース36
台東区上野1-20-10 お江戸上野広小路亭1階
--------------------------
BOOK & A(ブック&エー)
期間:2020/10/08~2020/10/11
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
--------------------------
新さっぽろ「アツベツ古書の街」(北海道)
期間:2020/10/08~2020/10/10
場所:新さっぽろサンピアザ光の広場
--------------------------
城南古書展
期間:2020/10/09~2020/10/10
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
--------------------------
京都まちなか古本市(京都府)
期間:2020/10/09~2020/10/11
場所:京都古書会館1階
京都市中京区高倉通夷川上る福屋町723
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信
を希望された方にお送りしています。
ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。
【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約600万点掲載
の古書籍データベースです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
見逃したメールマガジンはここからチェック!
【バックナンバーコーナー】
https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33
┌─────────────────────────┐
次回は2020年9月下旬頃発行です。お楽しみに!
└─────────────────────────┘
*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*
全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です
https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner
==============================
日本の古本屋メールマガジンその306 2020.9.10
【発行】
東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」
東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館
URL http://www.kosho.or.jp/
【発行者】
広報部:志賀浩二
編集長:藤原栄志郎
==============================
第20回 伊藤嘉孝さん 古本から新刊を生み出すひと
第20回 伊藤嘉孝さん 古本から新刊を生み出すひと南陀楼綾繁 |
| 私自身もそうであるように、編集者には古本好きであることが結果として仕事につながっている人がいる。なかでも、会社じたいが古本マニアの巣窟ではないかと疑われるのが国書刊行会だ。絶版になった本や稀覯本を資料として、復刊、アンソロジー、全集などを刊行している。 今回はその国書刊行会の若手代表(?)として、伊藤嘉孝さんに話を聞いた。同社で武術、民俗学、考古学などの本を企画し、新しい路線をつくっている。 「これまでの古本との付き合いが、すべて仕事につながっている気がします」と語る伊藤さんに古本遍歴を聞いた。 伊藤さんは1978年、岩手県盛岡市生まれ。父は銀行員。両親との3人家族。 伊藤さんは1999年、20歳で大検により早稲田大学人間科学部に入学。 伊藤さんは考古学関係の本も編集している。 古本を探すのにはネットや古書目録は使わず、即売会にもあまり足を運ばない。それよりは、店舗を訪れたときに本と出会うのがいいと云う。 「出したい本はまだたくさんあります」と伊藤さんは云う。時を経て一度忘れ去られた本を古本屋で見つけ、新しい本として世に送り出す。さまざまな曲折を経て、伊藤さんは天職にたどり着いたのだ。 南陀楼綾繁 ツイッター
|
|
Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |
古書店開業記3(コロナ禍の中で)
古書店開業記3(コロナ禍の中で)古本&カフェ じゃらん亭 内山武明 |
| 実家の19号台風の後片付けが済んでから、平常の営業に戻し、年が明けて、2月頃からレコード寄席や浮世絵に関するイベントなどを行いました。徐々にお客さんや買取りも増えてきました。季節も暖かくなってきて、これからという時に、コロナの流行が始まり、来客数の低下、古書組合の交換会(市場)の休止、催事などのイベントの中止が相次ぎました。家にいる期間が長くなったので、片づけを行う人が増え、買取りが増えているという話もありましたが、当店の場合、買取も減りました。
第1波が収まった6月頃には、お客さんが戻ってきましたが、その後は、また低下し、いつの間にか開店1周年を迎えて、今に至っています。 ネット販売の古本屋と店舗での販売をする古本屋の大きな違いは、目に見えるお客さんがいるかどうかというところもありますが、在庫のとらえ方の違いも大きいと思います。極端なことを言うと、インターネットの販売は、在庫は全て販売してしまって無くなっても構わない(また仕入れれば良い)ということにもなります。これに対して店舗では、そういうわけにはいきません。いかに魅力的な在庫を保持していくかということになります。 市場でも、目的のものが必ずしも手に入るわけではありません。たいていは何十冊もの束になっており、欲しいものばかりではありません。特殊なものを集めようと思えば、目当てのものが少しでも入っている束に入札し、必要なものを残し、残りは、また市場に出すということを繰り返し、気長に集めていくしかありません。 一つは前回書いたことですが、得意分野を持ち、個性的な品ぞろえを目指すこと、2つめは、古いものの面白さ、良さを積極的に発掘、発信して、アピールするということが必要ではないかと思います。ネットの情報は、最近の事は非常に詳しい反面、少し昔のことになると極端に情報が少ないということがあります。懐かしいと思う層だけではなく、若い層にも古いものの面白さを積極的に発信していく必要があると思います。 古本&カフェ じゃらん亭 ツイッター |
|
Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |
2020年8月25日 第305号
■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■
。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。
。.☆.:* その305・8月25日号 *:.☆. 。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信
を希望された方にお送りしています。
ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。
【日本の古本屋】は全国930書店参加、データ約600万点掲載
の古書籍データベースです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━【お知らせ】━━━━━━━━━━━━
刻々と変わる古書店の新入荷情報は、日本の古本屋トップページに
ある「新着書籍」にて常に更新! ぜひご覧ください。
☆INDEX☆
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
1.本の本『本のリストの本』に参加して――
アイデアが広がる書誌エッセー 書物蔵
2.『近代出版史探索3』 小田光雄
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
━━━━━━━━━━━【自著を語る番外編】━━━━━━━━━
本の本『本のリストの本』に参加して――
アイデアが広がる書誌エッセー
書物蔵
めずらしく市販のエッセー集に参加しました。8月27日に発売と
なるので告知を兼ねてここに経緯を書いておきます。
■本の全体
去年、ライターの南陀楼綾繁さんに会った時に、〈本の本〉に参
加してよ、と言われて、いいですよと言ったら『本のリストの本』
とのこと。
「本の本でもややこしいのに、本のリストの本とは?」
当初、「要するに、書誌についいての解題書誌なのね」と単純に
考えていたんですが――というのも〈書誌の書誌〉というジャンル
が図書館学にあるので――出版企画書には「アカデミックな内容で
はなく、普通の本好きが読んで面白いこと」とありました。一緒に
送られてきた画家の林哲夫さんが書いた原稿を読んだら「あゝ、な
るほどぉ……」。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6000
『本のリストの本』
南陀楼 綾繁 著 / 書物蔵 著 / 鈴木 潤 著 / 林 哲夫 著 / 正木 香子 著
創元社 定価:2,300円+税 8月27日発売予定
https://www.sogensha.co.jp/productlist/detail?id=4128
━━━━━━━━━━━【自著を語る(246)】━━━━━━━━━
『近代出版史探索3』
小田光雄
『近代出版史探索』連作は5月の第二巻に続いて、7月に第三巻
を刊行することができた。いずれも昨年の第一巻と同様に、200編
を収録した700ページ前後の大部で、しかも第四、五巻も9月、11月
に続刊となる。
著者として、少部数高定価であることは読者に申し訳ない思いが
つきまとうけれど、出版業界の危機的状況下とコロナ禍の中での上
梓であるだけに、感慨無量といった心境に至っている。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=6103
『近代出版史探索3』 小田光雄 著
論創社 定価:6,000円+税 好評発売中!
http://ronso.co.jp/
━━━━━━━━━━━━━【次回予告】━━━━━━━━━━━
『中年の本棚』 荻原魚雷 著
紀伊國屋書店出版部 定価 1,700円+税 好評発売中!
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784314011754
『東京、コロナ禍。』
柏書房 定価:1,800円+税 好評発売中!
http://www.kashiwashobo.co.jp/book/b517597.html
━━━━━━━━━【日本の古本屋即売展情報】━━━━━━━━
8月~9月の即売展情報
※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている
即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。
お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
見逃したメールマガジンはここからチェック!
【バックナンバーコーナー】
https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33
┌─────────────────────────┐
次回は2020年9月中旬頃発行です。お楽しみに!
└─────────────────────────┘
*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の全国の古書店に ☆*
全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です
https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner
==============================
日本の古本屋メールマガジンその305 2020.8.25
【発行】
東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」
東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館
URL http://www.kosho.or.jp/
【発行者】
広報部:二見彰
編集長:藤原栄志郎
==============================
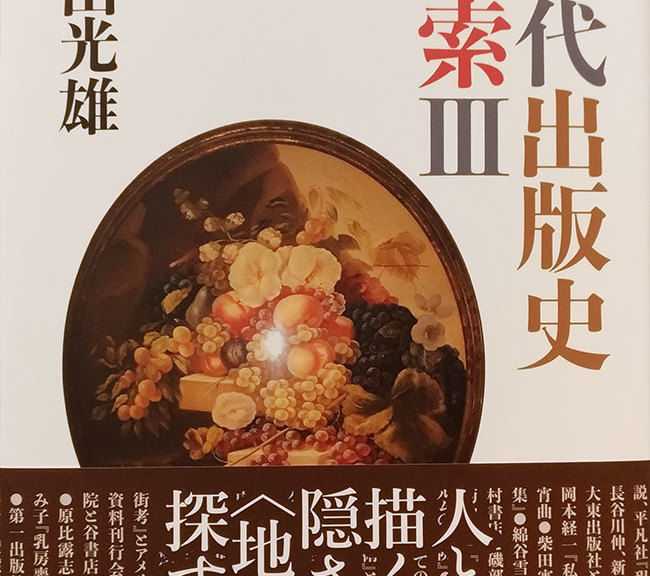
『近代出版史探索Ⅲ』
『近代出版史探索Ⅲ』小田光雄 |
| 『近代出版史探索』連作は5月の第二巻に続いて、7月に第三巻を刊行することができた。いずれも昨年の第一巻と同様に、200編を収録した700ページ前後の大部で、しかも第四、五巻も9月、11月に続刊となる。 著者として、少部数高定価であることは読者に申し訳ない思いがつきまとうけれど、出版業界の危機的状況下とコロナ禍の中での上梓であるだけに、感慨無量といった心境に至っている。 そのような次第なので、今回は『近代出版史探索』の執筆動機、拙ブログ連載事情、出版に至る経緯といったことなどに、具体的にふれてみたい。 私は2008年から出版業界の現在を定点観測、分析する『出版状況クロニクル』のブログ連載を始めている。それに関連して、出版業界の現在もさることながら、そこに至った出版業界の歴史を遡行し、明治から昭和戦前の出版史をあらためて検証すべきだというオブセッションに駆られていたのである。それは現在分析にしても、何よりも歴史と過去を対照化させることによって、より明らかにされるのではないかと思われたからだ。 しかしどのようにして書き、それを伝えるべきなのか。それはこれまで『古本屋散策』や『古本探究』三部作を書いてきたように、一冊、もしくは数冊の古本を対象とした短編の連作形式を採用し、自らのブログに連載していくべきだと思われた。だが長期に及ぶことは必至だし、これもまた必然的に実務を担う編集者の存在が不可欠だった。 そこでそれを妻の啓子に依頼するしかなかった。彼女は『出版状況クロニクル』の編集者であり、さらなる負担をかけるのは心苦しかったが、息子たちの助力を含めて、一家総出の仕事として、2009年に始められたのである。 そのようにして連載は進められ、10年がたち、1000回に近づき、7000枚に近くに及んだ。当り前のことではあるけれど、もちろん単行本化は思いもよらず、とりあえずは千一夜を目安としようと考えていたのである。 森下さんとは、今はなき人文図書取次の鈴木書店で知り合い、様々に助けられてきた。それに加えて、いずれ論創社から全集を出してあげようといってくれたのである。図らずも、『近代出版史探索』の刊行で、それが実現してしまったことになる。それに同伴してくれたのは、若い編集者の小田嶋源さんで、このような大部の5冊をほぼ1年で刊行できたのは、彼の体力と編集者としての才によっている。膨大な索引にしても、すべては彼の作成である。 『近代出版史探索3』 小田光雄 著 |
|
Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |
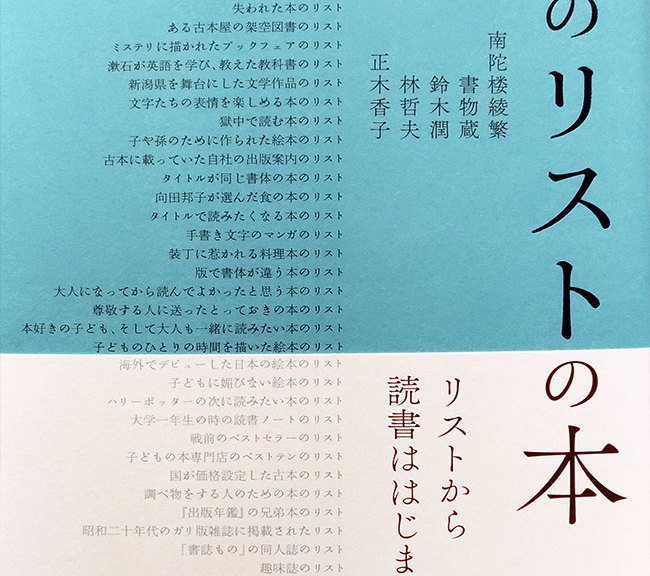
本の本『本のリストの本』に参加して――アイデアが広がる書誌エッセー
本の本『本のリストの本』に参加して――アイデアが広がる書誌エッセー書物蔵 |
| めずらしく市販のエッセー集に参加しました。8月27日に発売となるので告知を兼ねてここに経緯を書いておきます。
■本の全体 ■他の著者さんたち ■載せられなかったアイテム ■アイデア1――本文の逆接 ■アイデア2――付き物の逆接 ざっと全体を見てみると自分の担当箇所が一番、黒っぽく(漢字が多い)、やっぱり濃くなってしまったと反省しきりですが、全体として、みなさんのご協力もあって、文献リストや、書物満載の文学にまつわるいろんな話という、日本では珍しい本がおもしろく読める形になったように思います。 本好きには格好の読み物ではないかとお勧めする次第(´・ω・)ノ
|
|
Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |