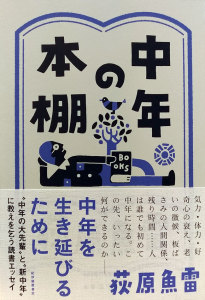一九八九年、大学在学中の十九歳のときからフリーライターの仕事をはじめ、三十余年になる。これまでは主に古本のエッセイを書いてきたが、最近は街道や宿場町の本の蒐集に追われている。
「中年の本棚」は二〇一三年の春、四十三歳から『scripta』で連載をはじめた。
今から八年前、東京・高円寺のコクテイル書房のトークショーに出席したとき、「三十代の半ばくらいから中年本を集めているんですよ」といったところ、この日、店に来ていた紀伊國屋書店のOさんに「中年本の連載をしませんか」と声をかけられた。
中年本はミドルエイジクライシス――“中年の危機”について書かれた本だけではなく、主人公が中年の小説や漫画、中年の心境を綴ったエッセイや対談、中年フリーランス、中年シングル、中年の貧困、中年の転職など、様々なテーマを取り上げた。
第一回目は野村克也と扇谷正造と吉川英治と源氏鶏太の本について書いた。題して「『四十初惑』考」。彼らの書物の中で「四十不惑」ではなく「四十初惑」という言葉をつかっている。中年になっても、迷い、戸惑うことがわかり、安心した。
田辺聖子は「とりあえずお昼」「とりあえず寝る」と気を取り直す。水木しげるは「中年をすぎたら、愉快になまけるクセをつけるべきです」と忠告する。津野海太郎は「日常の習慣(家事をこなしたり、いくばくかのさびしさを我慢したりする技術)」の再編成が老いの備えになると考えた。
目先の問題が片づけても片づけても次の問題が浮上する。連載中、郷里の三重にいる父の死や母の入院による遠距離介護を経験したり、腰痛になったり、五十肩になったりもした。
一難去ってまた一難。中年になって以来、この言葉を何度噛みしめたか。
これまで自分の周囲でもそうした話を見聞きしてきたが、心のどこかで他人事のようにおもっていた。書物で読んでいるだけではわからないことがたくさんある。老眼って、こんなに急に進むのか。
何かしらの経験を積んだ後、昔読んだ本を読み返すと、初読のときにピンとこなかった大切に気づくこともある。中村光夫や尾崎一雄の再読はほんとうに得るものが多かった。
そのあたりも中年期の読書の面白さだろう。
中年になってからも、はじめて知ることもたくさんある。気力や体力の衰えもそうだ。徹夜がつらい。寝ても寝ても疲れがとれない。風邪やケガが治りにくい。中年初期にはそうした心身の変調が不安につながった。この先、ずっと下り坂が続くのではないかと……。
若くもなく、ベテランと胸を張れるほどの実績もない。仕事をしていても、上司と部下の挟まれ、宙ぶらりんの立場で不安定な状態に陥りやすいのも中年のひとつの特徴である。こればっかりは誰もが通る道と開き直るしかない。
もっとも加齢による変化はつらいことばかりではない。油っこいものを食べると胃がもたれるようになったかわりに、豆腐や酢のものがおいしく感じられるようになった。読む本や聴く音楽の傾向もすこしずつ変わってくる。体力が落ちた分、余計なエネルギーを注ぐ余裕がなくなり、この先、自分のやりたいことが明確になったような気もする。
こうした自分の心身の小さな変化を愉しむくらいの気持でいたほうがいい。
本書は中年期の転ばぬ先の杖たる指南書を目指した。
疲れをためず、休み休み、五、六割の力で日々を乗りきる。これも中年の知恵だ。というか、無理したくても、無理ができなくなることが中年になるということかもしれませんが。
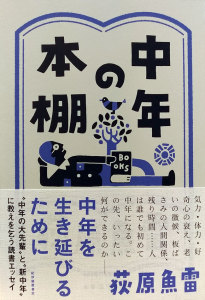
『中年の本棚』 荻原魚雷 著
紀伊國屋書店出版部 定価 1,700円+税 好評発売中!
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784314011754
文壇高円寺
http://gyorai.blogspot.com/
|