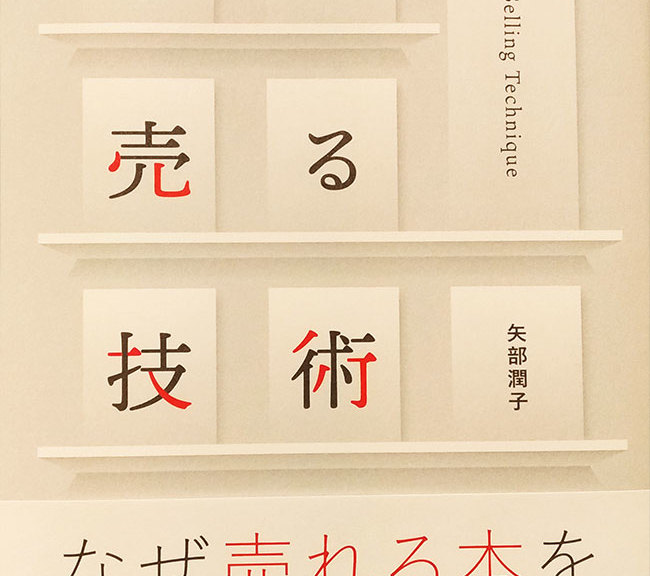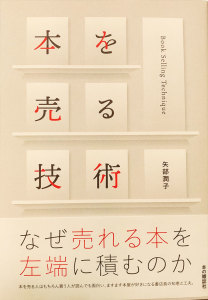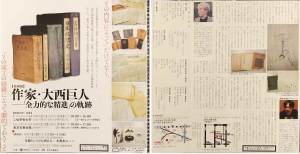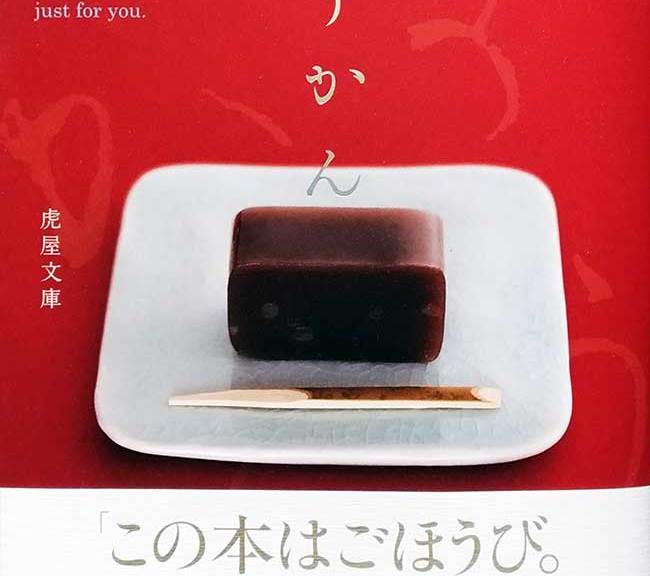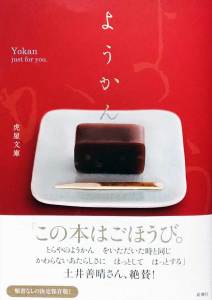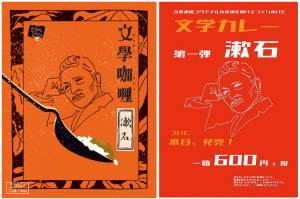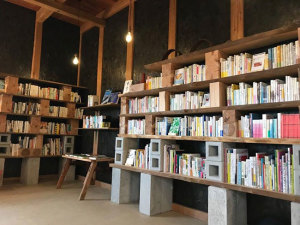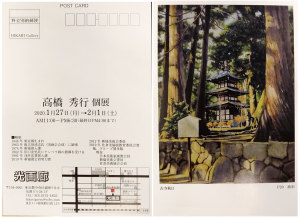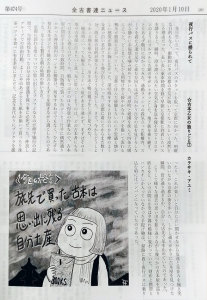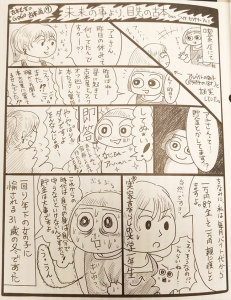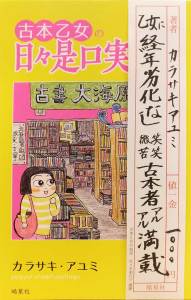■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■
。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。
古書市&古本まつり 第85号
。.☆.:* 通巻292・2月10日号 *:.☆. 。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。
初旬に(10日前後)全国で開催されている古本展示即売会など、
イベント情報をお送りします。お近くで開催される際は、ぜひ
お出掛け下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━
北陸古本案内 その2
オヨヨ書林 山崎 有邦
前回は石川県の古本屋について書かせていただきましたが、今回は
お隣、富山県の古本屋の紹介です。
東京から金沢に引っ越した数年の後、富山市・岩瀬の古道具屋
・スヰヘイ社さんから、ミニ古本市へのお誘いを受けました(そ
の古本市の、男の子が本を読んでいるイラストは、現在、細野晴
臣の本の表紙や、雑誌『POPEYE』のイラストなどでも活躍されて
いる富山出身の漫画家・堀道広画伯でした)。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5520
オヨヨ書林
https://oyoyoshorin.jp/
━━━━━━━━━【「文学カレー漱石」】━━━━━━━━━
「文学カレー漱石」
コクテイル書房 狩野 俊
当店は高円寺にある、古本屋と居酒屋がいっしょになった店です。
今では珍しくないブックカフェの先駆けとして20年以上に渡り、こ
のような業態の店を営んでいます。文学にちなんだお酒やつまみを
楽しみながら、壁にある本を読むことも買うこともできます。当店
では1年前から夏目漱石の名を冠した、文学カレー「漱石」というも
のをお出ししています。そのカレーのことを書かせていただきます。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5513
コクテイル書房
http://koenji-cocktail.info/
ツイッター
https://twitter.com/cocktail_books
━━━━━━━━━【シリーズ 古本マニア採集帖】━━━━━━
今月の古本マニア採集帖は休載となります。
━━━━━【2月10日~3月15日までの全国即売展情報】━━━━━
⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init
--------------------------
第三回ジュンク堂新春古書展(沖縄県)
期間:2020/01/18~2020/02/24
場所:那覇ジュンク堂 地下1Fイベント広場前
那覇市牧志1-19-29 D-NAHA ゆいレール 美栄橋駅 徒歩3分
--------------------------
第10回 戸田書店 古本・古書フェア(群馬県)
期間:2020/01/27~2020/03/15
場所:戸田書店 高崎店 高崎市下小鳥町438-1
--------------------------
イービーンズ古本まつり(レコード・CD市併催/宮城県)
期間:2020/01/30~2020/03/14
場所:宮城県仙台市青葉区中央4-1-1 9階 杜のイベントホール
--------------------------
三省堂書店池袋本店古本まつり
期間:2020/02/04~2020/02/11
場所:西武池袋本店別館2階=特設会場(西武ギャラリー)
--------------------------
フィールズ南柏 古本市(千葉県)
期間:2020/02/14~2020/02/28
場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場
柏市南柏中央6-7
--------------------------
第6回 古書会館de古本まつり(京都府)
期間:2020/02/14~2020/02/16
場所:京都古書会館 3階 京都市中京区高倉通夷川上る
--------------------------
港北古書フェア(神奈川県)
期間:2020/02/14~2020/02/25
場所:有隣堂センター南駅店店頭ワゴンでの販売
--------------------------
倉庫会(愛知県)
期間:2020/02/14~2020/02/16
場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12
--------------------------
さよなら東急東横店 渋谷大古本市
期間:2020/02/20~2020/02/25
場所:渋谷駅 東急東横店西館8階 催物場
--------------------------
たにまち月一古書即売会(大阪府)
期間:2020/02/21~2020/02/23
場所:大阪古書会館 大阪府大阪市中央区粉川町4-1
--------------------------
ぐろりや会
期間:2020/02/21~2020/02/22
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
URL:http://www.gloriakai.jp/
--------------------------
好書会
期間:2020/02/22~2020/02/23
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
--------------------------
浦和宿古本いち(埼玉県)
期間:2020/02/27~2020/03/01
場所:JR浦和駅西口下車 さくら草通り徒歩5分 マツモトキヨシ前
URL:https://twitter.com/urawajuku
--------------------------
第22回フジサワ湘南古書まつり(神奈川県)
期間:2020/02/27~2020/03/11
場所:有隣堂藤沢店4階ミニ催事場
藤沢市南藤沢2丁目1-1
--------------------------
城南古書展
期間:2020/02/28~2020/02/29
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
--------------------------
西部展
期間:2020/02/28~2020/03/01
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
--------------------------
第14回 上野広小路亭古本まつり
期間:2020/03/02~2020/03/08
場所:永谷お江戸上野広小路 ギャラリー+スペース36
台東区上野1-20-10 お江戸上野広小路亭1階
--------------------------
第93回 彩の国 所沢古本まつり(埼玉県)
期間:2020/03/04~2020/03/10
場所:くすのきホール
西武線所沢駅東口前 西武第二ビル8階 総合大会場
URL:https://tokorozawahuruhon.com/
--------------------------
東京愛書会
期間:2020/03/06~2020/03/07
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
URL:http://aisyokai.blog.fc2.com/
--------------------------
オルデーズクラブ
期間:2020/03/06~2020/03/08
場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12
--------------------------
3月反町古書会館展(神奈川県)
期間:2020/03/07~2020/03/08
場所:神奈川古書会館1階特設会場
横浜市神奈川区反町2-16-10
--------------------------
古書愛好会
期間:2020/03/07~2020/03/08
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
--------------------------
BOOK & A(ブック&エー)
期間:2020/03/12~2020/03/15
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
--------------------------
紙魚之會
期間:2020/03/13~2020/03/14
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
--------------------------
第51回 鬼子母神通りみちくさ市
期間:2020/03/15
場所:雑司が谷 鬼子母神通り
URL:https://kmstreet.exblog.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次回メールマガジンは2月下旬に発行です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信
を希望された方にお送りしています。
ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。
【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約600万点掲載
の古書籍データベースです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
見逃したメールマガジンはここからチェック!
【バックナンバーコーナー】
https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33
┌─────────────────────────┐
次回は2020年2月下旬頃発行です。お楽しみに!
└─────────────────────────┘
*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*
全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です
https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner
==============================
日本の古本屋メールマガジンその292 2020.2.10
【発行】
東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」
東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館
URL http://www.kosho.or.jp/
【発行者】
広報部:二見彰
編集長:藤原栄志郎
==============================