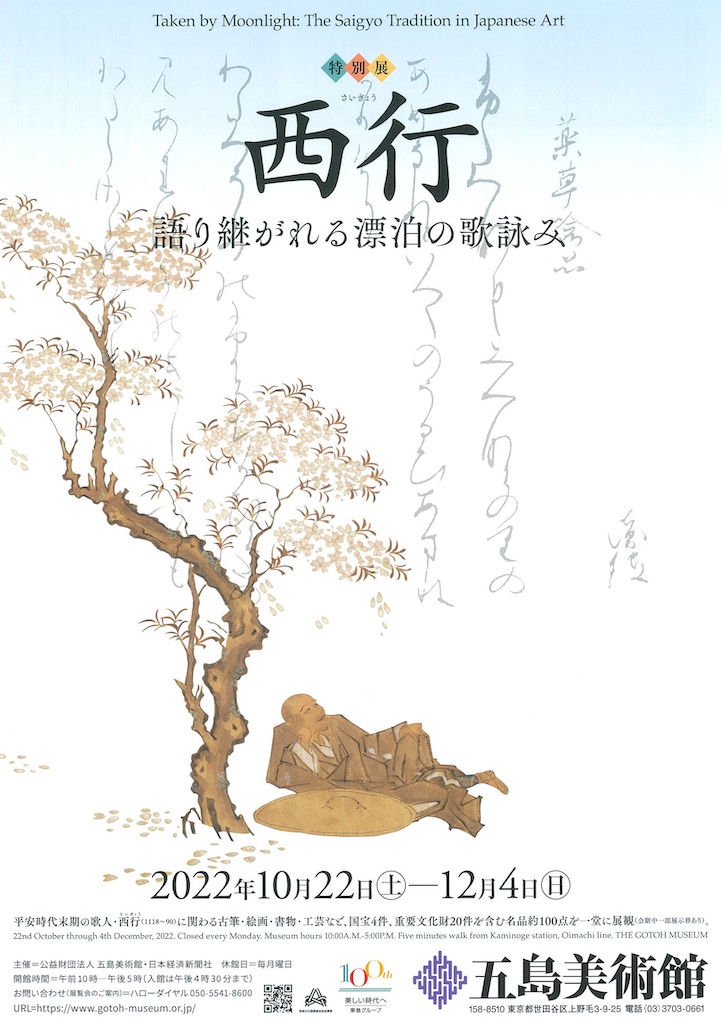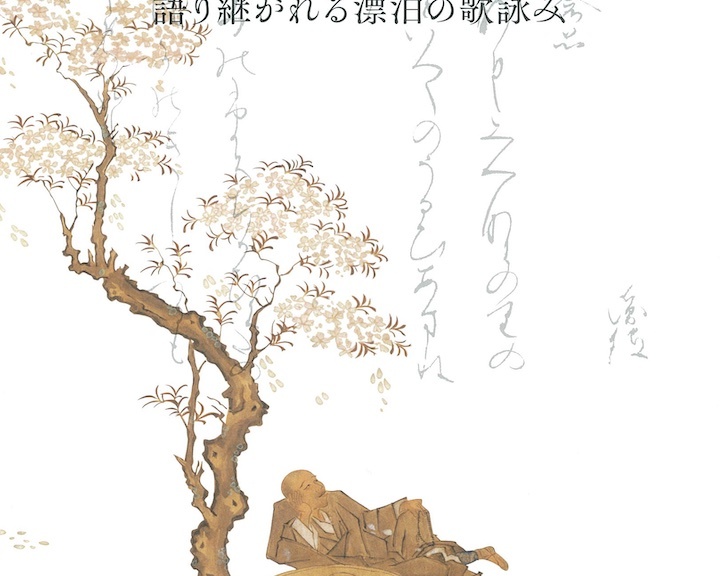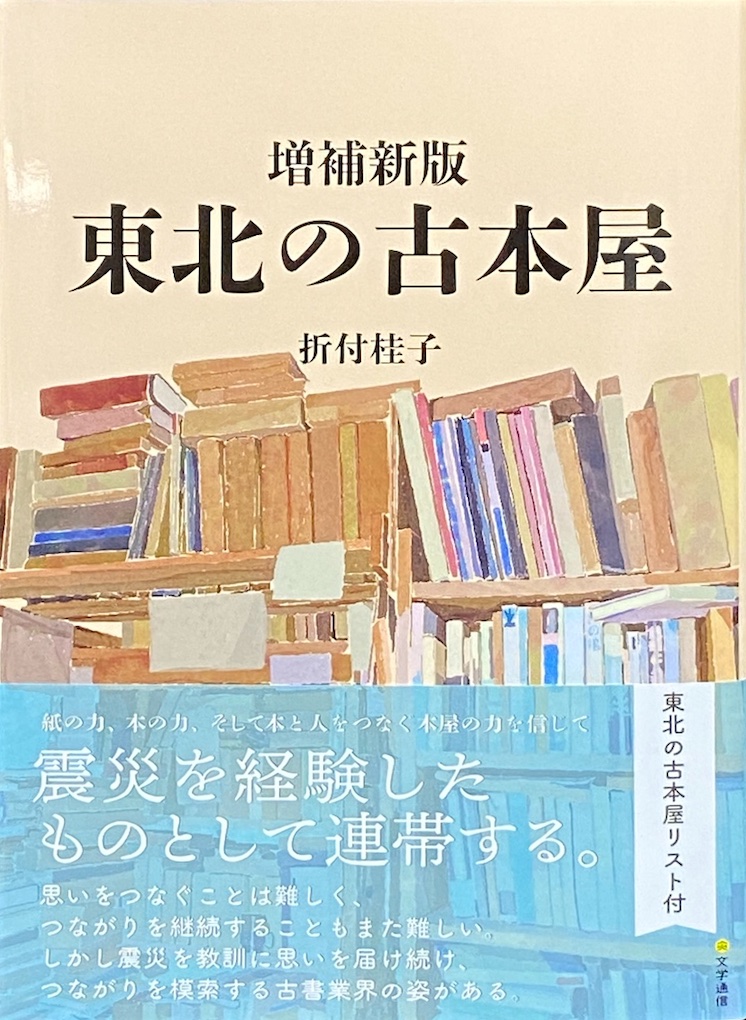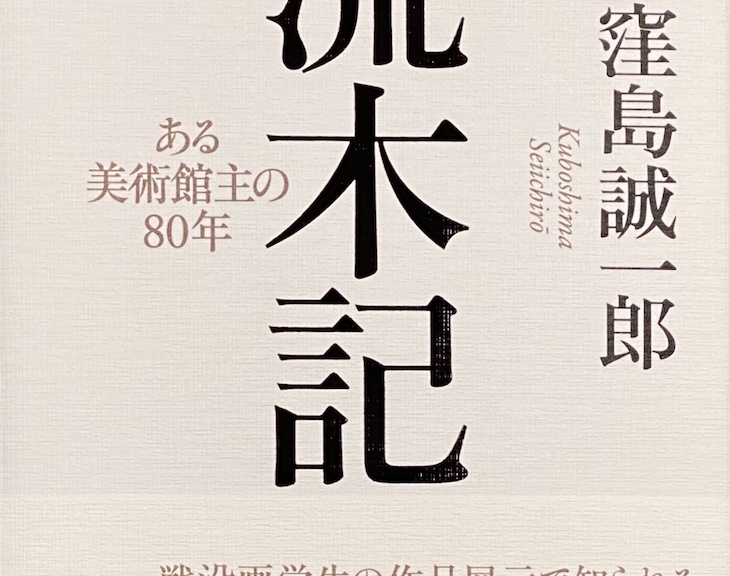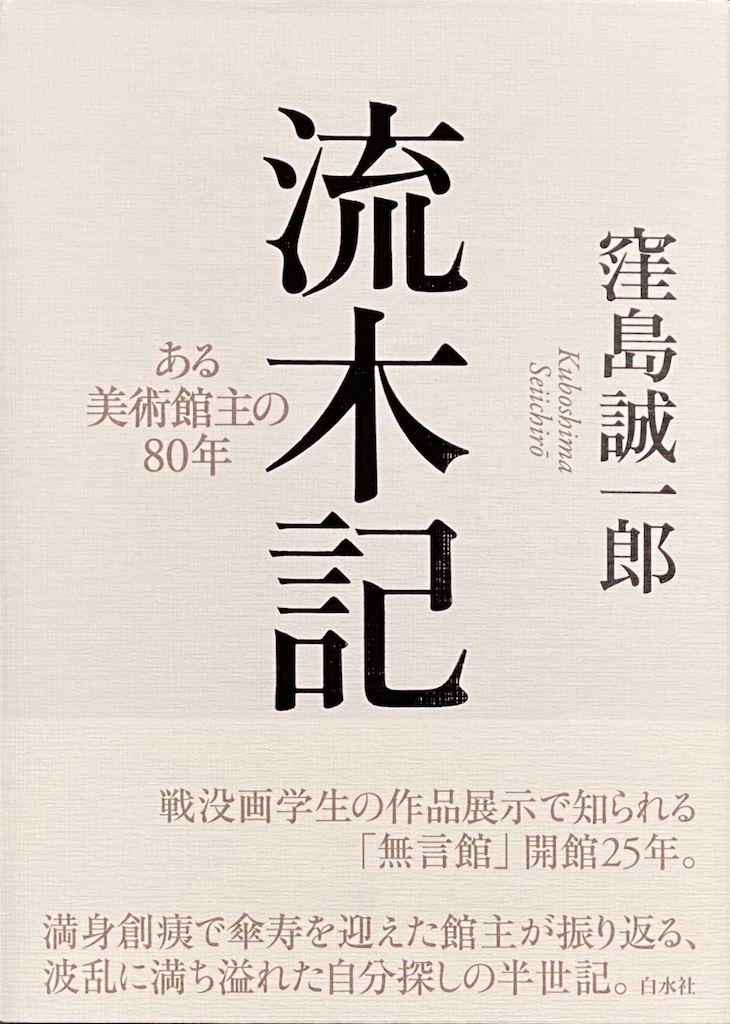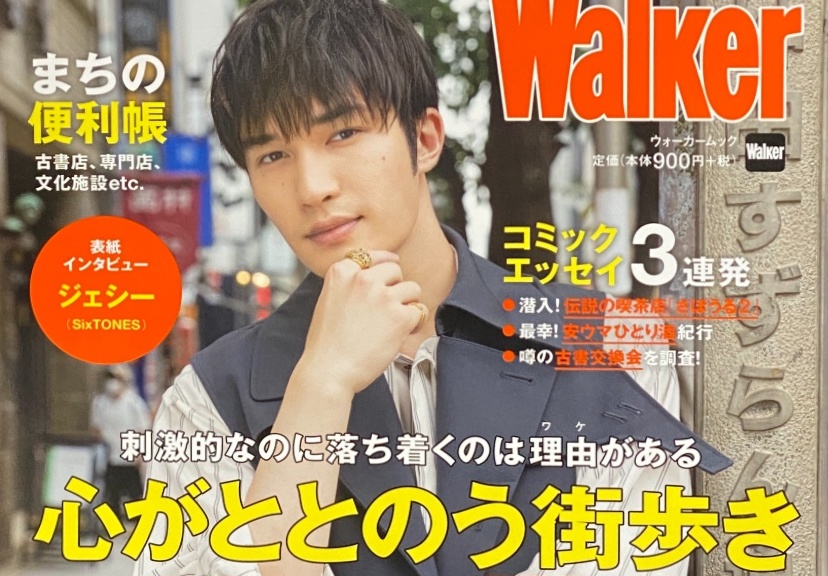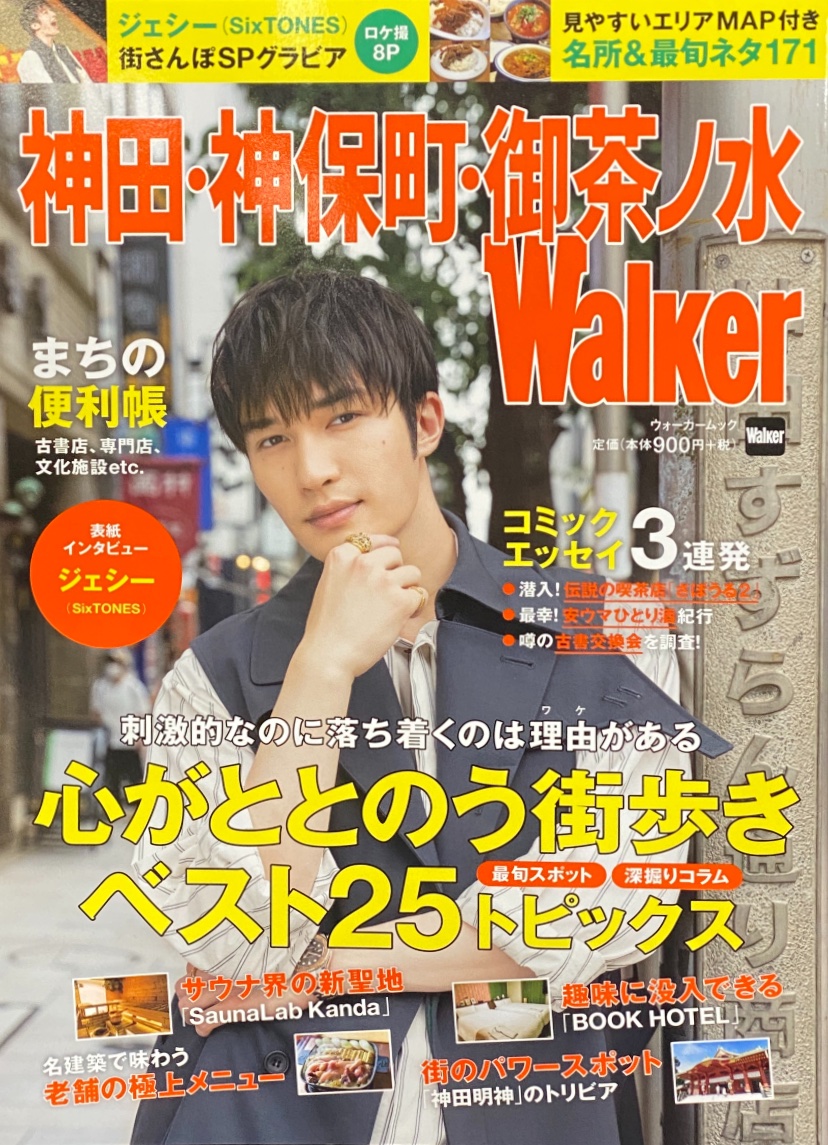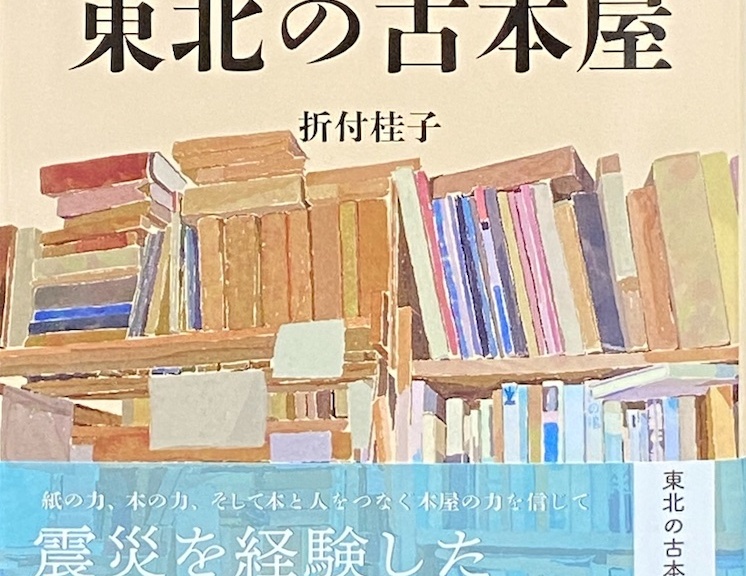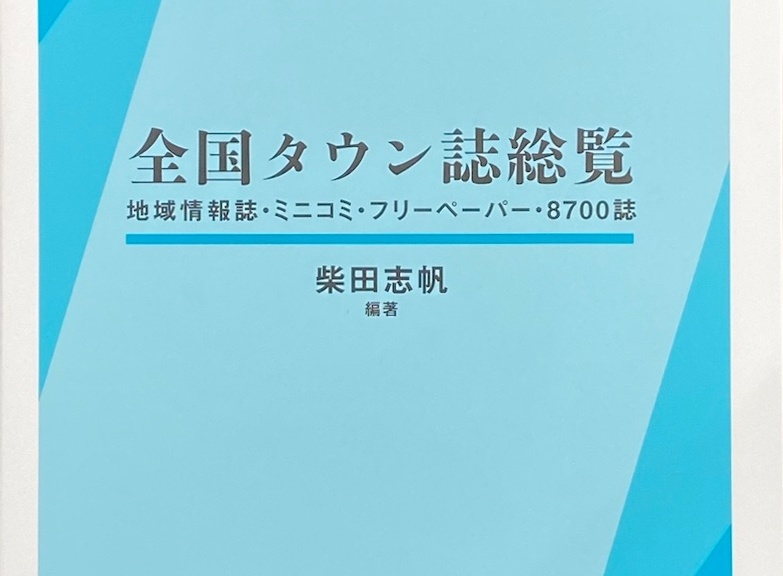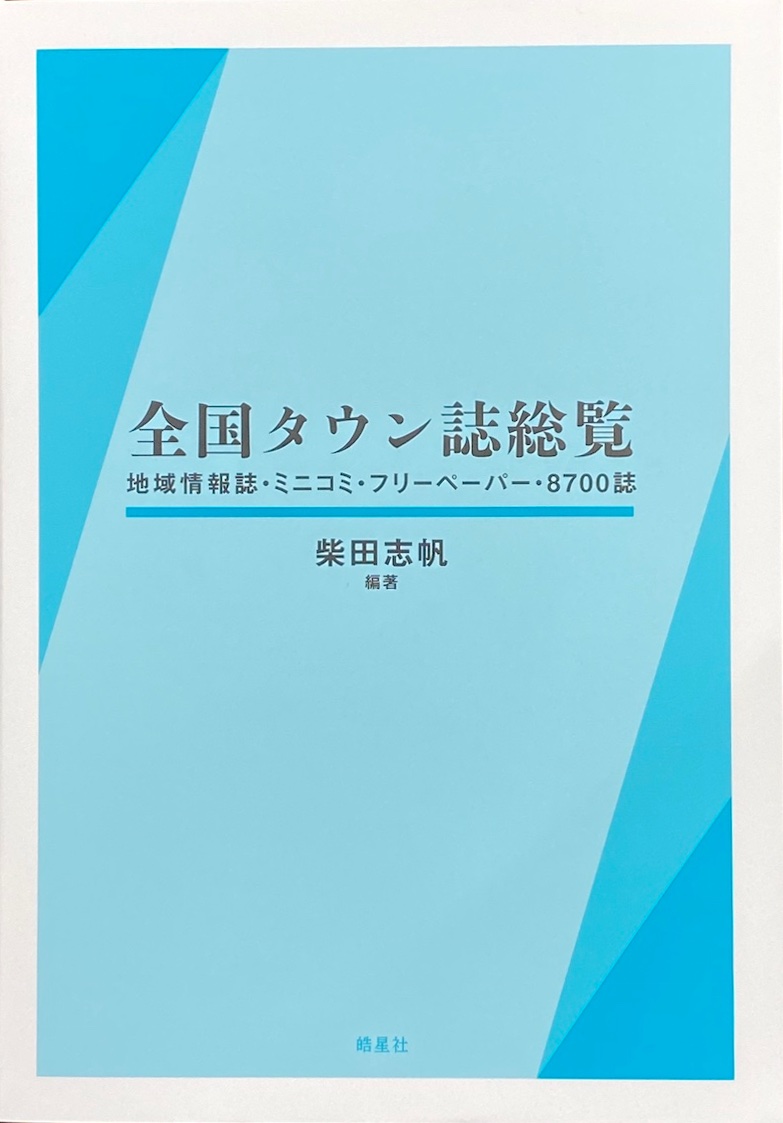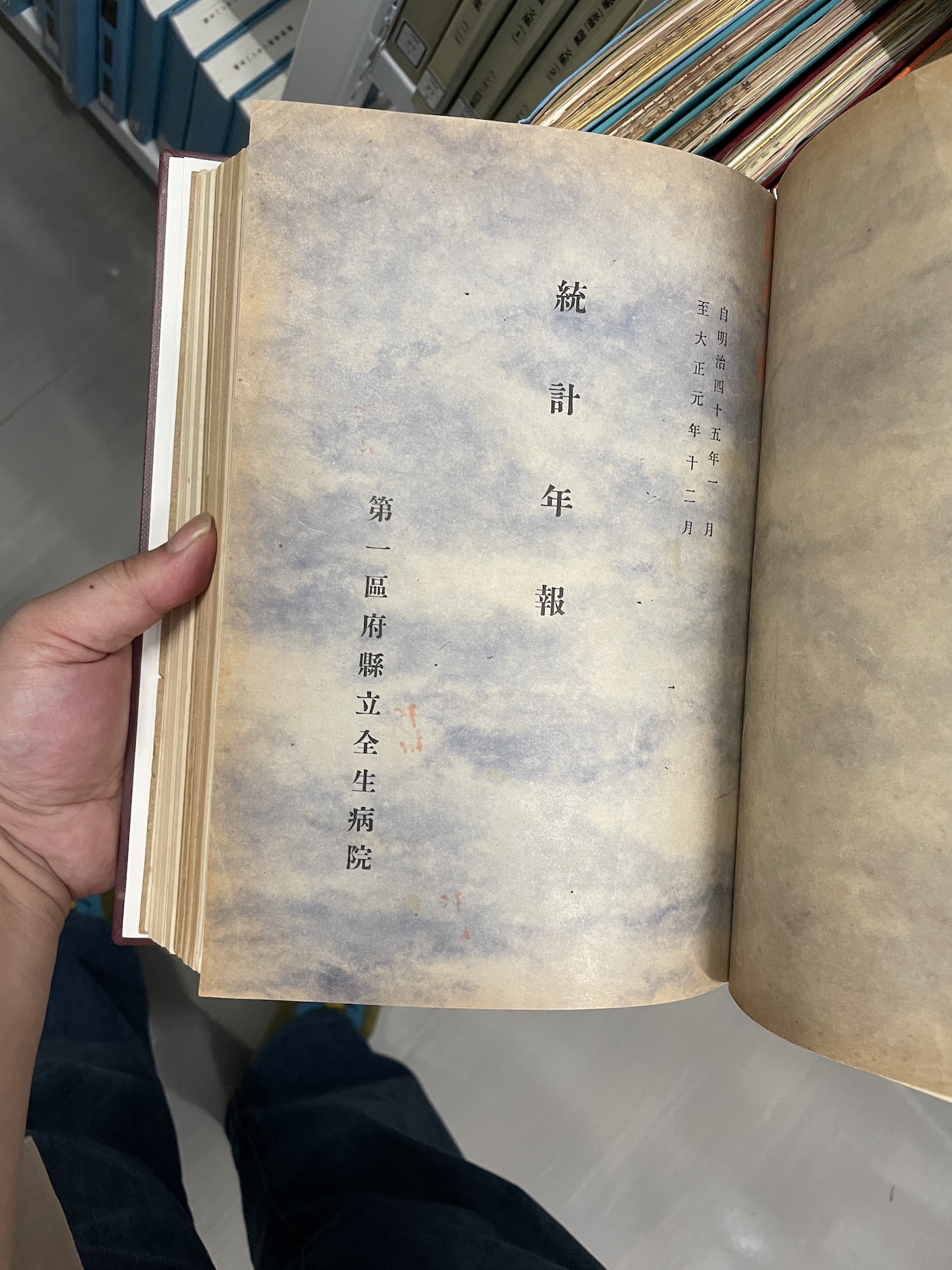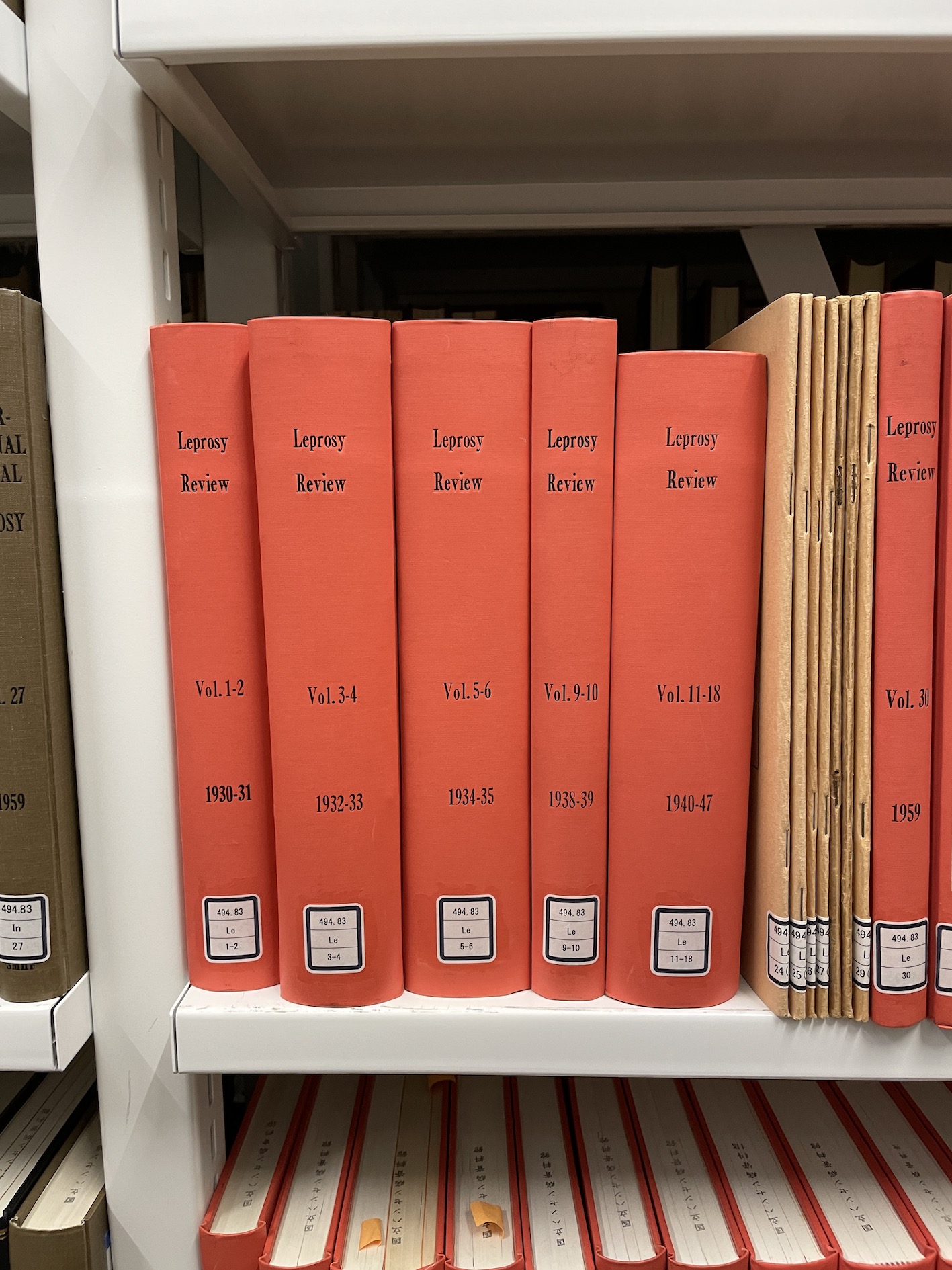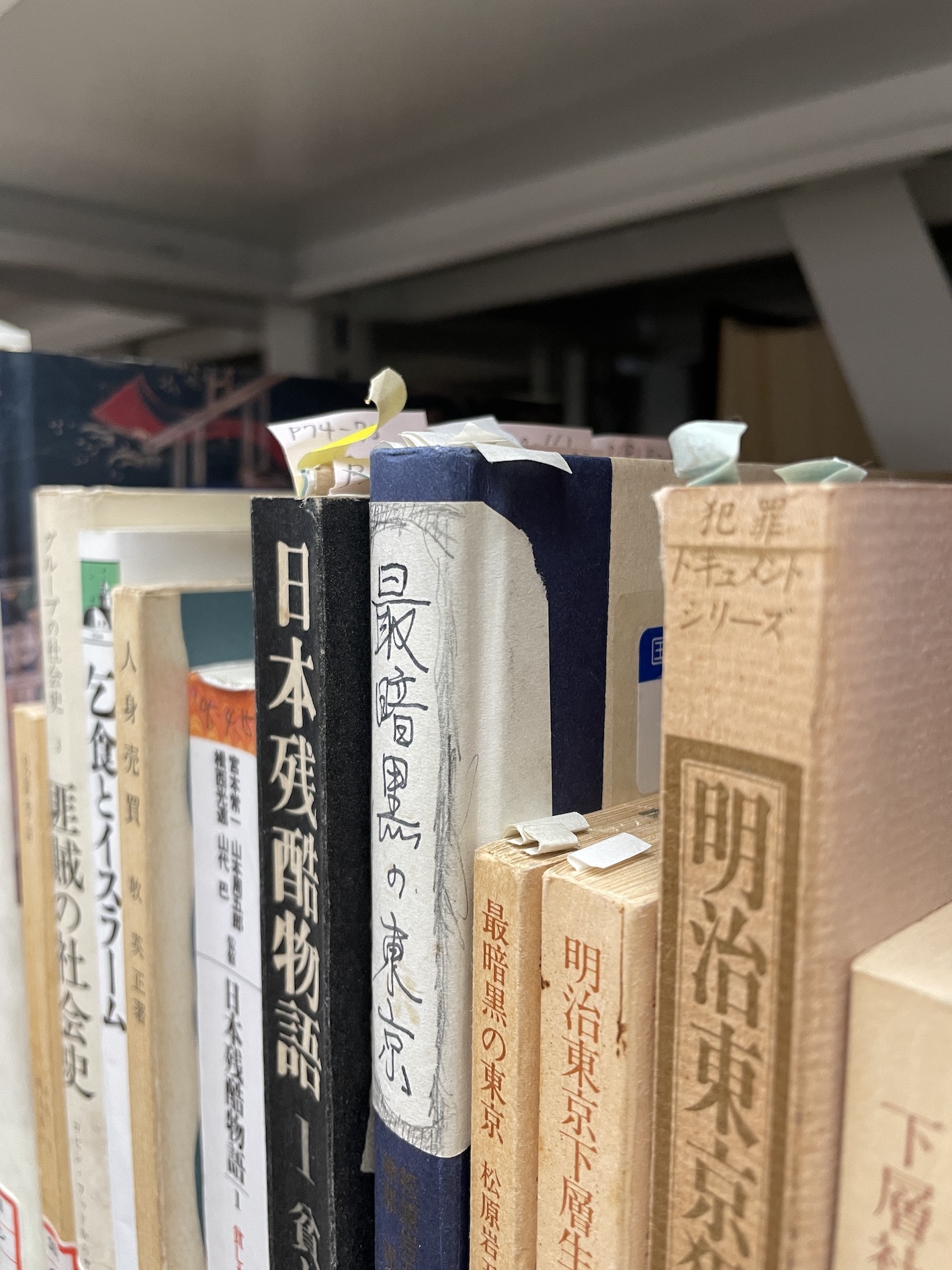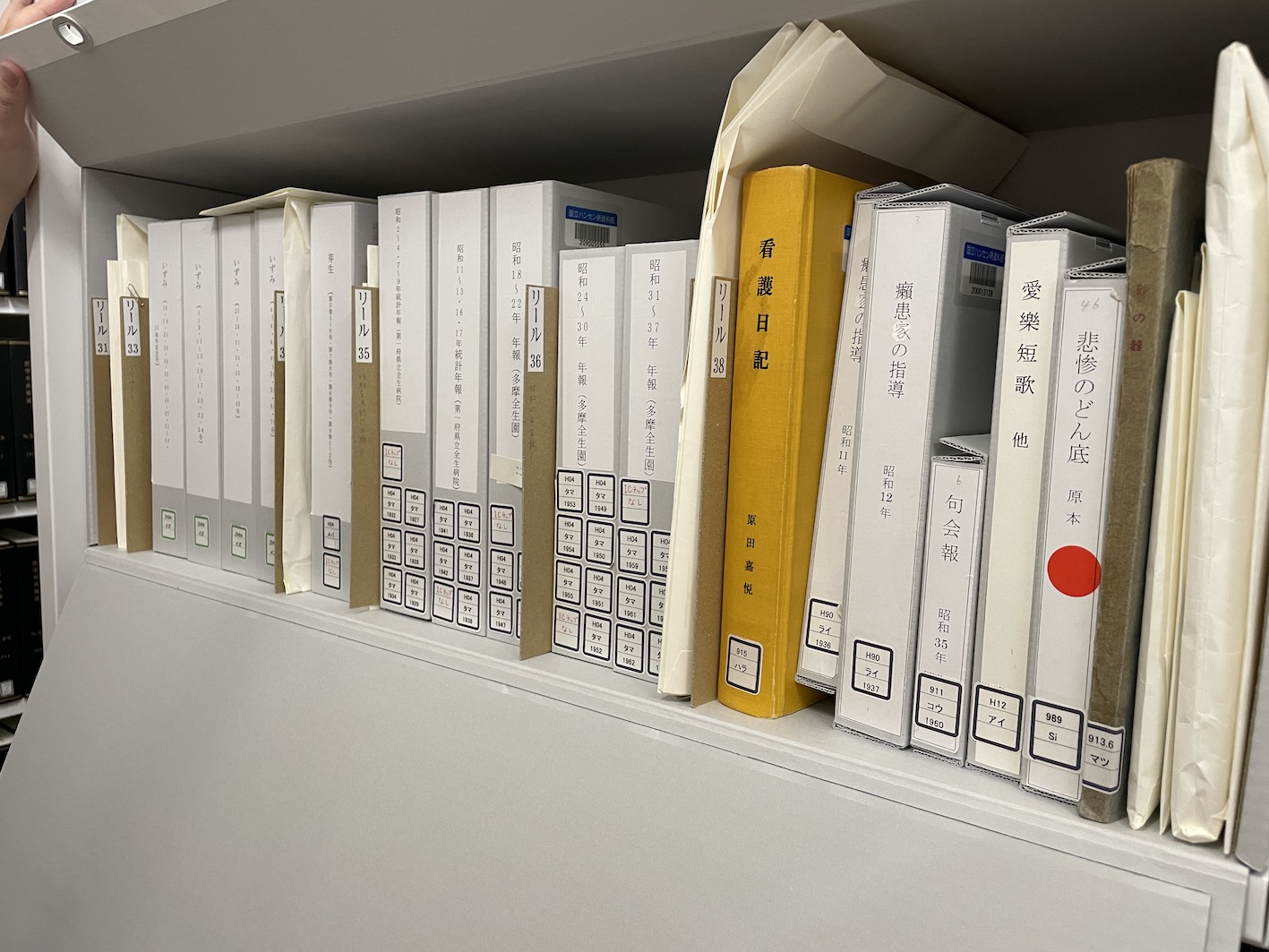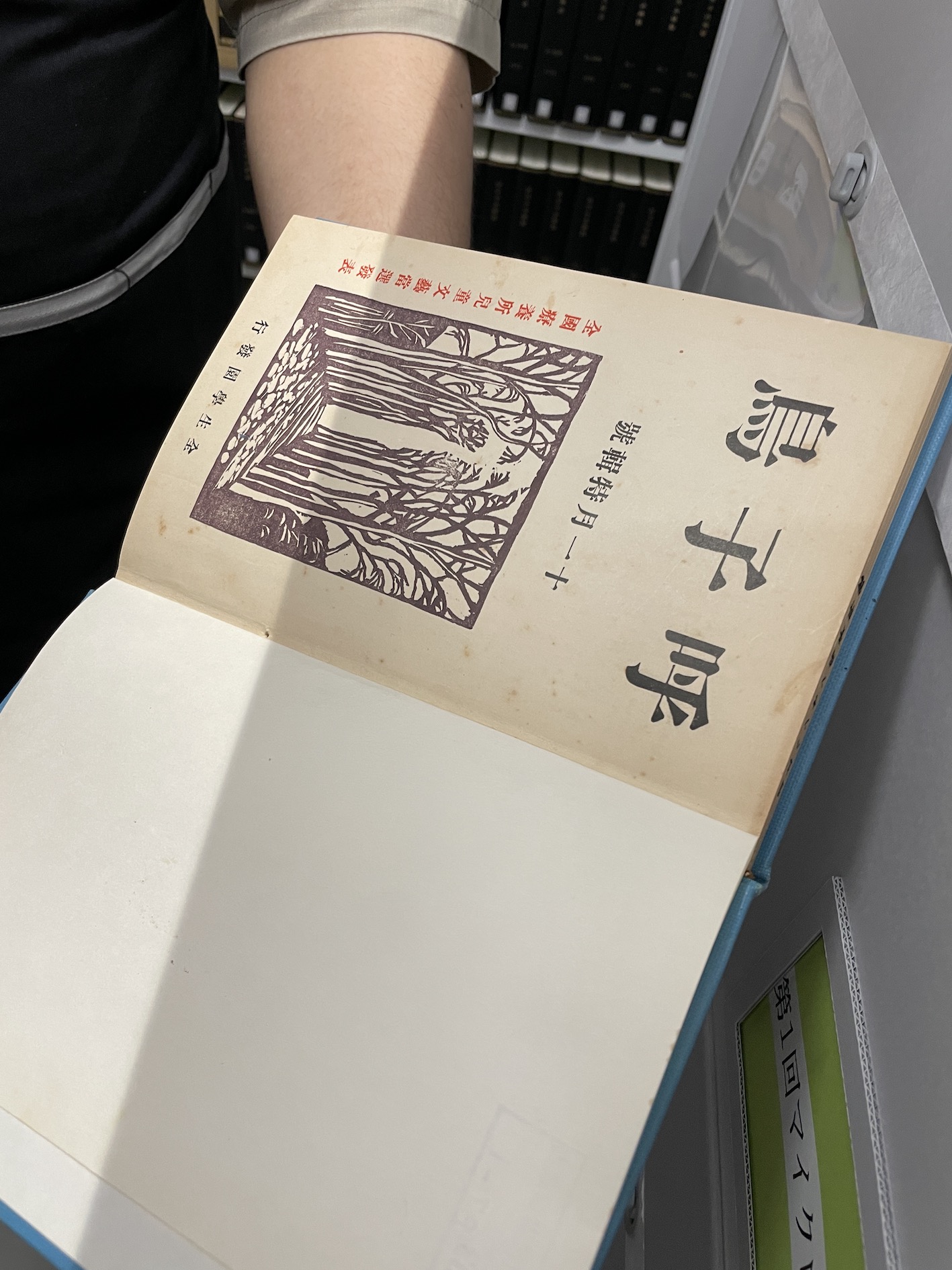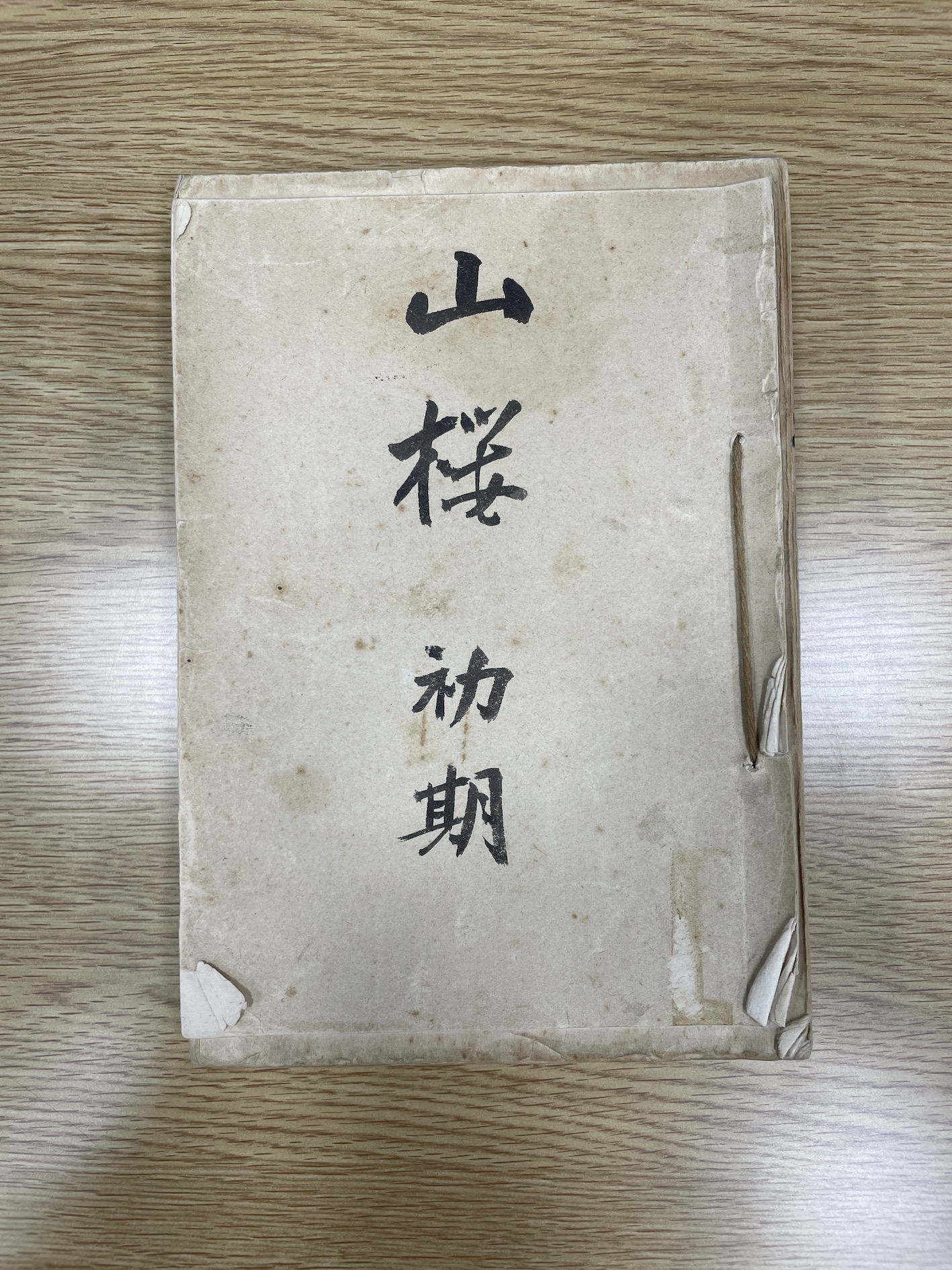■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■
。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。
古書市&古本まつり 第117号
。.☆.:* 通巻356・10月11日号 *:.☆. 。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━【シリーズ書庫拝見7】━━━━━━━━━
国立ハンセン病資料館 患者たちの手で集め、守った資料
南陀楼綾繁
国立ハンセン病資料館の書庫を見たいと思ったのは、YouTubeで観
た一本の動画がきっかけだった。
今年3月に同館が開催したオンラインミュージアムトーク「図書室
からの招待状~頁をめくり、想いを辿る~」は、図書室職員の斉藤聖
(あきら)さんが閲覧室や書庫を案内し、この図書室の役割を伝える
ものだった。斉藤さんの優しそうな風貌やソフトな語り口が心地よく、
見入ってしまった。
私はハンセン病については無知だ。映画『砂の器』(野村芳太郎監督、
1974)で、私が偏愛する俳優の加藤嘉がハンセン病患者の老人を演じ、
故郷を追われ、各地をさまよう場面が印象に残っているぐらいだ。ち
なみに、松本清張の原作にはこういった描写はない。
続きはこちら
https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=10202
南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)
1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一
文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、
図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年
から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」
の代表。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、「石巻まちの本棚」
の運営にも携わる。著書に『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、
『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』
(ちくま文庫)、『古本マニア採集帖』(皓星社)、
編著『中央線小説傑作選』(中公文庫)などがある。
ツイッター
https://twitter.com/kawasusu
国立ハンセン病資料館
https://www.nhdm.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「コショなひと」始めました
東京古書組合広報部では「コショなひと」というタイトルで動画
配信をスタート。
古書はもちろん面白いものがいっぱいですが、それを探し出して
売っている古書店主の面々も面白い!
こんなご時世だからお店で直接話が出来ない。だから動画で古書
店主たちの声を届けられればとの思いで始めました。
お店を閉めてやりきったという店主、売り上げに一喜一憂しない
店主、古本屋が使っている道具等々、普段店主同士でも話さない
ことも・・・
古書店の最強のコンテンツは古書店主だった!
是非、肩の力を入れ、覚悟の上ご覧ください(笑)
コショなひと 大屋書房 後編
YouTube 東京古書組合
https://www.youtube.com/channel/UCDxjayto922YYOe5VdOKu9w
━━━━━【10月11日~11月15日までの全国即売展情報】━━━━━
⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init
※現在、新型コロナウイルスの影響により、各地で予定されている
即売展も、中止になる可能性がございます。ご確認ください。
お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
------------------------------
TOKYO BOOK PARK 吉祥寺
期間:2022/05/20~2022/10/30
場所:吉祥寺パルコ2階 武蔵野市吉祥寺本町1-5-1
https://twitter.com/TOKYOBOOKPARK
------------------------------
第2回 サンモール古本市 in 金港堂(宮城県)
期間:2022/09/29~2022/11/06
場所:金港堂本店 仙台市青葉区一番町2-3-26
------------------------------
第22回 四天王寺 秋の大古本祭り(大阪府)
期間:2022/10/07~2022/10/12
場所:大阪 四天王寺境内内 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-11-18
http://kankoken.main.jp/
------------------------------
第27回八王子古本まつり
期間:2022/10/07~2022/10/11
場所:JR八王子駅北口ユーロード特設テント
------------------------------
横浜市歴史博物館・古書フェア(神奈川県)
期間:2022/10/12~2022/10/23
場所:横浜市歴史博物館1階エントランス(入館無料エリア)
横浜市営地下鉄ブルーライン・グリーンライン「センター北」駅より徒歩5分
https://www.rekihaku.city.yokohama.jp/
http://kosho.saloon.jp/spot_sale/index.htm
------------------------------
ぐろりや会
期間:2022/10/14~2022/10/15
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
http://www.gloriakai.jp/
------------------------------
本の散歩展
期間:2022/10/14~2022/10/15
場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4
JR山手線、東急池上線、都営浅草線五反田駅より徒歩5分
------------------------------
フィールズ南柏 古本市(千葉県)
期間:2022/10/14~2022/11/02
場所:フィールズ南柏 モール2 2階催事場 柏市南柏中央6-7
------------------------------
京都まちなか古本市(京都府)
期間:2022/10/14~2022/10/16
場所:京都古書会館3階 京都市中京区高倉通夷川上ル福屋町723番地
https://kyoto-kosho.jp/
------------------------------
平井のはみだし古本市
期間:2022/10/15~2022/10/23
場所:平井の本棚 2階 イベントスペース 江戸川区平井5-15-10
総武線平井駅北口下車30秒
https://hirai-spheniscidae.peatix.com/
------------------------------
秋の路面古本市 【第2回】(広島県)
期間:2022/10/15~2022/10/16
場所:広島PARCO本館1F 店頭 広島市中区本通10-1
https://hiroshima.parco.jp/pnews/detail/?id=20505
------------------------------
ア・モール古本市(北海道)
期間:2022/10/20~2022/10/25
場所:アモールショッピングセンター1階センターコート 住所:北海道旭川市豊岡3条2丁目2‐19
------------------------------
洋書まつり Foreign Books Bargain Fair
期間:2022/10/21~2022/10/22
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
http://blog.livedoor.jp/yoshomatsuri/
------------------------------
好書会
期間:2022/10/22~2022/10/23
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
------------------------------
秋の路面古本市 【第3回】(広島県)
期間:2022/10/22~2022/10/23
場所:広島PARCO本館1F 店頭 広島市中区本通10-1
https://hiroshima.parco.jp/pnews/detail/?id=20505
------------------------------
第101回シンフォニー古本まつり(岡山県)
期間:2022/10/26~2022/10/31
場所:岡山シンフォニービル1F 自由空間ガレリア
------------------------------
浦和宿古本いち(埼玉県)
期間:2022/10/27~2022/10/30
場所:さくら草通り(JR浦和駅西口 徒歩5分 マツモトキヨシ前)
https://twitter.com/urawajuku
------------------------------
特選古書即売展
期間:2022/10/28~2022/10/30
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
https://tokusen-kosho.jp/
------------------------------
第62回 東京名物 神田古本まつり
期間:2022/10/28~2022/11/03
場所:神田神保町古書店街(靖国通り沿い・神田神保町交差点他)
https://jimbou.info/news/20220915.html
------------------------------
杉並書友会
期間:2022/10/29~2022/10/30
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
------------------------------
第46回 秋の古本まつり―古本供養と青空古本市―(京都府)
期間:2022/10/29~2022/11/03
場所:百萬遍知恩寺境内 京都府京都市左京区田中門前町103
http://koshoken.seesaa.net/
------------------------------
東京愛書会
期間:2022/11/04~2022/11/05
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
http://aisyokai.blog.fc2.com/
------------------------------
オールデイズクラブ古書即売会(愛知県)
期間:2022/11/04~2022/11/06
場所:名古屋古書会館 名古屋市中区千代田5-1-12
https://hon-ya.net/
------------------------------
古書愛好会
期間:2022/11/05~2022/11/06
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
------------------------------
新橋古本市
期間:2022/11/07~2022/11/12
場所:新橋駅前SL広場
------------------------------
BOOK & A(ブック&エー)
期間:2022/11/10~2022/11/13
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
------------------------------
趣味の古書展
期間:2022/11/11~2022/11/12
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
https://www.kosho.tokyo
------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信
を希望された方にお送りしています。
ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。
【日本の古本屋】は全国981書店参加、データ約630万点掲載
の古書籍データベースです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
見逃したメールマガジンはここからチェック!
【バックナンバーコーナー】
https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=39
┌─────────────────────────┐
次回は2022年10月下旬頃発行です。お楽しみに!
└─────────────────────────┘
*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*
全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です
https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner
==============================
日本の古本屋メールマガジンその356 2022.10.11
【発行】
東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」
東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館
URL http://www.kosho.or.jp/
【発行者】
広報部・編集長:藤原栄志郎
==============================
・メールマガジンの購読停止、アドレスの変更はこちら
https://www.kosho.or.jp/mypage/
・このメールアドレスは配信専用です。
返信いただいても対応致しかねます。ご了承下さい。
・メールマガジンの全てまたは一部を無断転載することを禁じます。
・メールマガジンの内容に対するご意見、ご感想は
melma@kosho.ne.jp までお願い致します。
・メールマガジン内容以外のご質問は info@kosho.or.jp へお願い
いたします。なお、ご質問の内容によりましては、返信が大幅に
遅れる場合もございます。ご了承下さい。
============================================================
☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*゜*・゜☆*.:*・
============================================================