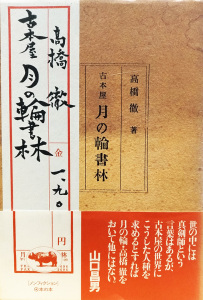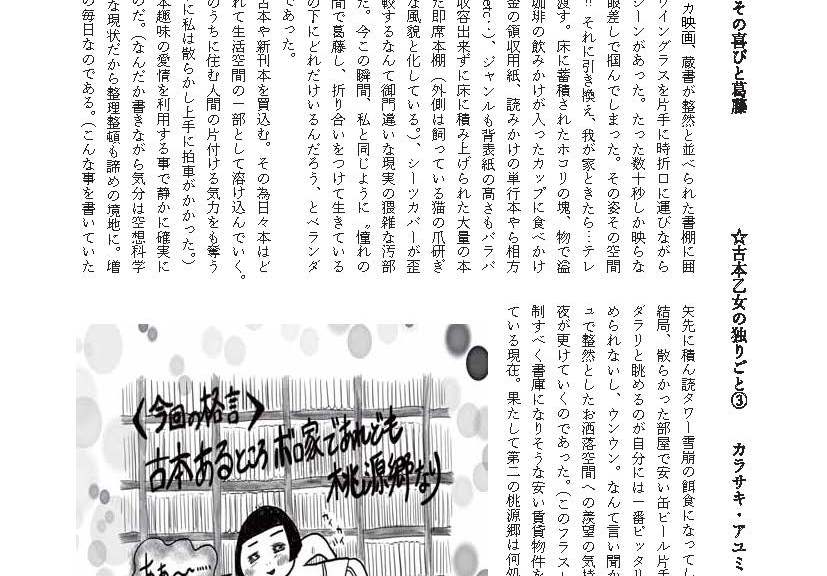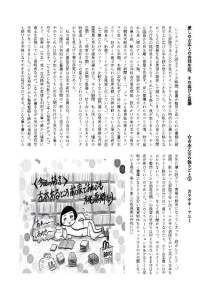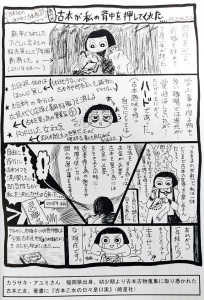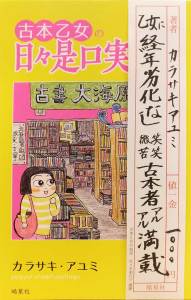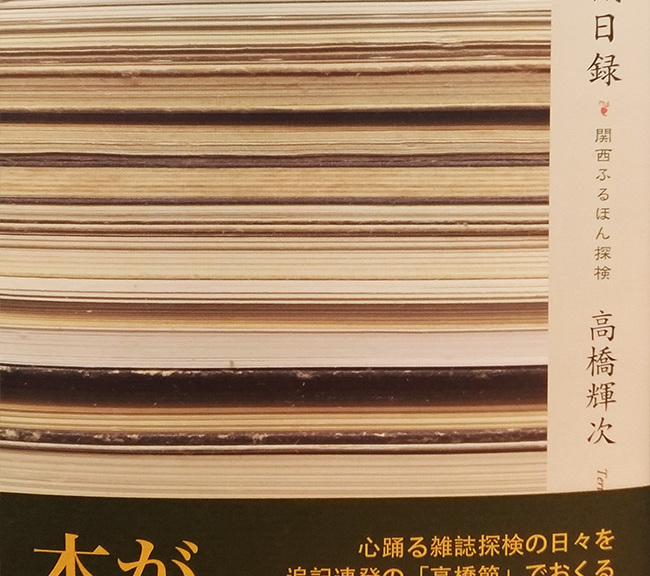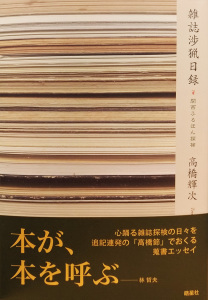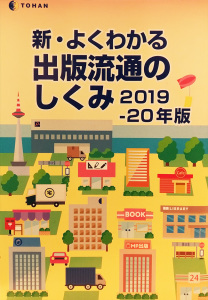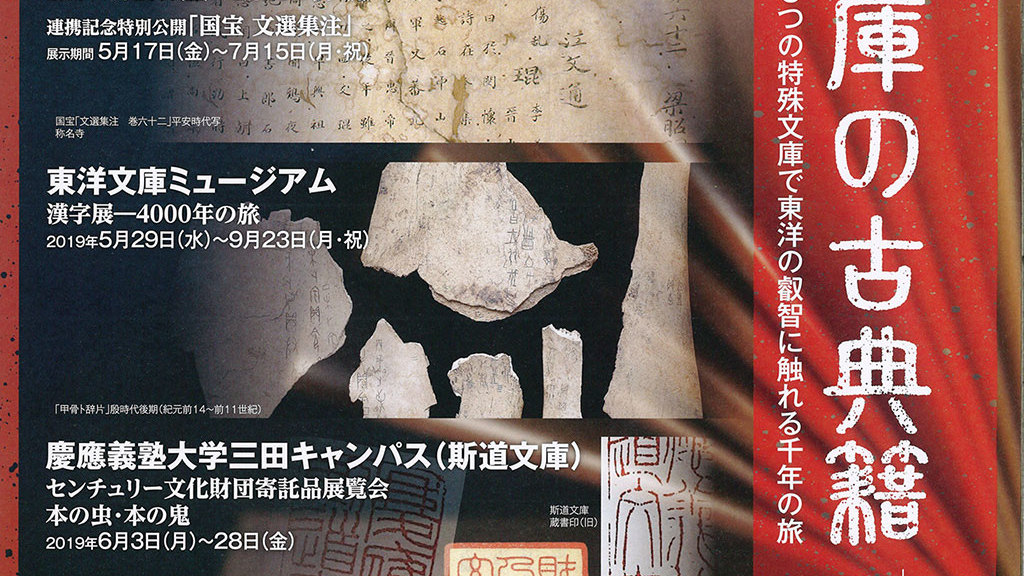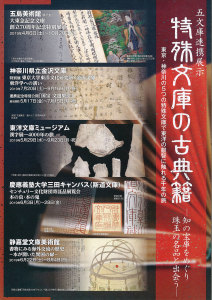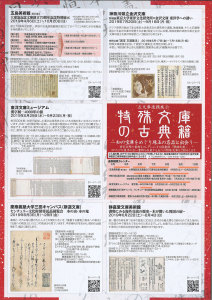第6回 中根ユウサクさん 息子に妖怪を教え込むひと
|
| 「見て見て―、この本すごいんだよ!」と、『こども妖怪・怪談新聞』(世界文化社)をめくって私に見せるのは、小学1年生のソウスケくん。今回登場願うのは彼……ではなくて、その横に座るお父さんである中根ユウサクさんだ。 子どもの頃から筋金入りの怪奇やSF好きである中根さんは、ソウスケくんが物心つくかどうかの時期から妖怪についての英才教育を施し、ソウスケくんは立派な妖怪マニアに成長した。『ゲゲゲの鬼太郎』が大好きで、親子で高円寺の即売会に出かけ、水木しげるの『妖怪大図鑑』(講談社)を買ってもらった。そういえば、いま見せてくれた『こども妖怪・怪談新聞』も水木プロダクションの監修だ。 親子二代にわたる妖怪本好きは、どのようにして生まれたのだろうか? 中根さんは1977年、愛知県豊田市生まれ。両親は公務員で、父は本好きだった。とくにマンガが好きで、あだち充から岡崎京子まで幅広く読んでいた。また映画も好きで、まだレンタルビデオがはじまった頃に借りてきて、アニメや怪獣映画を息子と一緒に観たという。小学2年のとき、『ゲゲゲの鬼太郎』のアニメの新シリーズがはじまり、親に原作や妖怪図鑑を買ってもらった。 古本屋について教えてもらったのも父からで、小学5年のときに市内の古本屋に連れて行ってもらい、マンガを買ったという。親子二代と書いたが、三代にわたって本についての知識が伝えられているのだ。 一方、学校図書館には子ども向けのSFや怪奇もののシリーズがあり、それらを読んだ。 「なかでも覚えているのが、あかね書房の『少年少女世界SF文学全集』に入っていたジョン・ウィンダムの『怪奇植物トリフィドの侵略』です。食人植物と文明が滅びるという、ハッピーエンドではない物語に衝撃を受けました」 中根さんは中学に入っても、本やマンガ、アニメに浸っている。高校では市の中央部に電車通学するようになり、行動範囲が広がった。 「本屋でサブカルの要素が強かった時期の『ガロ』を買って教室で読んだり、季刊『幻想文学』で紹介された作品を古本屋で探していました。同じクラスに探偵小説好きの友人や先生がいて、ぼくが黒板にいたずらで『大坪砂男』と書いたら、それを見た先生が(代表作の)『天狗』について語りだすくらいで(笑)」 この頃、のちに絶版文庫ブームを牽引した〈ふるほん文庫やさん〉が豊田市に開店している。中根さんはそこに通って、同店が発行する目録を読むことで、古本の基本的な知識を得る。ここで買ったのが、ウィンダムの『トリフィド時代』(創元推理文庫)。同じ作品のジュブナイル版を小学生で読んでいる。大げさに云えば、この作品はのちの中根さんの行動原理になる。 名古屋にある大学の経済学部に入り、大学の近くにあった〈ヴィレッジヴァンガード〉の本店でアングラやサブカルの本を買ったり、映画館でSFやホラー映画を観まくり、自主映画をつくってコンテストに応募するほどになる。中根さんの話を聞いていると、ともかく同時期にいくつもいろんなことに深くハマっているのが判る。 「大学では教授から大学院への進学を勧められました。ドクター中根という響きにちょっと惹かれましたが、自分がやりたいのはやっぱり妖怪のことだと思いました。それで、別の大学で民俗学を学ぼうとも考えたのですが、結局、映像関係の会社に就職しました」 仕事はきつく、古本屋通いが唯一のストレス発散法だった。SFやミステリー、UFO、オカルトなどの本を扱う〈猫又文庫〉の店主と意気投合し、仕事帰りに店に寄って話すのが楽しかった。どんな本がレアかということも教えてもらったという。 後に中根さんは、転職して2006年に東京に引っ越す。 「初めて来たときは、神保町に行くのに神田駅で降りるという定番のミスをしています(笑)。神保町に電車一本で行けるところに住み、毎週のように即売展に通いました」 そこで昭和初期に発行されたエログロ雑誌『猟奇画報』を手にして、妖怪が出てくることに驚く。これまで自分が考えていたよりも、「妖怪」というテーマには広がりがあると気づいたという。この雑誌に関わった民俗学者・風俗史家の藤澤衛彦は、妖怪研究のキーパーソンの一人である。 「エログロ雑誌から検閲や発禁のことを知りたくなるというふうに、興味の範囲がどんどん広がっていきました」というように、平田篤胤『古今妖魅考』という和本から、科学者にして心霊学者のカミーユ・フラマリオンが書いた『科学小説 世界は如何にして終るか』(改造社、1923)まで、ここでは紹介できないほど多くの単行本や雑誌を見せてもらった。 東京での中根さんは、妖怪についてのイベントに参加したり、コミケで妖怪の同人誌を出している人に会ったりと、知り合いを増やしていった。北原尚彦さんが会長を務める日本古典SF研究会にも属し、毎月の例会にも参加する。また、超常現象を取り上げる同人誌『Spファイル』とその後継誌『UFO手帖』にも参加している。いったい、いくつ並行してやってるんだ! 「喫茶店に集まって、蔵書を見せ合う会もやっていました。本は一人で集めていても広がりがない。詳しい人と情報交換することで、『そんな本もあるのか!』と知ることができるんです」 いま、中根さんが熱中しているのは、動く植物。先の『トリフィド時代』に出てきた食人植物の類(たぐい)は、さまざまな時代・場所の書物に見られるという。 「これも妖怪の仲間ですね。日本における食人植物のイメージが、どのように変遷していくかを追っているところです」 中根さんは、ネットや目録ではほとんど古本を買わず、店や即売展で買うようにしている。本の状態を確かめて、納得してから買いたいという気持ちが強いそうだ。 「内容が面白くても、状態が悪ければ買わないことがありますし、後でいい状態のものが出たときは買いなおすことがあります。本は自分だけでなく、次の世代の人のものでもあると思うので。死んだあとは息子が継いでくれれば嬉しいですし、彼がその頃には妖怪から離れていたら古本屋を通じて市場に戻してもいいんです」 もっとも、アマゾンやヤフオクを使わないことで自分に制限をかけている面もある。 「興味の範囲が広がるばかりで、当然本は増えていきます。妻は結婚前から私の古本趣味は知っていますが、すでに部屋が二つ本で埋まっているので、二人いる子どもが大きくなったらスペースをどうしようと、いまから頭が痛いです」 ここでソウスケくんが「パパの部屋は本の川みたいになっていて、入り口がないんだよ」と口をはさむ。中根さんが云うには、生まれたときから本の山に囲まれているので、狭いすき間をすり抜けるのに慣れているのだとか。もっとも、怖い絵の表紙の本が多いので、「あの本をどこかに隠してくれ」と頼むというのがカワイイ。 このインタビューは出版社の一室で行なったのだが、ソウスケくんが「ここも本がいっぱいあるけど、うちよりはマシですよ」と真面目くさっていったのには笑った。 中根さんの今後の探書と研究がますます深まることに期待するとともに、ソウスケくんが立派な古本マニアに育っていくように祈りたい。20年後ぐらいに、また親子でインタビューさせてほしいものです。
南陀楼綾繁 ツイッター
|
|
Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |