『出版を「自分事」として語るために』山崎隆広(群馬県立女子大学) |
|
2023年1月、15名の訳者の方々とともに本書を訳出、上梓した。A5判506頁函入。出版が抱える様々な課題を、歴史、経済、法、流通、テクノロジーなど複合的な視点から25章にわたって論じた税込26,400円(!)の大著である。筆者は本書監訳者の一人を務めさせていただいたが、巷間「出版不況」がいわれつづけるなか、決して安くはない価格でありながら、このような正統的出版学の研究書が出版されることはとても重要なことだと思うし、大変嬉しい。世の中まだまだ捨てたものではない、と思う。
2023年3月25日付『図書新聞』(3584号)掲載の監訳者鼎談の際にもお話ししたのだが、筆者は、本書にはこれまでの出版学の本にはない3つの特徴があると思っている。ひとつめは「メディア論」の視点があるということ。出版にまつわる本というと、どうしても出版の歴史を語るメディア史や、売上の増減を語る産業論の視点に傾きがちになるが、本書にはマクルーハン、フーコー、ブルデューなど、現代思想の重要な知見に基づいた分析が多分に盛り込まれていて、「メディアとしての出版」を根本的なところから語り起こそうとする姿勢が基底にある。メディア論の学徒にとっても非常に有用な視点を提供くれるといえるだろう。ふたつめは、ひとつめの点と関連するが、「出版と技術の関係」に対する言及がきちんとあるということである。出版メディアもその閉じられた世界の中のみで完結しているわけではなく、特に近年は他の様々なメディア技術と影響を与え合いながら成っていることは明らかなのだから、メディアを構成する「技術」に対する批判的視点がしっかり盛り込まれている本書の視座は、大変重要なものと考える。そして3つめとして、本書には伝統的な経済学に基づいた分析があることも非常に特徴的な点といえるだろう。スミス、リカード、マルクス、イリイチなどの名前や、「行動経済学」「不確実性回避指数」「効率的市場価格」などの用語が出てくる出版学の本というのも、あまり類例がないのではないだろうか。 さらに、本書を通じて感じたのは、出版という我々の営みをめぐる問題が、いまや世界的に共通なものになりつつあるということである。原著の出版はイギリスだが、本書の視点はゲームやコミックなど、ほんの少し前までは日本のサブカルチャーの十八番と思われていた領域や、アジアの検閲の問題にまで及んでいる。10年、20年前であれば「それって海外の出版の話でしょ、日本とは歴史も制度も慣習も違うから」で片付けられてしまいそうな出版をめぐる問題系が、本書を読むと世界共通の「我が事」として迫ってきているように思われるのである。そういった変化の背景には、やはりいくら論じても結論が見えそうにない「デジタル化」や「グローバリゼーション」の問題があることは確かだろう。これまで出版メディアに特徴的だったローカリティが失われつつあることを、本書は示唆するのである。 ここまで読んでいただいた方にはお分かりの通り、本書は単なる「出版関係者のための専門書」ではない。出版のみならず広くメディアについて研究する研究者、そして出版界に限らず新しいメディアビジネスを構想する実務者など、広く「メディア」に関わりのある人たち(つまりあらゆる人々ということだが)に読んでもらいたい、哲学的で実践的な本なのである。 さて、この原稿の冒頭で、私は「出版不況」と書いた。しかしその舌の根の乾かぬうちに、筆者は早くもその語りの作法を訂正したい欲望にかられている。この数年あるいは数十年の間の出版をめぐる報道などをみても、「出版」といえば「不況」とあたかもセットのように語られることが多い。しかし、本当にそういった視点でことを片付けてしまってよいのだろうか。近年の「出版不況」を「デジタル化」や「グローバリゼーション」といった言葉に集約させて、つまりは自分以外の「他者」によってもたらされた予期せぬ災厄のように語って納得してしまってはいないか。例えば本書には、「重要なのは、出版社の仕事である情報・文化的生産は、より広い背景を単純化しすぎることなく媒介するという点である」(263頁)といった記述があるが、「不況」の対極で生じている様々な事象を、我々は今こそきちんと検証する必要がある。自戒を込めていえば、「出版=不況」というような脊髄反射的な語り口こそ、我々が見直すべき姿勢なのではないだろうか。 世界の出版をめぐる問題を、「他人事」ではなく「自分事」として語るということ。我々人間がそうであるように、果たして出版もまた「歴史的存在」であるのなら、やはり出版も人間の終わらない「動的営み」として、歴史的文脈において語られなければならない。本書では、出版の未来についての安易な希望は語られていない。終章で示されるディストピア的な未来予想図もまた、著者たちが抱く確信的なビジョンというよりも、むしろこれからの出版に対して安易に結論を出すことについての拒否であり、また著者たちの思考の混乱をそのまま提示するというある種の誠実さとして捉えるべきだろう。 おそらく、出版に対する「デジタル化」や「グローバリゼーション」の影響はこれからもまだまだ進んでいく。AIなどの技術進化に対する無防備な礼賛も止まらないだろう。しかし、そういったいわゆるアルゴリズム的思考に収まらない予測不可能性をもつのが我々の社会であり、出版という営為である。出版は豊かで、楽しい。本書はそんなことを考えさせてくれるきわめて貴重な事典なのである。 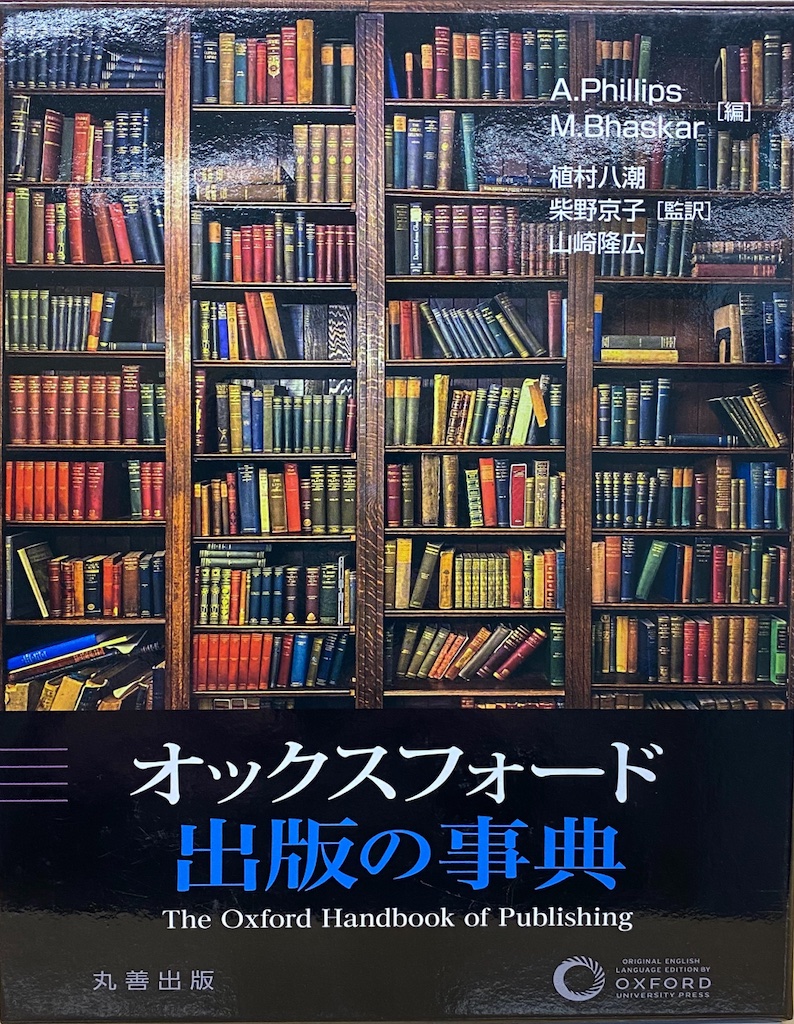 『オックスフォード 出版の事典』 丸善出版 2023年1月発行 A.Phillips, M.Bhaskar編 植村八潮・柴野京子・山崎隆広監訳 A5/528ページ ISBNコード:978-4-621-30792-2 定価:26,400円(税込) 好評発売中! https://www.maruzen-publishing.co.jp/item/?book_no=304830 |
|
Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |



















