『シティ・ライツ ノート』編集サークル街から舎 主宰・本間健彦 |
|
本書は本年(2023年)3月末に、わたしの主宰する編集サークル街から舎という個人事務所から刊行されました。補足説明をさせていただくと――。実は、街から舎は編集プロダクション業務を行う株式会社として1985年に創業し、2000年代入ってからは小さな出版事業にも手を染めてきたのですが、コロナ禍の昨年8月に会社組織を解散し、仲間と編集サークルを立ち上げ、身の丈にあった編集業務を続行していこうと方針転換を図りました。つまり本書は表向き街から舎が版元となって刊行するかたちをとっていますけれど、実情はいわば自主出版だったということになります。
この『シティ・ライツ ノート』という本は、わたしにとって単著としては9冊目の単行本ということになります。モノ書きの著作数としては寡作ですね!とよく言われるのですが、わたしは編集業を生業としてきまして、その合間に「これって本になりそうだな!」と閃いた人物や事象に出会うと、本を出してくれそうな出版社を探して企画を売り込み出版してもらってきたのです。そんな無名のノンプロ・ライターによる著述業なので、この位の著作数が精一杯だったのでしょう。 わたしは編集業を生業にしてきたわけですけれど、その遍歴をかいつまんで申しあげますと。『話の特集』の編集者を経て、1969年6月から72年3月まで新宿のタウン誌『新宿プレイマップ』の編集長を務め、その後はフリーランスの編集者・ライター稼業に長く従事したのち、冒頭に記したように(株)街から舎を設立して主宰するようになります。そして1992年10月、『街から』と題したミニコミ誌を有志市民と共に創刊し、街から舎から隔月刊で刊行してきました。 『街から』は、その誌名のためだったのか、外目にはタウン誌のように映っていたようですけれど、わたしたちスタッフは「シティ・マガジン」(市民誌)を標榜してきました。その理由は「インディペンデント・マガジン創ろう!」という意向と志を持った<有志市民>たちのメディアを目指したからでした。自立メディアを創りたいというのは、わたしの長い間の夢であり宿題だったのですが、しがないフリーランサーの身では日々の生活に追われるばかりで、実現の見通しなどとても立てられなかった。ところがあるとき、ふっと、「ミニコミ誌なら作れるのではないか・・・」という発想が啓示のように閃いたんですね。 ミニコミというのは、60年代末から70年代初頭にかけ、カウンター・カルチャーの蜂起した時代に活字志向の若者たちが、あるべき姿の生き方を模索し表明する表現活動の場として作っていたガリ版刷りやタイプ印刷の手作りの新聞・雑誌の呼称なのですが、90年代にはミニコミを作る若者たちはすでに消滅していて、絶滅危惧種のメディアと見做されていました。わたしは当時すでに五十路を迎えていたのですけれど、何を血迷ったのか、あの時代にアヴァンギャルド志向の若者たちが創っていたミニコミの事を思い出し、その手法にヒントを得て無謀にも「街から」誌の刊行に踏み切ったのです。 では、ミニコミの手法とはどんなものだったのでしょうか。端的に言えば、自立メディアを創るためには非商業主義路線をどれだけ徹底して歩めるかどうかという点が要諦でした。『街から』が律した要諦は、①市民会員を募り、会費として購読料をいただく。②『街から』誌の雑誌作りの方針に賛同してもらえる企業及び店舗に限定して広告料を取得する。③編集発行人及び編集スタッフ(ボランティア参加)の報酬はなし。ただし編集制作に要する経費は清算して支払う。④寄稿者やインタビュー取材をお願いした方に対する原稿料や謝礼の支払はしない。⑤雑誌編集発行に要する経費は、①と②を集計した収入によって賄う事を原則とする。以上のような点だった。 ずいぶんけち臭く、情けない手法なのですけれど、このような手法を貫かなければ、ミニコミ誌とはいえ自立メディアを立ち上げ存続させて行くことは不可能なのだ、と判断したうえでの選択でした。 しかし難題や課題は他にもあった。最も憂慮したのは、『街から』誌が対象とする<有志市民>が果して存在するのか否かという点でした。というのも『街から』の希求した<有志市民>というのは、こよなく自由を愛し、それぞれの人びとが各自のあるべき姿の生き方を目指す、そういう市民像を対象としていたからです。けれどもご承知のように、日本の社会には地域社会は存在するけれど、市民社会は未成熟と見做さざるを得ませんし、それゆえ市民意識も確立されているとはいえない状況が露見していたからです。 創刊当初、この国はバブル経済崩壊直後でまるで氷河期に突入するような時代であったので、友人・知人たちからは「どうせ3号雑誌に終るのだろうから、無謀な冒険は止めといた方がいいぞ」とずいぶん忠告を受けました。その危惧の念はミニコミ手法の貫徹で何とかしのぎ3号雑誌で終ることなく持続することはできたのですが、市民会員を増大し、市民が作る自立メディアとして大きく発展させるまでに至らなかったのは、わたしたちの力不足だったという点は否めなかったにしても、やはりこの国の市民社会の未成熟な点や市民意識の希薄な国民性という根深い壁にはばまれたのではないかという想念を抱かざるを得ませんでした。 そんな閉塞状況のなかで苦戦は免れなかったのですが、何とか『街から』は持続することができ、2000年12月に通巻50号を刊行する事ができました。隔月刊の発行で、創刊9周年目に達成できたのです。わたしたちにとってはまさに快挙!でした。50号の刊行を記念して街から舎ではインタビュー集『人間屋の話』という単行本を出版しています。この本はわたしがそれまでの『街から』に掲載してきた<有志市民>のオピニオンたち16人に対するインタビュー記事で編纂したもので、和田誠さんにカバーデザインをお願いしていて、その後、街から舎が出版事業に進出する端緒となる出版でした。 この『人間屋の話』を出版した際の出来事で今なお印象深く心に刻まれているのは、16人の登場人物のひとりで、序文の執筆まで引き受けてくださった故マルセ太郎さん(<笑いの哲人>として誉れ高かった方です)の次の言葉です。 われわれのような権力から遠い者は、一人ひとり無力かもしれない。しかし これはマルセ太郎さんから、街の小さなメディアをこつこつと作っているわたしたちへの激励のメッセージだったのだと思います。わたしたちはマルセさんがともしてくれた灯りをかかげ、ほふく前進を続けてきました。発行部数の伸び方の微小さには頭を痛めていましたが、手ごたえは感じていました。 けれども、2000年代に入ると、周知のようにインターネットの普及により若い人たちのあいだでは、ブログやツイッターで自分の意見や情報を発信し、情報交換する日常が普遍化し、それにともない新聞や雑誌など印刷媒メディア離れが加速する現実に直面することになります。また、経済至上主義の縦断爆撃現象が人びとの日常・価値観・生き方に根深く浸透している様子をニュース見聞するにつけ、人間は壊れつつあり、人類は破滅の道を突き進んでいるのではないかという危惧を抱かざるを得ませんでした。 だがしかし、わたしたちも結局、強大な圧力とわたしたちを取り囲む超大に壁に阻まれ、敗北するしかなかったのだな・・・と見做す事になります。でも、たぶん多くの皆さんは、街の片隅の小さなメディアの敗北物語などに耳を傾けたくはないでしょうし、当事者としても、もうこれ以上語りたくはありません。なので、結果だけを申し上げておきましょう。 • 20019年3月、『街から』は通巻157号を刊行し、終刊としました。 本書『シティ・ライツ ノート』は、数本他誌に寄稿した記事が入っていますけれど、大半は『街から』に掲載されたわたしのインタビュー記事、ルポ、コラム、編集後記などのなかから記事を選抜し編纂しました。添付したチラシに目次を記してありますので、ご覧いただき、もし関心のありそうな記事がございましたら、本書をご購入いただき、お読み頂ければ幸甚です。 蛇足かもしれませんが、本書を刊行した意図を付け加えておきます。それは、『街から』というミニコミ誌にどんな面々が賛同して加わってくださっていたのか、その一端を是非記録しておきたかったからなのです。 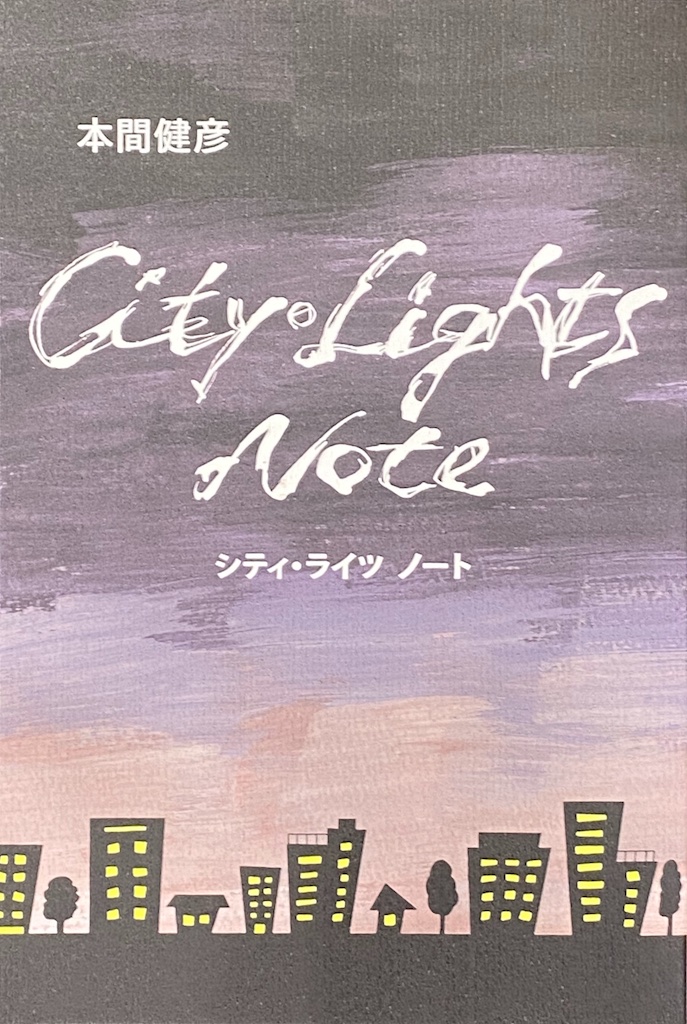 『シティ・ライツ ノート』 街から舎刊 本間健彦著 税込価格:2,200円(税込) ISBNコード:9784939139284 好評発売中! https://machikarasha.thebase.in/items/73875259 |
|
Copyright (c) 2023 東京都古書籍商業協同組合 |



















