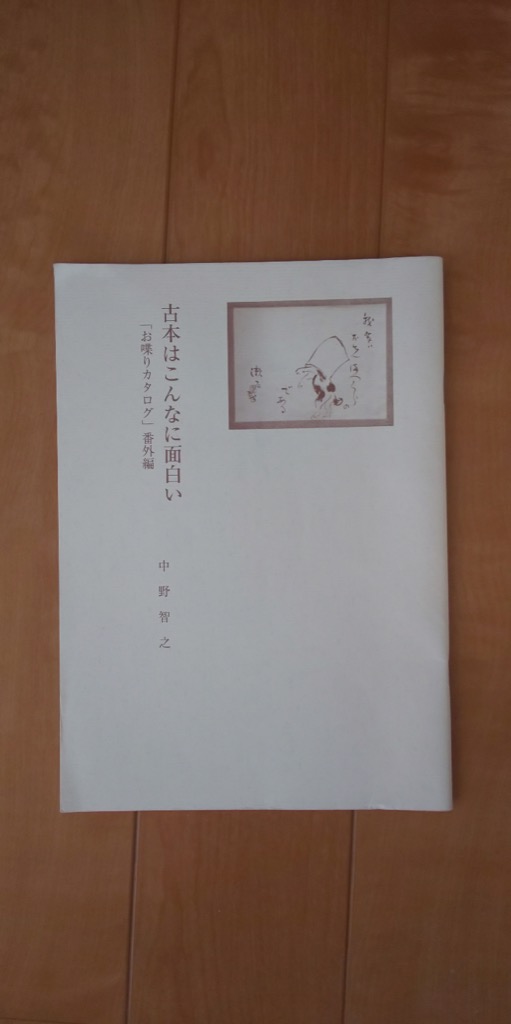懐かしき古書店主たちの談話 第4回日本古書通信社 樽見博 |
|
神保町の古書街の魅力は何かと言えば、毎週末の会館展と内容豊富な各店の均一台と答える古書ファンは少なくないだろう。かく言う私もその一人だ。均一小僧を名乗っていた岡崎武志さんとは、田村書店の店先や、四冊100円の棚があった文省堂書店(前々回書いた明文堂さんの隣にあった時代)、神保町古書モールかんたんむ書店の100円均一棚の前で良く出会った。会うたびに「樽見さん神保町パトロールですか」と笑っていわれた。
最近ファンからの要望で再開した小宮山書店ガレージセールで良く出会ったのが中野書店の智之さんだった。私と同年だが、文学書は勿論、古典から漫画まで古書全般に通じた数少ないオールラウンダーだった。「日本古書通信」の古書目録欄は毎号欠かさず掲載してくださり、売れないなどの苦情を言われたことも一度もない、本当にありがたいお客様でもあった。 智之さんは中野書店の二代目。父上実さんは、九大工学部卒のインテリだが、戦地から帰還した兄上が久留米で開いていた古書店を引き継ぐ形で古本屋になった。昭和35年に一大決心して上京、三鷹に出店した。昭和53年には神田古書センターに移転、当時の神保町では珍しい漫画や児童物を専門に扱った。その後文学書や古典を扱う有力書店になったことは周知のことであろう。実さんのお話は、平成15年3月号「古本屋の話3」で取り上げている。体の大きな方で、それは智之さんに遺伝している。実さんは平成13年に奥様に先立たれ、追悼の冊子を作られた。そこには智之さんの少年時代の写真が沢山収められていた。所謂坊ちゃん刈で、大きな襟のついたジャンパー姿、私は茨城の田舎の少年で、智之さんはいかにも東京の少年だが、同じ時代を生きてきたのだなと感慨深いものがあった。実さんと智之さんは仲の良い親子で、智之さんが優しく父を敬っていたという印象が強い。「日本古書通信」への初めての寄稿も「親父の目録」(1993年12月号)であった。 実さんは苦労した創業者として商売一途の面があったが、智之さんは組合や交換会の運営にも積極的に尽力されていた。実力も人望もあるから当然であったろう。神田古書店連盟や東京古典会の会長や役員も何期か勤められている。東京古典会会長当時、智之さんと小林書房の小林芳夫さん、一心堂書店の高林和範さん、浅草御蔵前書房の八鍬光晴さんに「東京古典会古典籍大入札会への思い」と題して東京古典会の運営について座談会を「日本古書通信」に掲載したことがある。(2013年11月号) 智之さんは「明治古典会は新しさを追求しようという姿勢が強いですね。いろいろアイディアを活かしていこうとします。東京古典会はその点変わらないというか、姿勢を変えない。珍しくて貴重な書物や資料を掘り起こし、業者が競争して、その価値を高めていこうという、その点はずっと昔から変わっていない」「お客さんの変化に合わせるというのではなく、和本というのはこういうところが面白くて、価値があるのだという、これまで積み上げてきた専門業者の目を信じてお客さんの方が、こちらに近づいてきて欲しい。それを願ってやっている」などと語っている。 神田古書店連盟の最も大事な行事が神田青空古本まつりの開催である。毎回連合目録を出していたが、各店の古書目録だけでなく、巻頭に諸家の古本にまつわるエッセイを掲載していた時期があり、司馬遼太郎氏など著名な作家の寄稿もあったと記憶する。この企画も智之さんなどのアイディアではなかったかと思う。智之さんご自身も確か「牛肉の味噌漬け」という一文を書いていた筈である。作家の書簡などに人気が出始めたころで、著名人のものは軒並み高額になる、所謂自筆物バブルが起きた。そんな中で智之さんも漱石の葉書を買った。それが牛肉の味噌漬けを貰った礼状で文学的資料にならない。著名な作家の書簡でも内容を見て扱わねばと自らを戒めたといった内容だった。それが面白可笑しくユーモアにあふれた文章であった。以来、何度か「日本古書通信」への寄稿を依頼したが、企画もの以外の原稿は貰えなかった。智之さんもメンバーだった反町茂雄氏主宰の文車の会の機関誌「ふぐるまブリティン」にもあまり寄稿されていないので、文章力はあってもその点はストイックだったのかもしれない。 現在、「日本の古本屋」の陰に隠れて目立たないが、神保町のオフィシャルサイト「BOOKTOWNじんぼう」の開設にも智之さんは関係していた。技術的なサポートをしてくれたのが東大情報研の高野明彦先生である。高野先生の開発された連想検索Webcat Plusは、書籍検索上画期的なもので、あふれる文字情報の海から、キーワードにそって関連する本や記事を拾い出してくれる。書名や著者名だけでなく、目次や内容紹介のデータもその網の目にかかってくる。高野先生とも親しい智之さんは、この機能を利用して新しい古書目録を作り始めた。タイトルは「おしゃべりカタログ」。取り上げる古書を読み、その面白さを紹介、その本の背景や関連事項まで解説に書き込んだ。その解説に含まれる言葉が、連想検索によってヒットしていくのだ。智之さんの解説は、古書価の高低にかかわらずその本の面白さを伝えていく。しかも対象は古典籍から遊女の手紙、大名の借金証文、ナチス文献、浅草オペラの楽譜などなど極めて広い。これらに取って付けたような説明文でなく、読ませるエッセイに仕立てている。これはかなり広範囲な読書と知識がなければできないことだ。最初に書いたように小宮山ガレージセールで智之さんが古本を漁っていたのはその為だろう。 私が中野好夫への興味からアラビアのロレンスとの繋がりで、サイードの『オリエンタリズム』を読もうとしたが歯が立たない。或る時智之さんに「サイードは難しくて」と話したら、「サイードは分かるでしょう」と一蹴され、これは並みの読書家ではないなと思ったことがある。 2011年の夏ころだろうか、智之さんが病気らしいという噂を耳にした。編集者とは因業な職業で、智之さんに連載をお願いするなら今だなと思ったのである。大江健三郎が師渡辺一夫を評した言葉の中に、人間は回復期にもっとも良い仕事を残すものだというのがあった。私はきっと引き受けてくれるに違いないと、思いついてすぐ古書センターのお店に伺い、「おしゃべりカタログ」に書いたものを本誌用に書き換えて連載して下さいとお願いするとその場で承諾してくれた。「一つだけ、樽見さんが面白くないと思ったら、遠慮なく伝えて。即やめるから、それが条件」と言われたことを覚えている。 連載は、2012年1月号から14年10月号まで32回続いた。一回目は「傾城の恋文」であった。横浜岩亀楼の遊女が旦那に送った懸想文である。原稿を頂いた時のメールがのこしてある。「一応五回分、お送りしておきます。懸想文は一回目用ですが、以下の順番は適宜で結構です。追ってもうすこしお送りします」とある。連載の一回目に遊女の手紙はふつう選ばない。今回読み直して、これは意図があったのだと気が付いた。遊女の手紙は流麗な崩し字である。なかなか読めないし、花街独特の作法、用語もある。 総合した知識がないと解説できない。しかも智之さんは今風に翻訳までしている。智之さん実は杉並のご自宅を一部劇場にし、ユニット演劇集団「ガザビ」を主宰、脚本を担当している。つかこうへい原作「熱海殺人事件―哀愁のトワエモア」、シェイクスピア原作「ベニスの商人」をアレンジした「さくらどき、鏡のよのなか」などの脚本を書いているようだ。このような経験と技術がなければ遊女の懸想文を今風には書き直せない。商品にはなりにくい物に価値を与えていくにはそれだけの下地が必要である。そのことを、それとなく示したかったのではないかと今にして思う。三回目の「榎本武揚の別れの手紙」は古書店主に求められる瞬時の判断力の話ということになる。いつもの東京古典会の市場の壁にポツンと掛けられていたもの。智之さんはその日付と、その書簡の三名の宛先に注目。勿論内容も読み切り、価値ありと判断した。唯の直観ではない。これも下地がなければ出来ない。 十五回目は「極道和尚、板にたつ」。演劇人でもあった智之さんならではの一篇。金星堂先駆芸術叢書『六人の登場人物』(ピランデルロ・大正13)の紹介だが、眼目はたまたま挟まっていたこの芝居の「非公開パンフレット」にある。演劇史では公演禁止とされたこの芝居が、実は三日間だけ「非公開」で上演されたことが分かった。面白いのは配役にある后東光が、極楽和尚今東光の誤植であると書いていることだ。この時のメールも残してある。私が「后東光よく気が付きましたね。『浅草十二階』といったか、今東光の青春自伝がありますが、それにも出てきますかね」と書いたら「今、手元にないのですが、たしか女の話題ばっかりで、あ、文学も少し。たしか芝居の話はなかったように記憶します」と返信があった。 連載は途中から病床からとなった。亡くなられて古書会館地下でお別れの会があった時、石神井書林さんがこの連載にふれて、「回を追うごとに文書が良くなっていくのに感動を覚えた」と語っていた。このお別れの会に頒布すべく、奥様千枝さんの支援を得て連載をまとめた『古本はこんなに面白い 「おしゃべりカタログ」番外編』を刊行した。千枝さんが巻末のあいさつに「本が好きで好きで、休みの日も自転車で本屋めぐりをしていた」と書かれている。思っていた通りである。 同世代の古本屋さんたちと話していると、「智ちゃんが生きていてくれたらな」と必ずのように出てくる。「日本古書通信」今年の2月号に前全古書連会長の河野高孝さんにお話を伺った。その中で「20年以上前「東京の古本屋」で中野書店の中野智之さんが、本部交換会の開催日組替えを提言されています。本心は交換会そのものの再編にあったことを、のちに当人から聞かされました。現会館が出来たときは、交換会再編の好機でもあったのですが」と語られている。本当に惜しい方を失くしてしまったと思う。(2014年12月没・60歳) |
|
Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |