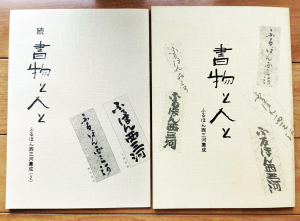懐かしき古書店主たちの談話 第9回 最終回日本古書通信社 樽見博 平成七年(一九九五)終戦五十年を記念し「日本古書通信」で「古本屋の戦後」を連載した。今回読み直して内容の貴重さも勿論だが、筆の立つ古書店主の多かったことに驚かされる。それぞれの積み重ねてきた経験に裏打ちされているからだろうと思う。以下のラインナップだった。 1月号 札幌・えぞ文庫・古川実 水戸のとらや書店さんは父上の話(白山の窪川書店で修業された)、高知のタンポポ書店さんは亡きご主人の話が中心である。宜野湾の緑林堂は屋号を変えて現在は榕樹書林さんである。私が人選したはずだが、お会いしたことがあるのは桃山書房、椿書房、尚古堂、マツノ書店、とらや書店、緑林堂さんだけである。天保堂苅部さんを推薦してくれたのは前回取り上げさせて頂いた石田友三さんであった。 東北や北陸、大阪や京都の古本屋さんを取り上げなかったのは何故か思い出せない。当時はまだ『全国古本屋地図』を毎年のように改訂増補していたから、各地の古書店さんとも深い交流があった。例えば「日本古書通信」目録欄の常連だった長野県諏訪市の文化書局の百瀬威さん、北九州の教養堂の田中正文さんなども、それぞれの土地での貴重な体験をお持ちだったろう。あるいは平成7年にはもう引退されていたのだろうか。 連載は戦後復興期における地方の古本屋の状況や変遷が記録されていて各編とも貴重であると共に面白い。この「全連ニュース」では無理だが、二か月後に送信される「日本の古本屋」メルマガではPDFデータを添付して読んで頂けるようにしたい。 私は古書業界しか知らないが、これほど同業同士の横の連携が密で、商品を融通し合う業界は他にないのではないかと思う。これは偏に古書という商品の性格と、古書市場の運営を業者が共同で直接運営しているからだろう。前記した『全国古本屋地図』の殆どが各地の古書店主によって書かれていることも(自店以外の古本屋を宣伝しているのだから)考えてみれば他の業界ではありえないことだ。 前回話題にした古書店主たちの「往信返信」や「古本屋の戦後」を連載した時代を思い出すと、所謂バブル経済以後ではあったが、古書業界はまだまだ華やかな好景気の中にあった。明治古典会七夕古書大入札会も東京古典会古典籍展観大入札会も豪華に開かれ、各地の古書店主たちがグループで多数来会していたし、首都圏の各デパート即売展にも各地の古書店の参加があり、北海道から九州まで業者同士の交流も盛んであった。現在も各地から参加は多いのだろうが、大挙して来会という感じではなさそうである。 前記した諏訪市・文化書局の百瀬威さんも頻繁に上京されており、事務所にも必ず立ち寄っていかれた。諏訪大社秋宮に隣接する和菓子の老舗新鶴本店の塩羊羹を私たち社員にも買ってきて下さった。もう七十代後半であったろうが体も大きく元気な方であった。諏訪の歌人島木赤彦の研究家で、『去りがてし森 赤彦への相聞歌川井静遺歌』『島木赤彦自筆による堀内卓歌集』『辛夷の花 柿の村から島木赤彦』などの出版もされていた。 その百瀬さんが、私の入社する6年前の昭和48年7月号に「訪書紀行 長野県の古本屋」を寄稿されている。「ももせ・たけし」と署名されている。 「筆者は信濃路の古本屋の生態或いは店相をどのように描くかに先立つて古本屋のおかれてある環境―教育文化の風土と伝統についてその片りんを紹介することが便利だと考えた」と冒頭に書かれている。 郷土や郷土誌への愛に溢れ、古本屋の存在価値がそこにあることに寸毫の迷いもない。改めて当時、文化書局が「日本古書通信」の目録欄にどんな古書を載せていたか見直してみた。前回取り上げた旭川の尚古堂さんの達筆すぎる原稿に触れたが、百瀬さんの字も同様だった。当時の私には分からなかったが、見事な品ぞろえである。集書には相当な苦労というか努力をされていたのだろう。本誌目録欄が喜ばれていたことに改めて納得させられた。 岡崎の桃山書房鳥山将平さんも、しっかりと西三河の地に根を下ろした古本屋さんであった。編集されていた『ふるほん西三河』の品の良さも、お店の佇まいも鳥山さんそのものであった。連載の2回目「忘れ得ぬ人々」で、やがて『ふるほん西三河』につながっていく豊橋の冬日書房、刈谷の西村書房との合同目録『古本あらかると』について書かれている。名古屋の市場で出会った三人。 「二人は吹き荒れたレッドパージの風をくらって本屋を始め、私はシンパ。心情において通ずるものがあったか、顔を合わせた時から太い絆で結ばれることになり、三河の三人ということでさんさん会がはじまったのである。昭和三十五年の安保騒動の時から学生運動のたけなわの頃、私の店も学生自治会の分室の趣を呈していたものだった。その頃の学生達は誰がどんな卒論を書いているのかも解っていて、資料探しに手を貸したことも懐かしい。その頃の卒業生たちは今も近くに来るときっと寄ってくれる。」 「昭和四十一年になって、さんさん会でまた目録をはじめようかということで「古本あらかると」を出し始めた。三年程の間に反戦平和、フランス文学とその周辺、雑誌特輯、編年戦後文学などのテーマ別に十三号まで発行した。うちでタイプ印刷を始めたのもこの頃で、はじめは目録を作ろうと思った訳だったが、障害者の働く場としてふくらんでいって、次第に母屋をとられる格好にもなってきてしまった。」 「昭和五十七年から組合の補助で「ふるほん西三河」を発行するようになった。有志の販売目録集の頭に三頁ばかりの小文を付けたのも、さんさん会の当時からの想いが実ったものである。季刊で休みなく五十号に達しようとしているが、全国からの暖かいご支援があって永続きをしているのである」とある。 『ふるほん西三河』は2004年の85号まで刊行され、目録欄を除いた記事欄が、1995年に50号まで、2004年に51号~85号の複製合本版が出されている。 合同目録の中でも『ふるほん西三河』は特に優れたものであった。鳥山さんに負うところ大であった筈である。「思い出す人々」の最後に次のようなことを書かれている。 「本を売って生業としている以上、本は売らねばならぬ。大体自分の好きな本を売っているので、心の片隅に、本を売りたくない本心がのぞいている。現実には客と話が弾み気が合えば、結局秘蔵の本を見せ手放すことが多い。客それぞれが持っている文庫をより充実するのが本屋の仕事であろうが、せつない業である。自分の文庫を持ちたいというのは烏滸がましい事なのだろう。このわがまゝを残すかぎり、所詮素人商人の域を離れることが出来ないのが解っていて止められない。」 正直な心からの吐露だと思う。こうした心持の古本屋に扱われる本は幸いである。 広島の椿書房藤井成一さんは終戦直後からのベテラン古書店主だが、「日本古書通信」に目録を掲載されるようになったのは晩年であった。教科書や資料類が専門だから仕入れに上京されることも多く、事務所によく立ち寄られた。文化書局の百瀬さんはいつも塩羊羹だったが、椿さんは広島の「川通り餅」をお土産に下さった。「川通り餅」は毛利元就の祖先師親に由来するお菓子とのことである。 藤井さんの「広島・私と古本屋」はまさに原爆投下後の終戦時から昭和30年頃までの激動の広島古書業界史と言えるもので、簡潔な見事な文章である。神戸の黒木書店さんとは当時からの盟友であったようだ。黒木さんは広島では最初、京橋筋で澄江堂書店として営業されていたが、千田町に移り黒木書店となった。広島原爆ドーム前を流れる川は元安川だが、澄江はその別名ではなく芥川龍之介に由来するのだろう。詩書文学書専門の黒木さんらしい店名である。 藤井さんの「広島・私と古本屋」では書いていないが、「黒木さんが神戸に移る時も、広島に残るようにすすめたのだがね……」と言っておられた。文章の最後には「尚、最後にこの度の大震災で大きな被害を被った黒木さんが災害に屈せず、本の整理や古書の買いに活躍されている由を承り、その不屈の精神に敬意を表し」ますと盟友を称えておられる。 昨年、栃木県川治温泉に行った時、龍王峡に立ち寄ると、日光教育委員会の案内看板に「龍王峡は昭和二十四年三月、大字藤原の斎藤茂吉氏の提案により伊の原より浜子に至る約五キロメートルの鬼怒川河川敷にハイキングコースが造成されたのを発端とし」と書いてあった。此の斎藤茂吉さんは今市の晩晴堂書店さんに違いないと思った。 晩晴堂さんは、「日本古書通信」の目録欄に数回掲載されたことがあったが、掲載後「売り上げが広告代に届きましたので、お支払いに来ました」と、事務所に顔を出された。如何にも好々爺といった風情であった。『全国古本屋地図』を出しているころ、日本の古本屋には小林秀雄さんもいたが、斎藤茂吉さんもいることを知りおかしかったが、晩晴堂さんは見るからに優しいお爺さんであった。それでも龍王峡の看板を読んであの斎藤茂吉さんに間違いないと思った。恐らく当地の文化的名士のお一人であったのだろう。 私は会うことはできなかったが、大阪の天牛新一郎さんや、懐かしい蒐文洞の尾上政太郎さんなど、土地の人気者、有名人の古書店主もかつては少なく無かった。 世の流れのスピードが速くなり、よく言えば平等になったともいえるが町場と郊外や農村の生活(外観ではなく)の差がなくなり平均化してしまった。その中で声の大きな者、宣伝力のある者だけが目立つようになってしまう。 古本屋に流れる時間と言われることがある、古本屋の店内や棚にはどこか世間離れした雰囲気があり、そこに入ると穏やかで豊かな贅沢な時間を過ごすことが出来た。今回は土地の匂いを満身にまとったような古書主を取り上げたが、古本屋の魅力は個性的な古書店主たちの醸し出すものであった。 時代が変われば、古本屋も変化していく。昔は良かった、昔気質の古書店主は魅力的だったと言っても詮無いことである。新しい魅力的な古書店主も少なくない。知識も豊富である。古本の需要が減る一方で、古書市場に流れてくる荷の量は増えている。自然と書物の一冊一冊の扱いがぞんざいになってくる。本をこよなく愛する者の商売であった古本屋が、ともすれば他の流通業と変わりなくなりつつある。古本屋も変わっていかねばならない。でも失ってはいけないものもあるのでないかと思う。 編集部のご厚意でながながと連載を続けてきたが、以上のような思いから、私の接することの出来た古書店主たちの思い出を書かせて頂いた。意とするところを汲んで頂き、お許し願えれば幸いである。(了) |
|
(「全古書連ニュース」2024年9月10日 第502号より転載) 日本古書通信社 |
|
Copyright (c) 2024 東京都古書籍商業協同組合 |