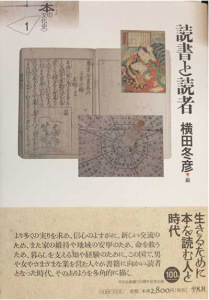『シリーズ本の文化史2 書籍の宇宙―広がりと体系』鈴木俊幸 |
| このシリーズは、「書物・出版と社会変容」研究会を母体としている。2015年7月現在、すでに98回続いているこの研究会に参集してきた面々による蓄積、またそこから広がる人脈に基づいて発想された企画で、今のところ6巻までの原稿が出そろい(つつあり)、順次刊行の予定、本書はその第2巻である。内容は以下のとおり。 鈴木俊幸「書籍の宇宙」(総論)、堀川貴司「歴史と漢籍―輸入、書写、和刻―」、高木浩明「古活字版の世界―近世初期の書籍―」、岩坪充雄,「「書」の手本の本―法帖研究の意義と方法―」、佐藤貴裕「辞書から近世をみるために―節用集を中心に―」、柏崎順子「江戸版からみる一七世紀日本」、山本英二「領内出版物―治世と書籍―」、高橋明彦「何を藩版として認めるのか―蔵版の意味するもの―」、鈴木俊幸「草双紙論」、磯部敦「書籍の近代―東京稗史出版社の明治一五年―」。 いずれも気鋭の専家の執筆(私のものも混ざっているが、本人もちょっとはそのつもりでいたりする)。執筆者に期待したことは、それぞれのテーマの書籍について、その面白さを、時代・社会との関わりを意識してわかりやすく語ってほしいということであった。これは、書籍が新たな歴史を紡ぎ出す有力な資料となりうること、また、書籍が位置していた社会・時代を考え、その書籍の当時に占めていた位置を割り出せば、その書籍の面白さと価値とを十分引き出せるということを示したかったからである。その意図が十分実現されている好もしい一書ができあがったと自画自賛している。もとより、この9本半で広大無辺の「書籍の宇宙」を覆うことができるはずもないが、それぞれの宇宙系の面白さから、宇宙全体の豊饒を十分想像していただけるであろうと思っている。 新しいものはどんどん古くなる。すでに古いものは、それ以上古びることはなく、価値を見いだされた過去のものは、その価値を減ずることはない。見いだされた新たな価値によって、新鮮な輝きを放ち始める古書もある。古書店、また古書展を覗いてみるべし。古書を手にとってみるべし。触ってみることは大事である。江戸時代の古書とても、容易に手に触れることができるし、ほんのポケットマネーで自分の蔵書にすることもできるくらいに、まだまだ古書市場にあふれている。それを手に取ったところから豊穣なる宇宙への展望が大いに開けたりするのである。本書は、星座早見盤よろしくその展望のためのよいガイドになるであろう。まずはこれを頼りに、お気に入りの星座や天体にたどりついていただけたら幸いである。 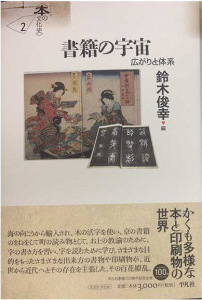
『書籍の宇宙 広がりと体系』鈴木俊幸 編 『読者と読者』横田冬彦 編 |
|
Copyright (c) 2015 東京都古書籍商業協同組合 |