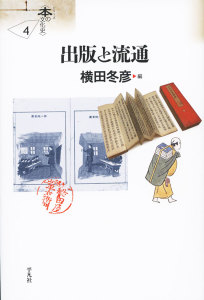『本の文化史 1巻 読者と読書』『4巻 出版と流通』横田冬彦 |
| この「本の文化史」シリーズ、第一期分6巻のうち、私は1巻と4巻の編集を担当した。先月出たのは4巻だが、1巻目も合せて書かせていただく。2巻・3巻については、鈴木俊幸さん・若尾政希さんの文章(本誌186・193号)を参照してほしい。 出版社側の編集担当は平凡社の保科孝夫さんである。保科さんの書く本の帯は簡にして要を得、編者の気持ちをとてもうまく表している。 1巻『読者と読書』――生きるために本を読む時代 /より多くの実りを求め、信のよすがに、新しい交流のため、また家の維持や地域の安寧のため、命を救うため、暮らしを支える知や経験のために、この国で、男や女やさまざまな業を営む人びとが、書籍に向かい読者となった時代、そのありようを多角的に描く。 4巻『出版と流通』――だれが、なぜ、どんな仕組みで、本をつくり、弘めるのか/利を求めて、教えを正し弘めるために、組織と支配を固めるために、国民を創り出す教育をめざして、本屋が、教団が、本所が、学派が、国家が、刷るばかりでなく写して、売るだけでなく貸して、本を弘める。そこにどんな仕組みが、どんな変化が、どんな規模が働いているか。近世から近代へ、書物の動態。 二つの帯に共通するキーワードは「~のために」である。何のために読むのか、何のために本を作るのか。誰が何をという問いにも、様々な身分や職業の人びと、様々なレベルの集団や組織、様々な分野の書物と目配りはしているが、核心的な問いは、なぜ・何のためにという人びとの思いである。それは、本があまり売れなくなったといわれる現代において、なぜ読むのか、なぜ本なのかという問いが、もっとも切実だからである。 情報や知識を得るためであれば、インターネットの方が手っ取り早い。しかし、なぜそうなのかという問いには、割り切れば一言で済むとしても、実際は複雑で丁寧に語る必要のあることが多い。複雑な内容は、読む側にさまざまな理解や疑問をよびおこし、読者の頭のなかで作者との対話がはじまる。つまり、問いをたてながら、考えながら読むことになる。 日本の近世=江戸時代は、貴族階級や僧侶だけでなく、ふつうの人びとが本を読み始めた時代である。ものごとを、そして時代や社会を、少し複雑に「考える」ようになったのである。そこにもいくつかの波があったが、歴史を顧みれば、そうした波を経ることで、ふつうの人びとの考える力が育くまれてきたことがわかる。 昨今イギリスでもアメリカでも、ものごとを単純に割り切って、扇動的に説明するやり方が政治を左右しているように見える。しかし、それでよかったのかという問いもまた立てられている。そこに本をめぐる、次の波への期待もある。この時代を少し複雑なこととして自分の頭で考える「ために」、本の役割が求められている。 1巻――総論・読者と読書(横田)、1・江戸時代の公家と読書(佐竹朋子)、2・武家役人と狂歌サークル(高橋章則)、3・村役人と編纂物(工藤航平)、4・在村医の形成と蔵書(山中浩之)、5・農書と農民(横田)、6・仏書と僧侶・信徒(引野亨輔)、7・近世後期女性の読書と蔵書について(青木美智男)、8・地域イメージの定着と日用教科書(鍛冶宏介)、9・明治期家相見の活動と家相書(宮内貴久) 4巻――総論・出版と流通(横田)、1・三都の本屋仲間(藤實久美子)、2・地方城下町の本屋(陶山高明)、3・「暦占書」の出版と流通(梅田千尋)、4・仏書・経典の出版と教団(万波寿子)、5・平田国学と書物・出版(吉田麻子)、6・地図・絵図の出版と政治文化の変容(杉本史子)、7・明治初期の学校と教科書出版(稲岡勝)、8・近代の貸本屋(浅岡邦雄)、9・近世出版文化の統計学的研究(松田泰代)
|
|
Copyright (c) 2016 東京都古書籍商業協同組合 |