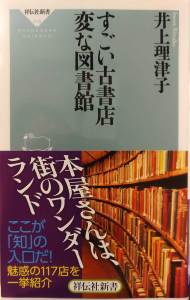『すごい古書店 変な図書館』祥伝社新書井上理津子 |
|
「洋服のショップでは『どんなものをお探しですか』と声がかかるし、寿司屋さんでは『今日はマダイ、いいのが入ってますよ』と案内される。本屋さんも、そんなふうだったら面白いのにね」 飲み屋で、日刊ゲンダイの読書面デスクからそんな話が出たのがそもそものきっかけである。町の本屋さんを訪ね、連載したミニルポが、晴れて一冊になった。 この本に登場するのは、東京と近郊の古書店85軒(と専門図書館32軒)。 ・2代目、3代目が店主の老舗古書店 ・「就職しないで生きるには」的に始め、20~40年の古書店 ・近年開業したニューウェーブ的な古書店 おおよそこの3種類だが、図らずも、店主の個性がモノを言う、ひとクセもふたクセもある古書店ばかりだ。 明治40年創業の秦川堂書店(神保町)には、都道府県別の古地図がずらり。3代目店主が、「“使える古地図”の量はウチがたぶん日本一」とおっしゃり、「入門者におすすめ」と、全国の大正3年の詳細地図(復刻版、1000円)を出してくれた。「我が家のルーツ探し」に求める人が多いそうだ。 九曜書房(武蔵小山)は、店頭に安価な雑本が並ぶ一見普通の店だが、の帳場付近に、ひとかどの写真集がたんまりと潜んでいた。石元康博の『シカゴシカゴ』などレアものも。店主は、美術館にあってもおかしくないような写真集の数々を目の前で開き、聞けば、縷縷解説もしてくれた。 去年開店した弥生坂緑の本棚(根津)の店主は、大手花屋からの脱サラ。「植物と古本、どちらも売ります」と、店内には観葉植物と本が共存し、多肉植物グラハラリーフを食べられるカフェも併設している。 と、ちょっと特異な品揃えの店のことをここに書いたが、絶版になった文庫を揃えた大河堂書店(経堂)、部落や沖縄、在日などが専門の水平書館(神保町)、4階建のビルまるごと古書店の高原書店(町田)など、がっつりと読む本が詰まった店も。パソコン検索システムなどないのに、輪郭を伝えれば、数多ある本の中から「これのことですね」とさっと1冊を取り出してくれた店主も少なくなく、私は「さすが」とうなりっぱなしだった。 そんなこんなが、1軒ずつ見開きに収まり(自分で言うのもなんですが)読みやすい本に仕上がった。この本を手に、掲載店にぜひ足を運んでほしい。 本稿を書くにあたって、改めてこの本を通読して思ったのは、店主とお客が本屋さんをつくり、本屋さんが町をつくってきたということ。リアル本屋さんは、町の厚みのバロメーターだと、ひしひしと感じています。
|
|
Copyright (c) 2017 東京都古書籍商業協同組合 |