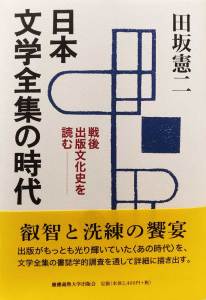『日本文学全集の時代 ー戦後出版文化史を読む』田坂憲二 |
|
本書は、1950年代から70年代まで、戦後の出版界で大きな役割を果たした文学全集の類を、代表的な10の出版社を中心に分析したものである。世界文学全集については、特定の出版社を切り口にしたものであるが、すでに『文学全集の黄金時代 ー河出書房の1960年代』(和泉書院、2005年)で明らかにしたので、今回は、日本文学全集について、主要な出版社を網羅して、体系的に考察したものである。記述の方法は、個別の出版社ごとの通時的記述を骨格とした。この方法を採ることによって、出版社ごとの伝統や特徴、出版戦略を浮き彫りにした。これに適宜、他社の全集を共時的・同時代的に見ることにより、出版界全体の動きを視野に納めることができたのではないかと思う。 執筆に当たって留意したことは、同じ文学全集というジャンルを取り上げるのだから、出版社ごとの記述が重複しないように、異なった角度から論じることである。筑摩書房の章では文学全集を通史的に概観し、角川書店の章では一つの叢書がどのように成長していくのかを跡づけ、新潮社の章ではベストセラーがどのように改編され生き延びていくかを析出し、講談社の章では大衆文学の全集の歴史に目配りをし、河出書房の章では古典文学と近代文学とのコラボレーションの問題に着目し、中央公論社と文藝春秋の章では挿絵や「文学館」という独自の体系を論じた。旺文社と学習研究社の章では好敵手のこの二つの出版社(筆者に村松梢風のような筆力があれば名勝負物語を書きたいところ)では文学全集だけではなく学年別雑誌の消長も併せて記述した。したがってそれぞれの章は個別に楽しむことができ、同時に文学全集の断面から切り取った各出版社の社史ともなっている。個別的記述の独立性が高まれば、一方で全体を統一する力が弱まるから、各所で同時代の他社の状況を意識的に加えるとともに、巻末に各社の文学全集を一覧できる年表を附載した。 本書の基礎資料を集めるに際しては、とにかく古本屋さんのお世話になった。一通りの全集を函や帯や月報が附いた形のまま蒐集できたのはそのお蔭であり、無数にある異装版や後刷りをほとんど100円で求めることもできた。内容見本の類に至っては、もうこれは古本屋さんや古書展を抜きにしては蒐集できなかったものである。あとがきに古本屋さんの名前を列挙してお礼を申し上げたかったほどであるが、あまりに膨大になるので断念した次第である。この場を借りて御礼申し上げる。 最後にクイズを。次のキー・ワードと関係の深い出版社を組み合わせなさい。王道、拡大、教養、現代、差異、新進、先駆、定番。筑摩書房、角川書店、新潮社、講談社、集英社、中央公論社と文藝春秋、河出書房、学習研究社と旺文社。正解は本屋さんで!
|
|
Copyright (c) 2018 東京都古書籍商業協同組合 |