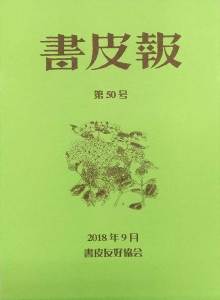「書皮報50号」中西晴代 |
| 「書皮報」は、<本が好き、本屋が好き、本屋のカバーも好き>の書皮友好協会の会報です。1983年の「本の雑誌」(本の雑誌社)に、「本屋のカバーを集めています。交換しませんか」という投稿が載って、それを見たカバーにこだわる人、集めている人、集めていないけど何となく面白そう、という人たちが集まって、本屋のカバーを『書皮』と名付けて、書皮友好協会ができた。日本の書店では、本を買うと無料でカバーを掛けてくれる。本はどこで買っても、同じ値段で同じ商品だ。それなら、気に入ったカバーをかけてくれる書店で本を買いたい。互いの連絡手段が、手紙か固定電話の頃のこと。近況や、入手した書皮、訪ねた書店、旅の報告など、手書きで書いた原稿をまとめて会報にした。 会員同士の情報交換で、日本各地の書店に様々な書皮があることを知って、素晴らしい書皮を讃えようということになった。そして毎年1回、会の中で人気投票をして、「書皮大賞、地方賞、特別賞」を決めて、賞状を持って書店を訪ねて、ご店主から聞いた書皮についての話を会報で紹介する、を30回続けた。会員たちの関心の的は、読んだ本より、新しくできた書店のことだ。どんな雰囲気と品揃えか、どんな書皮を使っているか?で、書皮は会員たちが集まる口実かもしれない。 会ができて35年という区切りの今年、会報は50号になった。さらに今年は13年ぶりに2冊目の「カバー、おかけしますか?2」(出版ニュース社)が出版されて、6月に東京古書会館で2度めのカバー展を開催するという、めでたい出来事が重なって、50号はそれらの報告でいつもより厚い104ページになった。 「カバー、おかけしますか?2」では、私のコレクションの中から、絵柄でジャンル分けした248枚の書皮を紹介。東京古書会館 2階でのカバー展(6月20日~23日)では、本に入らなかった<食べ物/元号/コンビニ/作家の似顔絵>などを加えた、32のジャンルに分けて書皮を展示して、韓国やアメリカ、中国で入手した書皮も入れた。順路の最初は、会場がある神保町に敬意を表して、<神保町の新刊書店/古書店>から。ガラスケースのほかに、会場の壁2面に書皮を貼りに貼って・・・その数567枚。いくつかのジャンルが部屋の中に入りきらなくて、外に置いてあった移動式パーティションへと続いた。 絵画作品展さながらの会場は、さっと見て通り過ぎてしまいがちだけれど、それではもったいない。以前よく見かけた新潮社の横向きひょうたん柄はマチスの作品だとか、絵の作者は誰もが知る著名人(伊丹十三、水木しげる、手塚治虫・・・)だとか、単行本用の大判書皮には絵の隅にオオグソクムシが増えたとか・・・蒐めているから知っていることがある。そんな”実は・・・”を紹介するギャラリートークを、会期中に5回行った。 13年前の東京古書会館でのカバー展との違いは、スマホ片手の若い世代が、気に入った書皮を撮影して、その場でSNSに上げていたことだ。書店のレジでカバーいりませんと言う人が多い一方で、日本だけにある書店カバーの文化が、若い世代にカワイイものとして受け継がれていくとしたら、喜ばしいことだ。 4日間だけ存在した、部屋の中すべてが「カバー、おかけしますか?」の書店カバーという、夢のような空間だった。会場で書いていただいたアンケート用紙には、「書店カバーにこんなに種類があるとは! 絶景だ。自分の思い出と重なる。本を日焼けや汚れから守ってくれる大切なもの。図書館のカバーがあるとは」等々。見慣れすぎて存在感の薄い書店カバーも、500枚以上並べばオーラを放つというもので、何人ものお客さんから「圧倒された」の声を聞いた。わざわざ足を運んでくださった皆さんに、楽しく驚いていただけたなら幸いだ。 「書皮報」50号は、そんなこんなの4日間のことを、思い出せる限り書いた記録集でもある。
|
|
Copyright (c) 2018 東京都古書籍商業協同組合 |