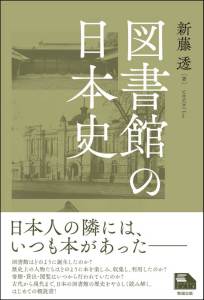『図書館の日本史』新藤 透(東北福祉大学) |
| 古代から近現代までの日本史を単独で執筆できる歴史家は数少ない、というか現代ではいない。戦後、日本史学は社会経済史や民衆史で発展してきた。研究が進展するにつれてさまざまな観点から論じられるようになり、現在では多種多様な視点から研究されるようになってきた。環境問題やLGBTなどのきわめて「現代的」な論点でも日本史は研究されているのだ。 つまり、とても一人ではすべての観点に目配りをして通史を叙述することが困難になっている。日本史の通史概説書は今日でも出版されているが、各分野の執筆者数十人を総動員して著されているのが一般的だ。しかしそのような「概説書」であると、却って論点が散漫になってしまうので、一冊の書物として通読した場合歴史を学び始めた初学者には難解に映ってしまうのである。 それに比べて戦前の「国史学者」は、通史を単独で書けた。政治史を中心とし、史実を時系列で並べたオーソドックスな体裁のものが多いが、事実関係に拘って古代から近現代まで通して書いてあるので通読した場合スッと頭に入ってくる。観点もひとつに絞っているので、初学者には理解しやすいのだ。 それを専攻している図書館情報学の一領域である「日本図書館文化史」で出来ないのか――。無謀にもそう思ってしまい、ひといきに書き上げたのが本書『図書館の日本史』である。 日本図書館文化史の通史は、司書課程科目「図書・図書館史」の教科書として刊行されているものを除けば、そう多くはない。しかも戦時中に刊行された小野則秋『日本文庫史研究』上下巻を除けば、戦後出版された図書館史の本は近代史の記述が多く、前近代においては図書寮や金沢文庫、足利学校、紅葉山文庫などの発達の経緯が書かれているものばかりであった。これを「文庫史観」と筆者は勝手に名づけているが、あまり興味をそそられるような内容ではないのである。 文庫を中心に論じるにしても、単純にそれだけ切り取って設立と衰退の経緯を述べてもさほど面白くはない。そこに携わった人間の情熱や思惑、文庫を取り巻く政治情勢や時代性など、周辺情報にまでふれなければ「歴史」とはならないと私は考える。 例えば足利学校の附属文庫にしても、史料上の制約もあり詳細は不明な箇所も多々あるとはいえ、さまざまな「ドラマ」があった。関白豊臣秀次が奥州の九戸政実を討伐した帰途に古河に立ち寄り、挨拶に出向いていた足利学校の校長を拉致しさらに蔵書のほとんどを秀次の管理下においた事件などは、日本史学では有名な事件であるが図書館史の本で取り上げたことはなかったと思われる。 また江戸時代後期に各地の農村で見られた「蔵書の家」という活動は、庄屋の個人蔵書を村人に一般開放していたもので、書籍の貸出だけではなく読書会や講演会などの「イベント」も行っていた。これらは「〇〇文庫」という体裁ではなく、あくまで表面上は庄屋の私的活動にしか見られなかったので、小川徹氏の著作を除いては図書館史として取り上げられなかった事例である。 従来の図書館史の本は、図書館業界関係者を対象としたものが多く、一般向けの本はなかったと思われる。図書館を頻繁に利用している方は多い。普段利用している図書館がどのような歴史をたどってきたのか――。それを知ることで図書館自体に関する興味が高まり、もっと図書館が好きになって頂ければ著者としては本望である。
|
|
Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |