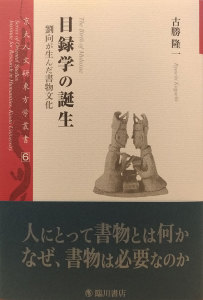『目録学の誕生―劉向が生んだ書物文化』古勝隆一 |
| 中国の伝統学術では書物が重視されるが、主に分類の面からそれら書物を研究するのが目録学である。「目録の学は、学中第一の緊要の事」(王鳴盛、18世紀の中国の古典学者)とまで言われ、近代的な中国学においても基礎の学として強調されていて、日本の大学で中国古典を学ぶ学生は、おそらく耳にタコができるほどその重みだけは聞かされるはずだ。十分身につくまで学び続けるかどうかは、人によるとしても。 しかし、この目録学、一般の読者にはやや馴染みが薄いのではないか。倉石武四郎氏『目録学』、井波陵一氏『知の座標』といった、十分な内容の手引きがすでにあるが、どうもそれほど広くは読まれていないようで、ビブリオフィルの諸氏も、目録学固有の理論やその歴史にまで精通しているとは限るまい。 私が勤務する京都大学人文科学研究所で、所員が一人一冊、東方学の一般書を執筆して叢書にしようと計画を立てたのが数年前のことで、お鉢が回ってきて、目録学のことを書くと決めたのだが、いまさら概説を書いても仕方ないという気もして、あれこれ考えた末、目録学の礎を築いたとされる前漢時代の人、劉向(りゅうきょう)に焦点を当てることにした。 劉向は、中国の書物史上、きわめて重要な人で、その人物と学問を日本の読書界に紹介しようではないか、というわけである。劉向は、漢の皇族の一員として生まれ、衰退してゆく前漢王朝を何とか立て直そうとした。国政の中枢に近い官僚であり、かつ経書に通じた大学者であった。重要な人物であるにもかかわらず、日本語で読めるこの人物の伝記はまだなかったから、なるべく詳しく書いたつもりである。 しかし、劉向の人物紹介だけではつまらない。伝えたいことの核心は、中国の書物史にどれほど大きなインパクトを劉向が与えたのか、という点であった。彼は皇帝の命令を受けて、同僚たちとともに、皇室図書館の全蔵書を系統的に整理し、すべての書の定本を作り、皇帝に向けて解題を書き、目録を作ったのであるが、この一大事業が後世の書物の歴史に大きな影響を与え、「目録学」と称される独特な学問分野の基礎とされた。その意味で、劉向は「目録学の祖」なのである。本書では、その事業の詳細と意義に関してある程度の紙幅を割いた。 中国の書物史は、その後さらに発展を遂げ、ついには四庫全書という大叢書を生み出したが、その基礎は劉向の「目録学」にある。そして、私の見るところ、この目録学は、歴史学やその他の方法論には回収も還元もできない、独自の視点と思想を持っている。その礎を置いたのが他ならぬ劉向、というわけである。本書を手にとっていただき、この目録学の世界に身をゆだねていただければ、というのが、著者の願望なのである。 なお、私は「学退筆談」と題するブログ記事を数年前から書いており、目録学を含む中国古典の話題を様々提供している。別に「オープン・サイエンス」を気取るわけではないが、学問的な興味を新鮮なうちに、考えを記事にして公開してきた。本書とあわせ、本を愛する多くの方に読んでいただきたい。
学退筆談(中国古典に親しむ) https://xuetui.wordpress.com/ |
|
Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |