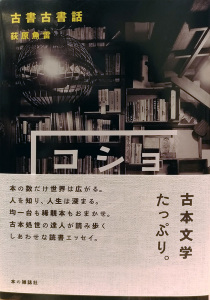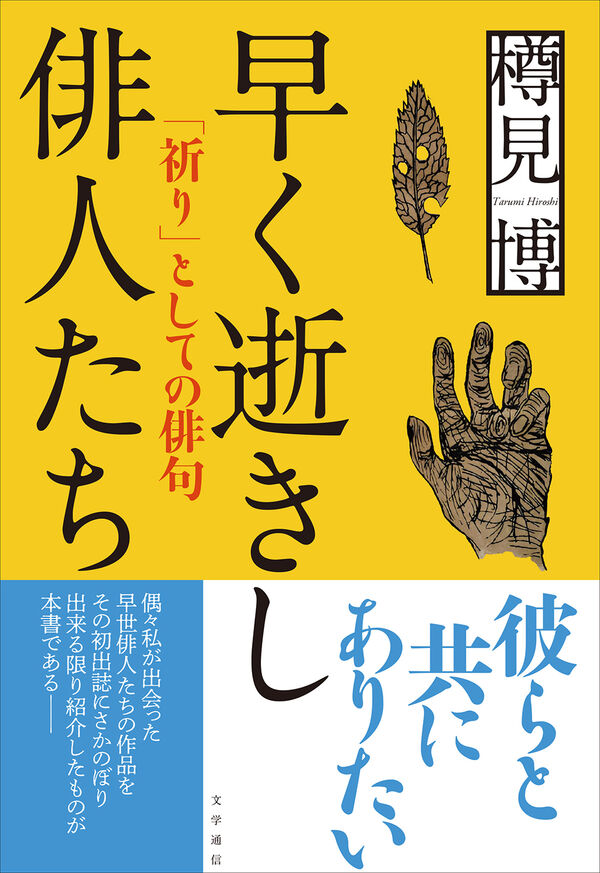古書古書話荻原魚雷 |
| 『小説すばる』二〇〇八年一月号から二〇一八年三月号まで十年ちょっと「古書古書話」という見開き二頁のエッセイを連載していた。十年ちょっと分なので、四百六十頁超??わたしがこれまで出した本の中ではいちばん分厚いです。ただし一篇一篇は短い文章なのでパラパラ読むには適しているのではないでしょうか。 横井庄一、平野威馬雄、辻潤、トキワ荘、野球、将棋、音楽、予言の本、家事の本、実用書、日記。登場する本がバラバラなのは、そのときどきの自分の興味、関心に抗わなかった結果である。 一九八九年の春、十九歳で上京。その年の六月からライターの仕事をはじめた。その後、大学を中退し、定職につくことなく、四十九歳まで、平日の昼間に古本屋をまわり本を読んで原稿を書いて酒を飲んで寝て……という日々を送ってきた。 「趣味を仕事にする」のが夢だった。「趣味が仕事になると楽しくなくなる」という意見はたくさん聞いた。その意見に半信半疑だった。「古書古書話」の連載中はずっと楽しかった(今も『小説すばる』で「自伝の事典」という連載を続けている)。 JR中央線沿線の高円寺に暮らし、三十年ちかく西部古書会館にも通っている。古書会館に並ぶ本の雑多さは、まちがいなくわたしの思考にも反映されている。 『古書古書話』は中央線の「古本屋濃度」の高い「古本本」といえるだろう。「古本屋通いの楽しみは、単に目当ての本を早く安く見つけることではない。 自分の知らないおもしろそうな本を探すこと。本そのものが醸し出している雰囲気や時代性を感じとること」 そんなことも書いた。わたしは本を探す時間が好きだ。本を読むことよりも好きかもしれない。本そのものについて調べるのも好きだ。 本の内容はどうでもいいとはいわないが、どんな本でも作者の横のつながり、縦のつながり、その本の刊行時の時代背景などを探っているうちに、いろんなことが見えてくる。点と点がいつの間にか知らないうちに線になるように関係ないとおもっていた本と本がつながっていく。 『古書古書話』の中には、漫画の中に出てくる架空の古本について調べた回がある。藤子不二雄の『まんが道』で主人公のふたりが神保町ではじめて買った古本(のモデル)を探したのだ(「ヒマラヤ謎の雪男」の回)。 寄り道と脱線も古本趣味の醍醐味である。行き当たりばったりに読み耽ってきた本について書いたエッセイ集だが、古書の世界の渾沌とした雰囲気は味わえる本になっているのではないかとおもう。 荻原 魚雷(おぎはら ぎょらい)
|
|
Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |