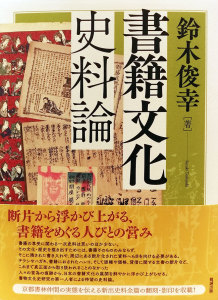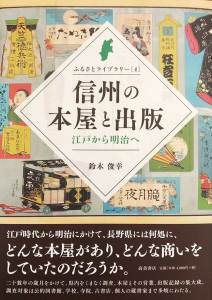『書籍文化史料論』鈴木俊幸 |
| 旧著『書籍流通史料論 序説』(2012年、勉誠出版)は、書籍流通に関わる論考に絞ってまとめたものであるが、このたび上梓の『書籍文化史料論』は、流通だけではなく、江戸時代から明治の半ばまでの書籍文化史全体に及んで、これまで書きためた、また書き下ろしの史料がらみの論考を収めた。勉誠出版の雑誌『書物学』に15回連載した「書籍文化史料片々」も併せて収めた。いずれも、書籍の文化の歴史の、書籍そのものだけではなかなか捉えられないさまざまな様相を、書籍に関わる、また関わりそうな史料を掘り出しながらあぶり出そうとしたものである。といえば、いささかかっこよく聞こえるが、どんな史料があってどう使えるのか、何が史料となりうるか、手探りしながら試みたものたちである。あぶり出せたものは、小さな局面、小さな状況に過ぎないかもしれないが、そこそこ具体的で生々しいはずである。 出来上がった本をパラパラと繰って図版を眺めてみると、これとこれはG書店で見付けたもの、この店は年に一回は当たりがあるなとか、これはO書房に頼んで落札してもらったものだとか、これはS書店の目録から注文したもの、間に合ってよかったとか、これはT書店から他とまとめて買い入れたものだけど、まだ料理できていないものも残っているなとか、N書房の店頭ワゴンも油断なく毎週チェックすべきだなとか、ハンコ目当てに東京古書会館ではなんでもかんでも買いあさったな、とかとか、これまでの渉猟のさまざまが思い出されて懐かしい。古書会館の和本の山の中に見付けたものを、家に帰ってじっくり眺めているうちに、ひょっとしてツレがまだ山の中に混ざってはいなかっただろうかと気になって翌日早々また古書会館に出向いて見付けたものもある。それは30年ほど前のことで、ようやくこの度日の目を見たわけである。機が熟すのに時間がかかったというか、機が熟したことにしちゃう踏ん切りができたというか。 昨年10月に松本の高美書店から出版した『信州の本屋と出版―江戸から明治へ』も、これまた30年近く心掛けてきた信濃出来の書籍・摺物の網羅的な収集が基礎になっている。質はともかく点数については、長野県立図書館や信州大学図書館所蔵のものを今では優に越えているであろう。ヤフオクや長野県内で得たものも多いが、これも神保町通いで集めたものが圧倒的に多くを占めているのであった。そんなこんな、私がこれまで続けてきた書籍文化史の研究(らしきもの)は、古書店・古書展とともにあった。これなくしては、ありえなかった。したがって、両書ともそれなりにお金をかけた本ではある。 といっても、1000円以内で入手のものがかなりの割合を占めている。これだけの金額で1世紀以上前のものがたくさん手に入るということは、それだけ豊富な蓄積を誇れる厚みのある文化であった証拠である。そして、誰でも小遣い銭で始められる研究であるということでもある。また、無駄歩きを含めて、多大の時間を掛けた本でもある。しかし、その時間とは、煩瑣な日常業務から切り離されて気ままにうろうろできる至福の時間であった。現在も、新たな研究に歩を進めるための史料獲得とモチベーション維持のために古書店歩きは欠かせないし、今後も、金曜日の神保町通いは私にとって大きな楽しみであり続けるはずである。 『書籍文化史料論』鈴木俊幸 著
|
|
Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |