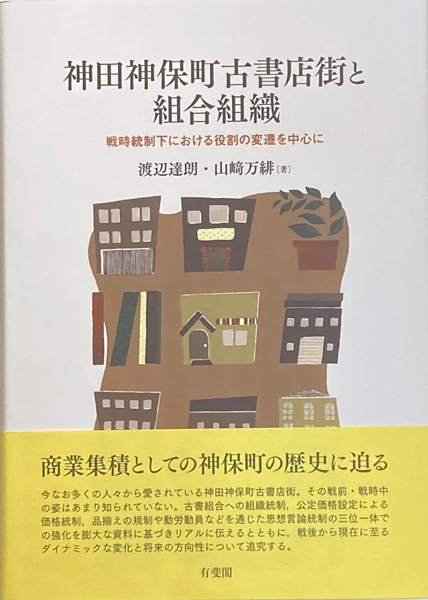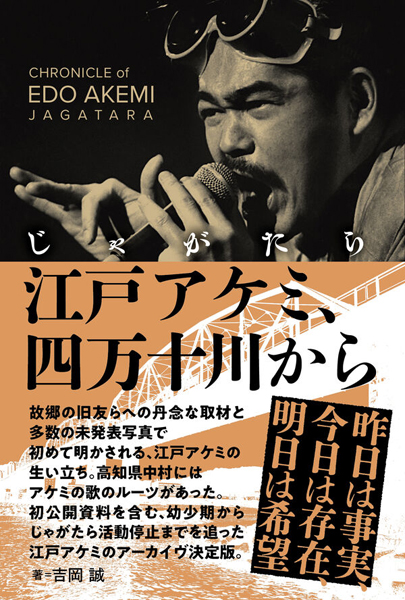古書市場が私の大学だった青木正美 |
| 四月で八十六歳、二十(はたち)で始めた古本屋も六十五年になる。「よく生きにけり」だ。 かたわら『古本屋五十年』他の自叙伝、調べた限りの明治以後の業界史、個性ある先輩たちの伝記、日記関連本など四十冊余りの本を書いた。今度の『古書市場が大学だった』では、生涯を通じての私の思いを、末尾に書下しているが私の本音である。定時制高校の二年すら終えていないのを、これらの本まで書かせてくれたのが古書市場→特に”明治古典会”だったからだ。そこは例えれば、あの弘文荘・反町茂雄校長の許、文学堂内藤勇、木内書店木内民夫、不思議な先輩、杉浦台紀教授連のいる古書の実践大学だった。 今回私が「日本古書通信」に三十数年間の連載分から八十四篇をまとめたものだが、右の”学校”のことは度々出てくる筈だ。ともあれ本は漱石、藤村、龍之介への思いや古本屋ならではのエピソードから始まる。特に「小学校さえ出ていない」と自称した窪川いね子(のちの佐多稲子)、室生犀星、小山清など学歴などものともせず独自の文学を極めた人達には、いつか自分を重ねてしまっていたかも知れない。 また、昭和三十四年創刊(学燈社)の「みどり」は”作家訪問欄”に注目、「石原慎太郎と湘南高校」「古本屋になりたかった開高健」「二十三歳の大江健三郎」を書いた。この時点での高校の旧友、本人の生の声を若い記者が取材文章にしたもので、のち三人が大成しているだけに出色の出来上りだった。 そしてもっとも読んで頂きたいのは、八十四篇中の(60)「古山高麗雄氏と話したこと」(78)「つげ義春さんと会う」の二篇だ。あの太平洋戦争下、もう伝説となった文学青年のグループに「悪い仲間」があった。当時の世相からは、不良青年たちとも見えた彼等の中から戦後安岡章太郎と古山という二人の芥川賞作家が生まれてしまう。中には戦没者もいた彼らだが、縁あって私はその何人かと知り合い取材、『「悪い仲間」考』(平19/古通)を出す。文章(60)は、古山氏の亡くなる一か月前に氏と一時間余り電話で語り合った記録。 一方、文章(78)の場合は平成十二年、私が調布市のつげ氏が指定された駅前喫茶店で、延々三時間対話した日の日記を、”訪問記”として二回にわたって載せたものだ。つげ氏、「何しろ、立石は出ちゃってから行ってないんです。いい思い出は全くない。子供の頃、駅の改札口でキャンデー売りとかね。あれが一番辛かった。でもよくあんなこと駅が許してくれてましたね。・・・・ええ、母が死ぬまで青戸で暮らしてたんで、去年まで京成線に乗ってました。堀切を通過中はここに青木さんがいるんだなんて・・・でも立石へはねえ」 私は、最後にお聞きした。「今目の前にしているつげさんと、熱狂的なファンに支えられた”つげ義春”という巨人とはものすごく乖離していると思うんですが?」 氏は答えている。 「私は本来、マンガ家とか画家とか思われたくないんです。好きな画家も、強いて言えばレオナルド・ダビンチ、もしくはそれ以前の名もない絵の職人さんなんです。それは手塚治虫さんくらいの天才なら、ああいう風に扱われても仕方ないですけど、赤塚不二夫さんみたいにテレビで顔を売っているのはね? あれでは電車も乗れません・・・」 最後、思わずつげさんとの出合いを長々と写してしまったように、面白いことは受け合いです。 どうか読んでみて下さい。 『古書市場が私の大学だった―古本屋控え帳自選集』青木正美 著 |
|
Copyright (c) 2019 東京都古書籍商業協同組合 |


本屋の周辺.jpg)