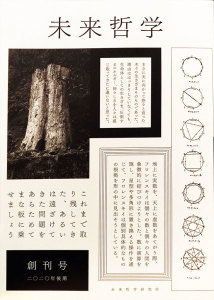『未来哲学』の創刊末木文美士 |
| この度、未来哲学研究所の機関誌として『未来哲学』が創刊の運びとなった。未来哲学研究所は、現代という困難な時代を超えて、未来にどのような希望を紡ぐことができるか、という切実な課題へ向けて、新しい哲学の創造を志す研究者が集まり、2019年に創設された。所長の末木文美士、副所長の山内志朗・中島隆博を始め、従来の西洋近代中心の枠にとらわれず、古代・中世、そして東洋・日本に及ぶ広い領域の哲学・思想の研究者によって、異質の思考がぶつかり合い、火花を散らしながら、次の世代につながるものが生まれてくる、そのようなエネルギーに満ちた場の形成を目指している。特定のオフィスを持たず、ゲリラ的、流動的であろうとする。事務局長のぷねうま舎の中川和夫氏が取りまとめ役に当たり、カクイチ研究所の後援を得ている。
ところが、本格的な活動にかかろうとした矢先に、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって出鼻をくじかれた。しかし、この危機的な事態こそ、むしろ新しい哲学の確立を一層強く要請するものである。2020年8月にオンラインで行われた創設記念シンポジウム「未来哲学とは何か」では、まさしくその船出に相応しい熱い討論が交わされた。現在、シンポジウムの他、セミナー、水曜哲学会、青年哲学会などの企画が進行中、あるいは準備中である。その活動の状況は、ホームページhttps://miraitetsugaku.com/でご覧いただきたい。 『未来哲学』の刊行は、研究所の中核的な事業の一つであり、年2回程度の刊行を意図している。創刊号は2020年11月に刊行されたが、所長の末木による「創刊のことば」の後、特集・コラム・論考・書評と対話の4本の柱を設定した。「特集」は、シンポジウムの提題(山内志朗・永井晋・中島隆博)とコメント(佐藤麻貴)、ならびに中島隆博・納富信留の対談により、過去の叡知の再発見を通して、どのように未来を切り開くかが論じられている。「コラム」は、周辺分野の研究者による興味深いエッセーによって、視野を広げようというもので、辻誠一郎(縄文学)、三津間康幸(古代バビロン文化史)、細川瑠璃(ロシア思想)の三氏により、常識を打ち破る新鮮な知見が披露されている。 「論考」は、中堅・若手の研究者による力の籠もった論文であり、仏教に関して護山真也・師茂樹、イスラームに関して小村優太・法貴遊、田辺元に関して田島樹里奈が執筆した。専門的な問題がスリリングに今日の課題に直結して論じられている。最後に「書評と対話」は、末木『日本思想史』に対する葛兆光の書評をもとに、葛・末木の対談で深めている。 以上のように、本誌は研究所の活動を反映して、水準を落とすことなく、しかし、狭い専門の枠にとらわれず、未来へ向けて哲学のエネルギーを結集することを目指している。人文系の学問の不要論がかまびすしいが、そんな時代だからこそ、世界や人間についてもっとも深く根源から捉え直す真の哲学が生まれなければならない。広く関心を持っていただけることを期待したい。 『未来哲学 創刊号』未来哲学研究所編 |
|
Copyright (c) 2020 東京都古書籍商業協同組合 |