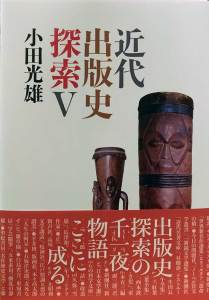『近代出版史探索Ⅴ』小田光雄 |
| 『近代出版史探索』は短編連作のかたちで書き継がれ、2019年に第1巻、20年に第2巻から第5巻までが続けて出され、ようやく1001話に達した。この連載は2009年に始めているので、12年を閲したことになる。 拙ブログ連載タイトルは「古本夜話」で、確かに毎回古本屋で購入した本を取り上げ、それに関する様々な事柄を記述していくスタイルをとっている。そのためによくある古本エッセイかと思われるかもしれないが、もちろんそのように読まれてもかまわないけれど、いくつもの問題設定と目的を内包させ、書き続けてきたのである。それは前著『古本屋散策』のタイトルと内容に差異が生じていることとも共通していよう。 そうした問題設定と目的に関しては各巻の本文や「あとがき」で、様々にふれてきているが、第5巻刊行に際し、このような多くの読者に配信されるメールマガジンに書く機会を得たこともあり、それらを具体的に挙げてみる。 *出版業界総体をテーマとする。それは作者(著者)・出版社(経営、編集、営業)・取次(流通)・書店(販売)・読者がトータルな対象となる。 とりあえず「千一夜」を迎えたし、第5巻の刊行に合わせて告白すれば、この探索シリーズの試みは、ベンヤミンの『パサージュ論』を範として続けられてきた。ここではパリのパサージュならぬ、日本の出版業界総体が対象となり、近代の商品としての出版物が生み出す幻想の中に、近代日本がイメージした集団の夢と神話の探究を目的としている。 近代日本のイメージ造型は西洋と東洋のせめぎ合いの中で、出版物を通じて形成されていった。テレビもない戦前の世界にあって、雑誌や書籍が果たした役割は想像以上に大きく、それは大東亜戦争へと導いていく一端を担っていた。現在からみれば、それもベンヤミンのいうところの幻影・幻像空間(フアタンスマゴリー)のようでもある。 それらの根源と痕跡をたどるために、アトランダムな古本の集書を絶え間なく繰り返し、まさに遊歩者(フラヌール)のように近代出版史を遡行し、それらの内容を記録し、引用し、時代との関係、出版に至る経緯と事情を追跡し、その分野のトータルな集積となることもめざしてきた。 大風呂敷を広げて、本当に恐縮だが、「千一夜」を迎えての妄言として、ご海容願えれば幸いである。そのようなわけで、『近代出版史探索』シリーズは出版、文学、思想史もしくは広範な文化史の読み直しをめざし、現在でも続いている。少部数のために高定価で心苦しいこともあり、図書館にリクエストして、読んでもらえればと思う。 出版・読書メモランダム 『近代出版史探索Ⅴ』 小田光雄 著 |
|
Copyright (c) 2021 東京都古書籍商業協同組合 |