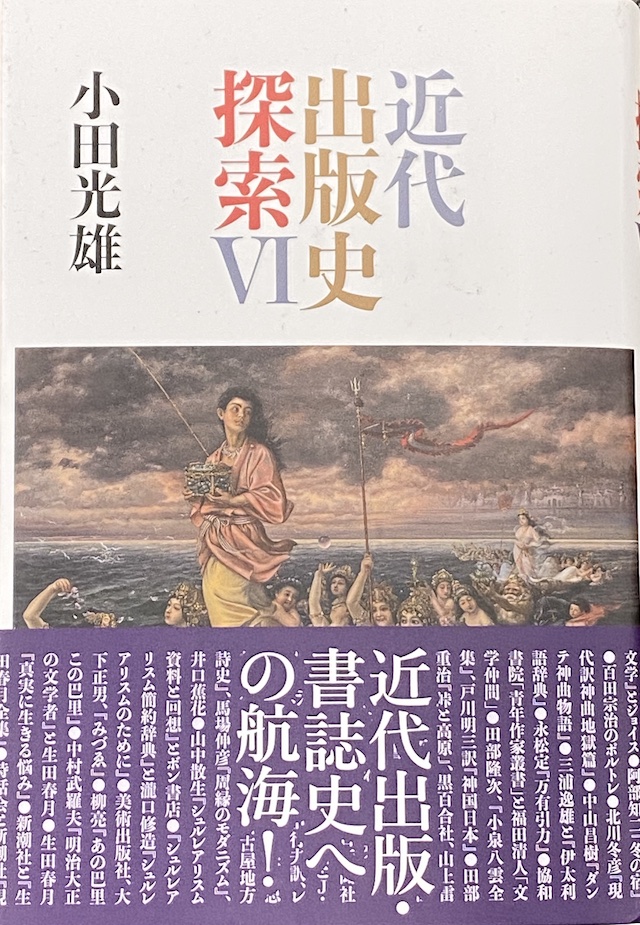『近代出版史探索Ⅵ』小田光雄 |
|
論創社の森下紀夫、小田嶋源両氏の全面的なバックアップを受け、3年余の短い期間で、本探索も六巻目となった。お二人の期待に応えるためにも、とりあえず十巻をめざし、今しばらく書き続けていくつもりだ。
本探索の目的は各巻の「あとがき」で、様々に述べてきたが、一巻で既述しておいた「新たな近代出版史の森の造形」はなされつつあるし、姿を見せ始めているといっていいだろう。ただどれだけの読者がいるのかは定かでないし、書評もまったく出ないに等しいので、少しばかり残念ではある。しかしここまで刊行できたわけだから、版元だけでなく、書店と図書館の支援、少数ではあっても読者の存在を信じたい。 このようなことを書いたのは、本探索の主要な時代背景である大正から昭和戦前にかけて、確固たる読者、読書社会が形成され、出版もまたそれをバックヤードとして営まれてきたと判断せざるをえないからだ。そうした読者と読書をめぐる共同体を支えとして出版業界も成長し、それは所謂「想像の共同体」であったにしても、戦後まで持続され、1990年代までの出版社・取次・書店という近代出版流通システムを維持するコアだったと確信する。もちろんそこには古書業界も含まれている。 そうした思いは戦後ただちにみすず書房を創業した小尾俊人の次のような言葉に最近出会ったことにもよっている。「著者があり、訳者がある。出版者があり、読者がある。書店があり、図書館がある。それらをむすび支える無数の網、ネットワークがある。その質と拡がりが、文明の内容をなしている。その環の一つで、私はあったのだ」(『本は生まれる。そして、それから』幻戯書房、2003年) このようにして小尾とみすず書房も始まったわけで、それは戦前の大正、昭和の多くの出版者も同じだったにちがいないし、そこに著者、訳者、読者がいて、書店や図書館もあり、さらに付け加えれば、古本屋のみならず、赤本、特価本、造り本、外交販売本などの多彩な版元も存在していた。 本探索はこれらをトータルな出版業界として捉え、横断的に追求し、近代出版史だけでなく、文学史や思想史を含んで、群像ドラマとして描き出そうと試みている。そこでは大出版社と中小出版社の区別はなく、それは出版者、著者、訳者も同様で、作品もしかりである。そして出版社、著者、訳者、作品は繰返し言及されるという再現法を採用している。 そのようにして見出される近代出版史の世界は異化され、従来と異なる様相を呈してくる。例えば、昭和初期は円本時代と呼ばれ、予約出版の全集のバブル出版に焦点が当てられている。しかし新たな照明を当てれば、文学的にいって、近代文学、外国文学、大衆文学の三派鼎立だけでなく、一方では詩や演劇の時代、もう一方では近代思想やプロレタリア芸術の時代であったことも浮かび上がってくる。それらに「エロ・グロ・ナンセンス」の出版物の氾濫も忘れるべきではない。 いうなれば、出版をコアとして文学、文化、芸術が渾然一体となって沸騰していたのだ。それと併走するように出版者、著者、訳者、読者がコラボレーションし、文学、思想、演劇から「エロ・グロ・ナンセンス」の出版に至るまで、すべてが百花斉放していた時代だといえよう。それが昭和の始まりにおいて沸騰点に達したことによって、昭和が出版の時代であり続けたように思われてならない。小尾にしても、私のような戦後生まれの世代にしても、そうした昭和戦前、戦後の出版状況の中から出立してきたことになろう。 このようなことを記してきたのは、数日前に、『日本読書新聞』と『図書新聞』の前編集長井出彰の訃報が届いたからでもある。享年78歳を考えれば、彼もまた戦後出版史の証言者の一人で、『書評紙と共に歩んだ五〇年』(「出版人に聞く」シリース9、論創社)が残されたことはよかったと思う。 自著の紹介が中途半端になってしまったかもしれないが、井出のインタビューは私が担っていることもあり、諒とされたい。 |
|
Copyright (c) 2022 東京都古書籍商業協同組合 |