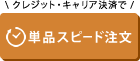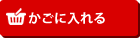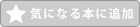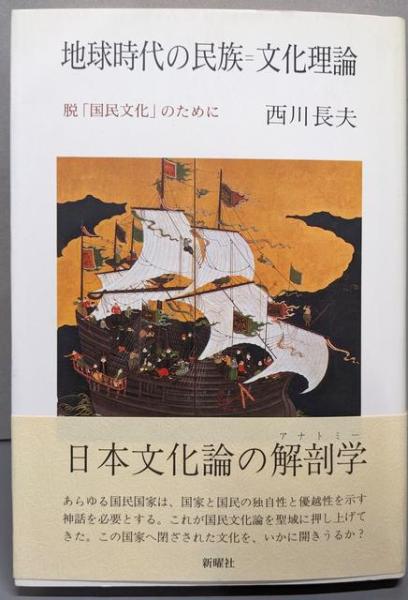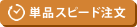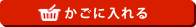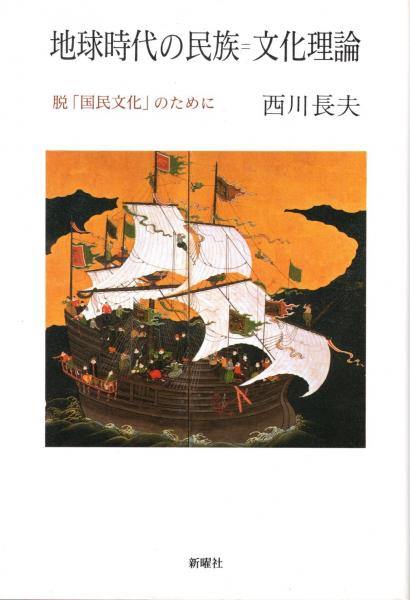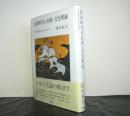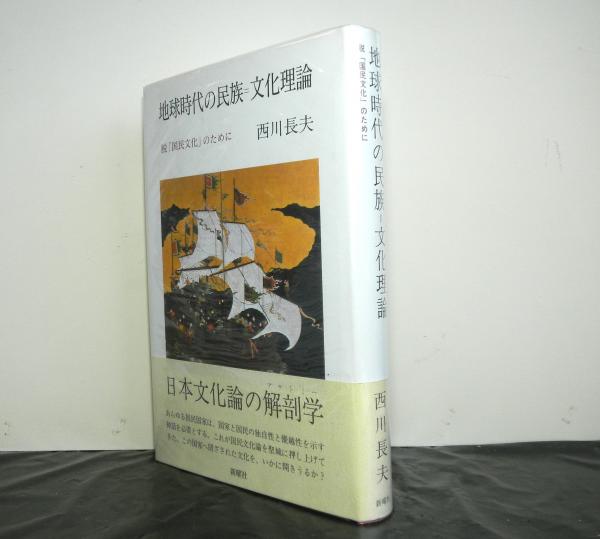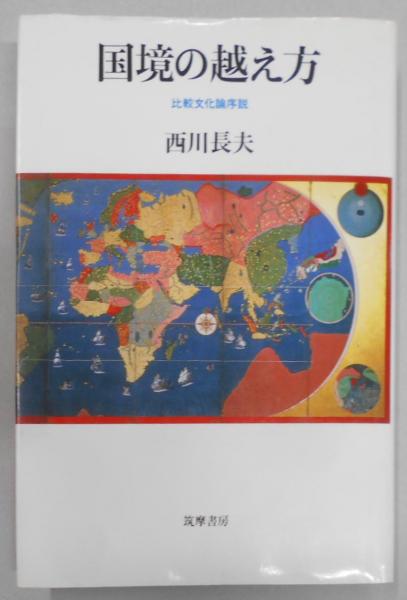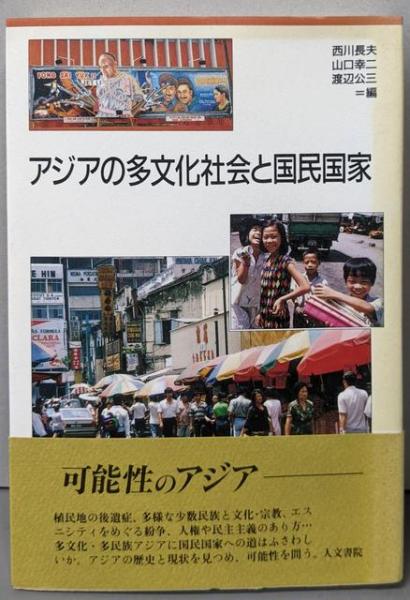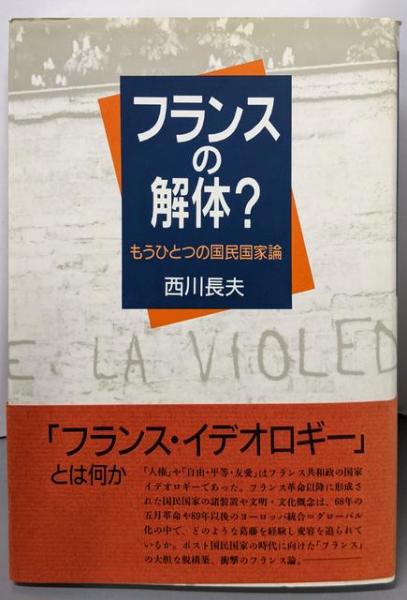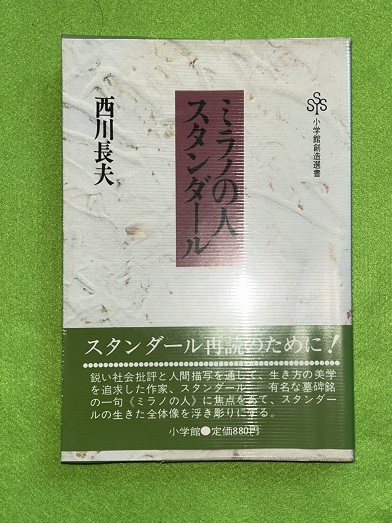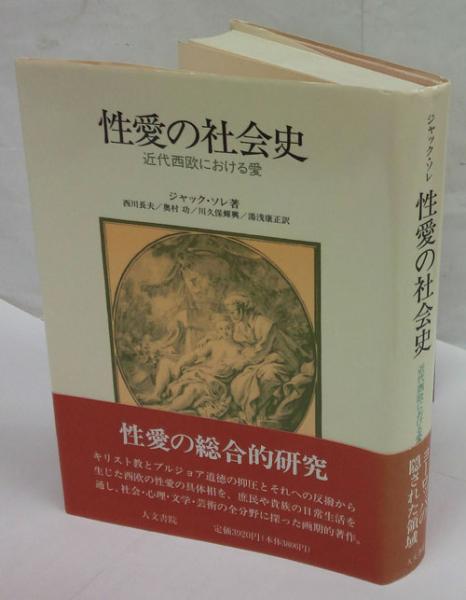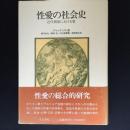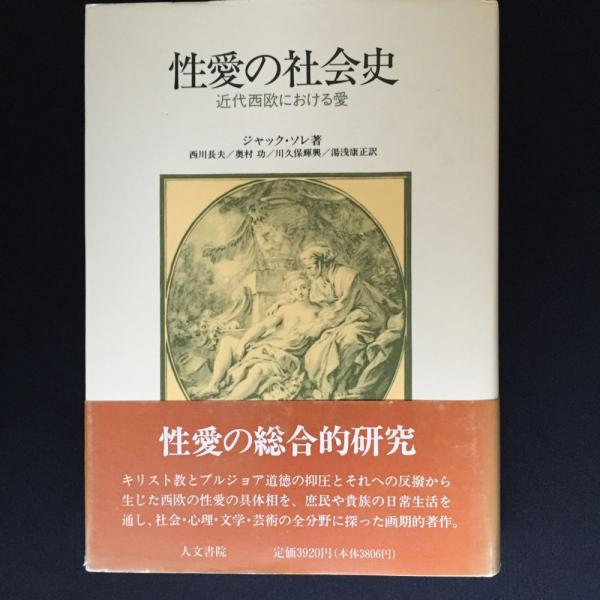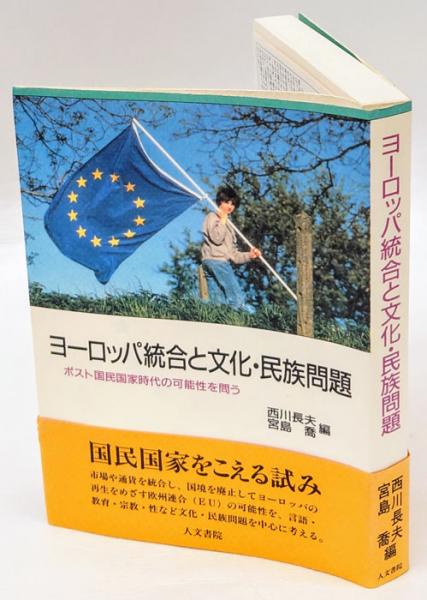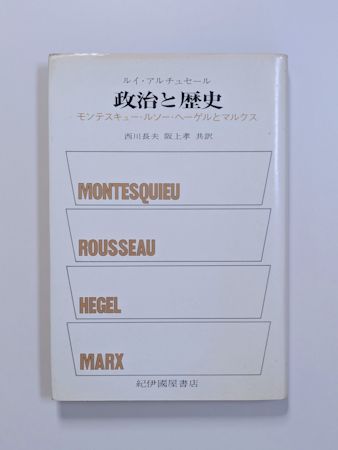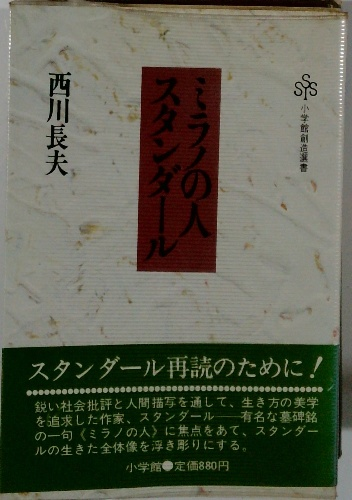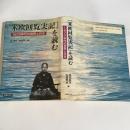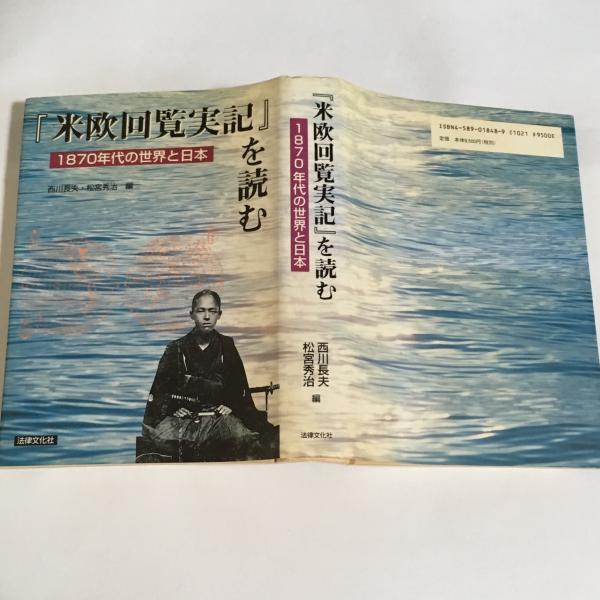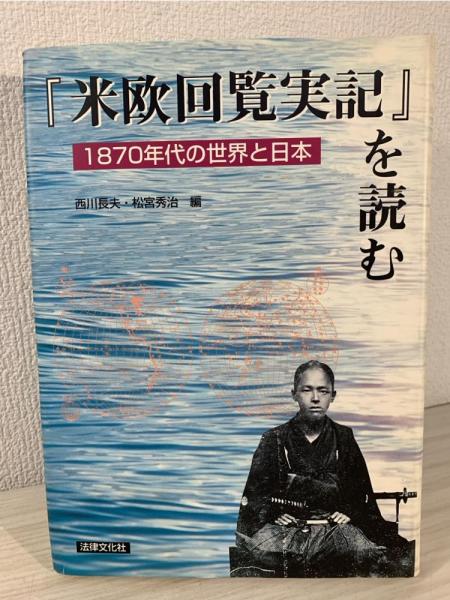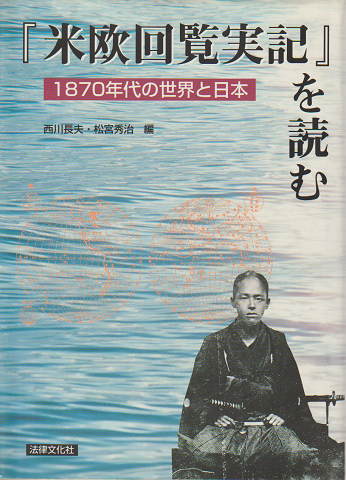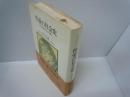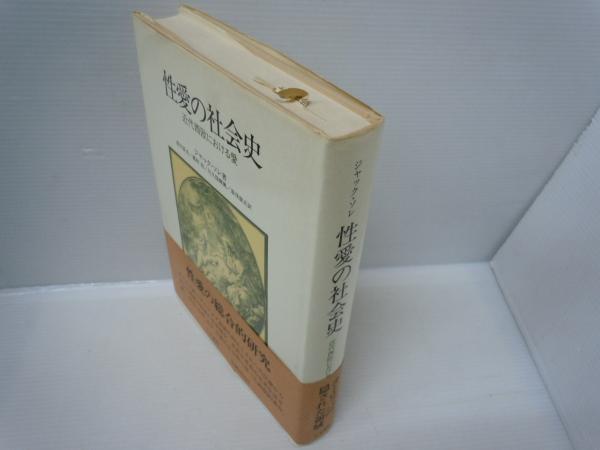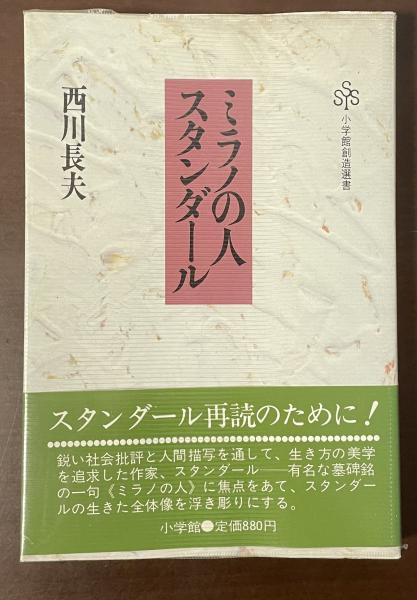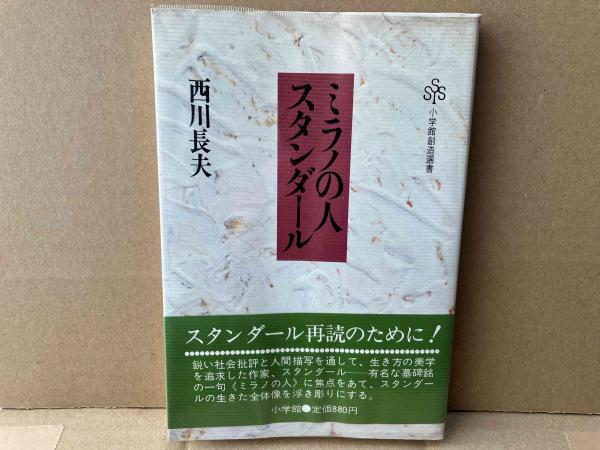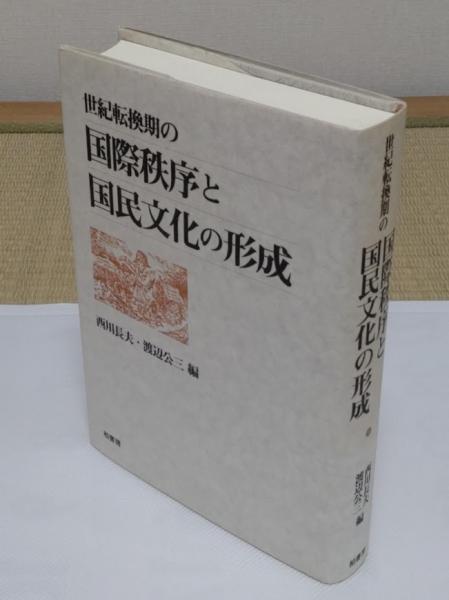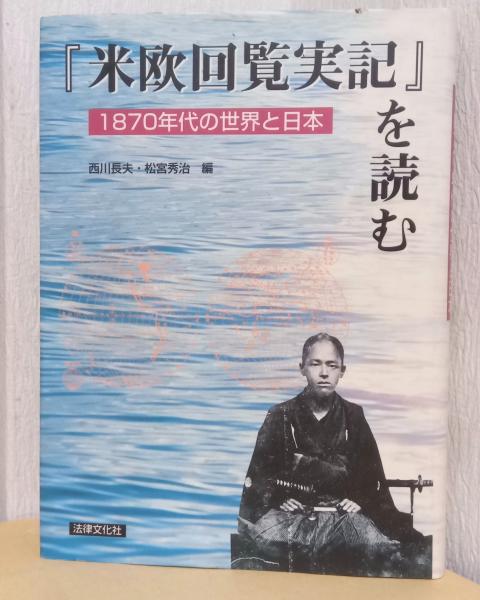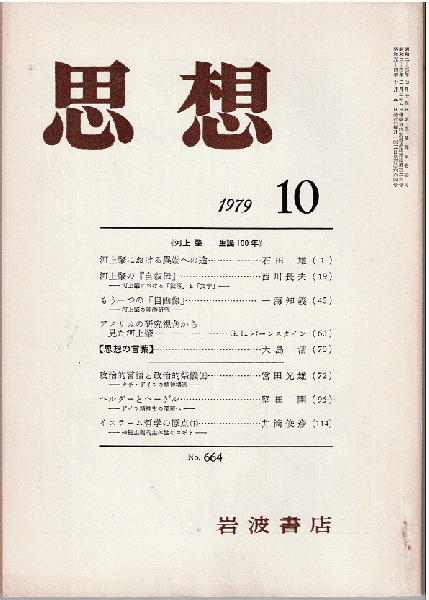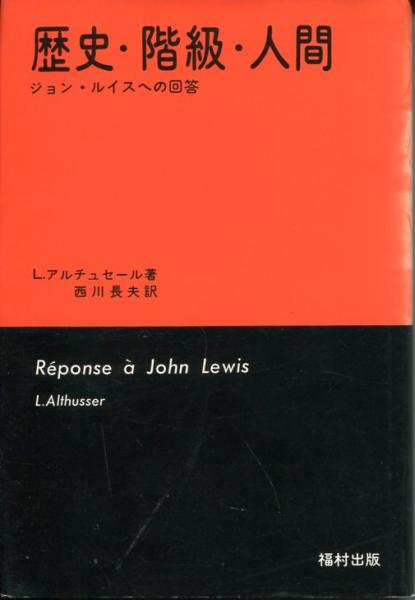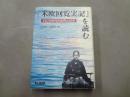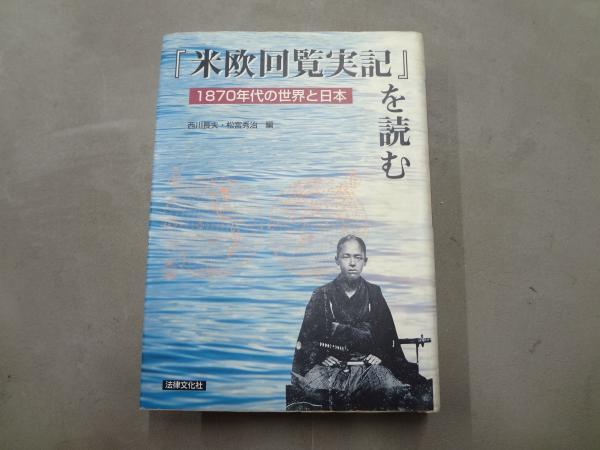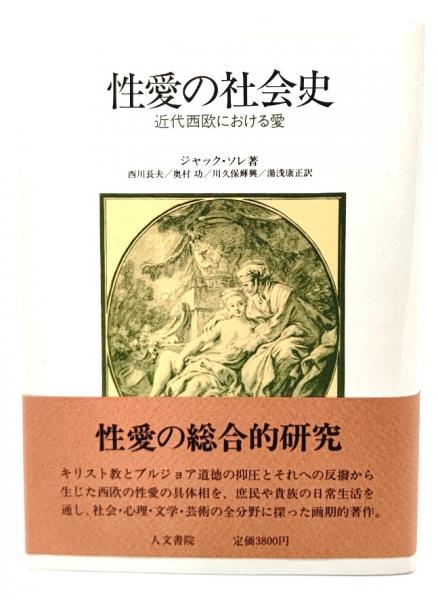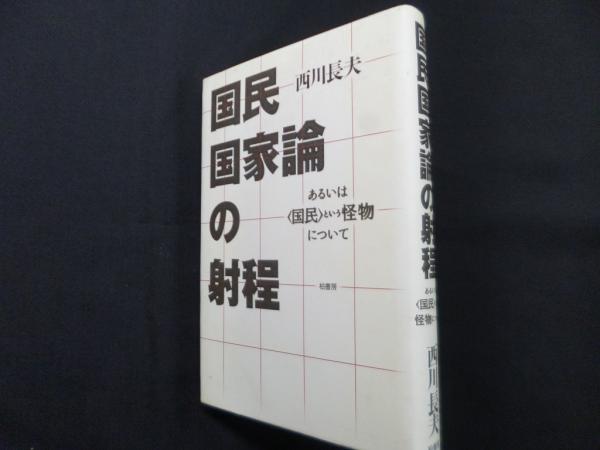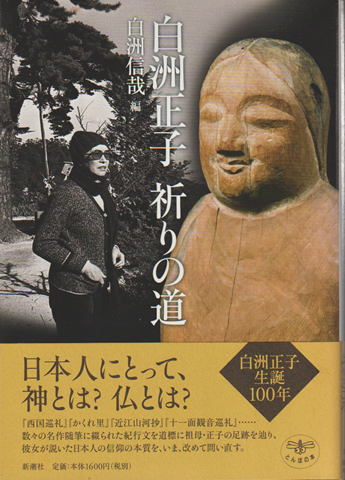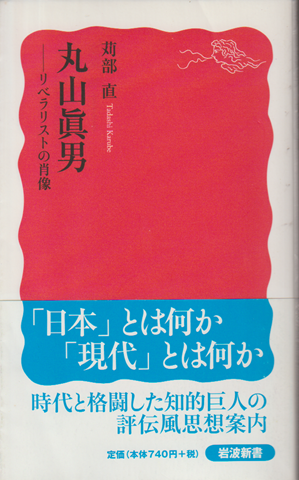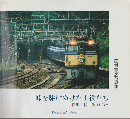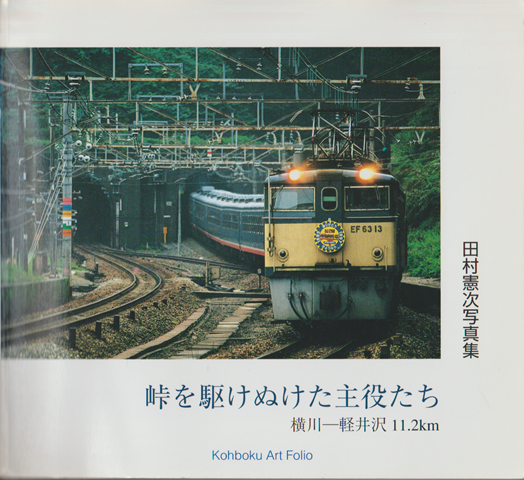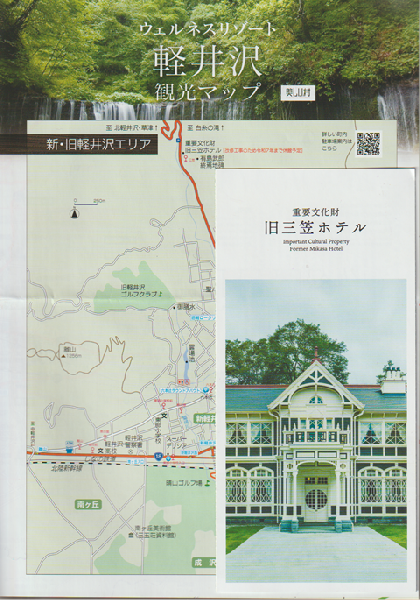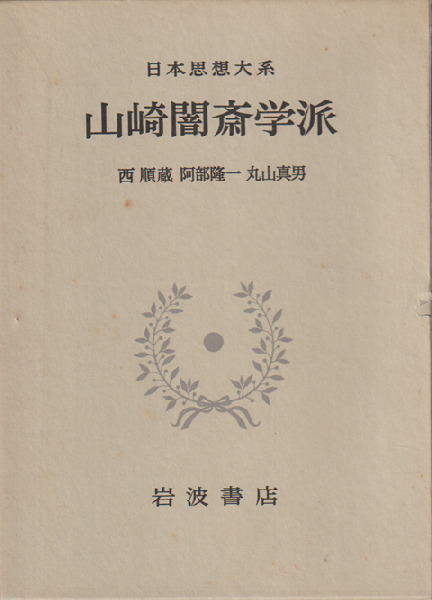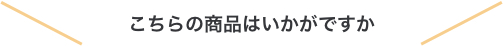
キーワード「地球時代の民族=文化理論」の検索結果
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町
北海道札幌市北区北8条西5丁目
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町
東京都葛飾区堀切
東京都八王子市東町
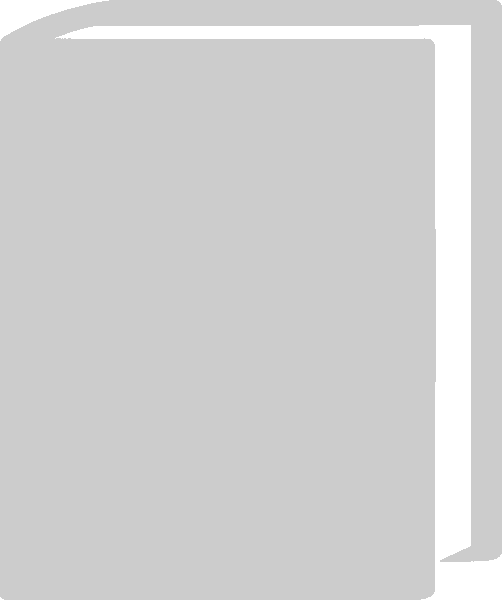
地球時代の民族=文化理論 : 脱「国民文化」のために あらゆる国民国家は,国家と国民の独自性と優越性を示す神話を必要とし,これが国民文化論を聖域に押し上げてきた。この自国への「過剰」で,閉ざされた関心をどのように開きうるか。ボーダーレス化する国際社会に対応する新たなメンタリティの探求。
大阪府大阪市北区浪花町
愛知県春日井市
著者名「西川長夫」の検索結果
東京都国立市東
岩手県一関市山目字立沢
東京都八王子市東町
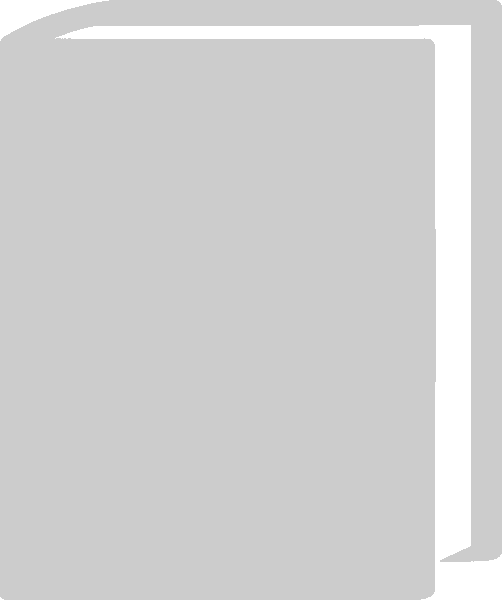
スタンダールの遺書 スタンダールの遺書の数は、彼の遺した作品の数よりはるかに多かった。 若い頃から精神の安定を欠くことの多かった彼は、度々死を想った。彼は世間からだけでなく、愛する女性にも拒絶され、時には自殺を考えた。22歳のときはそのための毒薬を友人に頼み、死を目前にした1840年には、自らを撃つための銃を買い求めている。彼は20代の終わりから、何度となく遺書を書くようになった。1828年だけで4通、1835年には10回以上それを記した。遺書だけあって、書面には様々な指示が盛り込まれた。死後出版の依頼、財産贈与、墓地の希望、原稿の遺贈。時々、死者の言葉は生きている者より力を持つ。
神奈川県川崎市麻生区早野
愛媛県松山市味酒町
天・小口に少しみあり 本文良好
岡山県岡山市南区郡
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町
北海道札幌市清田区
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5-127-13 伊勢佐木町ロイヤル1F
東京都青梅市成木8-33-
神奈川県海老名市門沢橋
新潟県三条市塚野目
京都府京都市左京区浄土寺西田町
千葉県山武郡九十九里町作田
東京都文京区本郷
北海道札幌市中央区大通西
[雑誌]思想 664号 1979年10月 河上肇-生誕100年(特集)
千葉県山武郡九十九里町作田
翻訳の世界 1980年1月 特集:児童文学の表現研究 素顔の翻訳家/千種堅 欠陥翻訳時評/西川長夫
福岡県北九州市戸畑区境川
京都府京都市左京区浄土寺西田町
東京都文京区本郷
京都府京都市左京区浄土寺西田町
大阪府大阪市天王寺区東上町
長野県北佐久郡軽井沢町追分
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5-127-13 伊勢佐木町ロイヤル1F
群馬県高崎市あら町
岡山県岡山市北区内山下
帯付
書店シール有
岡山県岡山市中区西川原55-3 西川原プラトン202
京都府京都市中京区壬生土居ノ内町
愛知県豊川市麻生田町
秋田県横手市上内町
大阪府吹田市江坂町
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町
ロマン主義の比較研究 (立命館大学人文科学研究所研究叢書 7)
北海道札幌市東区北二十六条東七丁目
20世紀をいかに越えるか 多言語・多文化主義を手がかりにして
東京都新宿区西早稲田
大阪府大阪市天王寺区東上町
京都府京都市北区小山西大野町
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5-127-13 伊勢佐木町ロイヤル1F
北海道札幌市北区北8条西5丁目
神奈川県海老名市門沢橋
東京都文京区小石川
京都府京都市左京区浄土寺西田町
20世紀をいかに越えるか 多言語・多文化主義を手がかりにして
京都府京都府京都市上京区有馬町184
東京都江戸川区南小岩
東京都目黒区目黒
宮城県仙台市青葉区本町
神奈川県川崎市宮前区神木本町
・本の形態 :単行本ハードカバー
・本のサイズ :22×16cm
・ページ数 :410p
・発行年 :1985年12月15日(初版第2刷)
・初版年 :1985年10月10日
・ISBN :9784409230145
◆本の状態:良好
・表紙カバー/そでの部分にうすいシミあり。・本体/天にうすいやけ、わずかな埃シミあり。見返しにうすいシミあり。・本文/非常に良い。
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町
長崎県長崎市鍛冶屋町
北海道札幌市東区北二十六条東七丁目
京都府京都市左京区一乗寺西水干町
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町
東京都千代田区西神田
佐賀県佐賀市新栄西
北海道札幌市東区北二十六条東七丁目
千葉県山武郡九十九里町作田
大阪府泉大津市二田町
神奈川県横浜市旭区本宿町
福岡県福岡市中央区大名
京都府京都市左京区東丸太町
東京都八王子市越野 8-23
書誌カタログから探す
「日本の古本屋」では、書籍ごとの基本情報を「書誌カタログ」にまとめております。書誌カタログからは欲しい本のリクエストが可能です。
お探しの本が「日本の古本屋」に追加された場合に自動通知をお送りさせていただきます。

-
リクエストを送る
-
書籍情報で在庫を検索
古書追分コロニーの新着書籍
長野県北佐久郡軽井沢町追分
長野県北佐久郡軽井沢町追分
長野県北佐久郡軽井沢町追分
長野県北佐久郡軽井沢町追分
峠を駆けぬけた主役たち 横川-軽井沢11.2km 田村憲次写真集
長野県北佐久郡軽井沢町追分
長野県北佐久郡軽井沢町追分
長野県北佐久郡軽井沢町追分
長野県北佐久郡軽井沢町追分