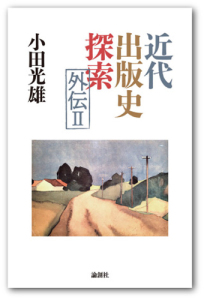「近代出版史探索外伝Ⅱ」と小田光雄小田啓子 |
|
故小田光雄の70冊目となる著書『近代出版史探索外伝Ⅱ』が5月に出版されました。売れっ子でも流行作家でもない小田光雄が73年の生涯で70冊もの著書を刊行できたことは感無量です。たくさんの方々のご支援があってのことと深く感謝いたします。
小田光雄も『近代出版史探索Ⅶ』の刊行時に、メールマガジン2024年2月26日号の「自著を語る」で、長編連作シリーズ『近代出版史探索』の成立経緯と関係者に対する深い謝辞を述べています。 次に論創社をはじめ、身近な人たちの好意と支援によって出版が継続されていることを伝えています。本の内容紹介にはふれずに、まるで虫の知らせがあったかのような感謝の言葉を並べ、3カ月後に亡くなってしまいました。 一冊目の『近代出版史探索外伝』は2021年9月に刊行されました。2009年から始めたブログ「出版・読書メモランダム」は「古本夜話」と、出版業界の定点観測である「出版状況クロニクル」を二本の柱として書き綴られましたが、その他に「ゾラからハードボイルドへ」「謎の作者佐藤吉郎と『黒流』」「ブルーコミックス論」などのジャンルもありました。「あとがき」で、その三本を映画の「雑多な三本立て上映」を模すようにして、『外伝』は編まれ、『近代出版史探索』シリーズの中にあって、「間奏曲のような趣」の「愛着のある論稿」で 小田光雄は静岡県西部の地方都市の二十数軒ほどの農村集落に生まれ、大学での在京期間を除き、七十年近くをそこで暮らしてきました。そして高度成長期に伴い、流入してきた新住民との混住の郊外消費社会が形成されていくなかに身を置いて、その変遷を見つめてきました。 今回の『近代出版史探索外伝Ⅱ』は論創社のホームページに連載されたコラム「本を読む」(2016年2月~2024年6月)の100編に、未発表原稿10編と「解説」3編などを加えて単行本化したものです。 小田光雄の著書ではめずらしく「本を読む」のタイトルどおり、少年期の農村の駄菓子屋兼 「ドゥマゴ文学賞」受賞時の挨拶で、自分は「読み書きの職人である」と見なし、ひっそりと居職の生活を続けてきたと述べています。そこに至るまでに書店員、店長、書店経営を経て、出版社パピルス代表として数々の翻訳書を刊行してきました。中学生の頃は「売れない物書き」になりたいと考えていたと語っていて、その夢もかなえられました。また「ドゥマゴ文学賞」を受賞するに至り、長きにわたって書き続けてきたご褒美だと喜んでおりました。 さて、小田光雄は3カ月に満たない闘病で亡くなってしまったので、直前まで元気で、これから出版したいリストを書いていました。まるで遺書のような「幻の企画書」です。 自治会長として古くなった公会堂の立て直しを計画しましたが、諸事情により無念の白紙撤回となりました。『自治会 宗教 地方史』は地方における宗教や歴史の大きな文脈の中でそのいきさつを綴っていて、原稿は完成に近づいていました。 『失われた新書を求めて』は『近代出版史探索外伝Ⅲ』として出したいと書かれていました。1950年代に創刊され、60年代に終わった新書の総合目録を作成し、戦後多数の新書が出現した背景と、消えてしまった経緯をたどる企画だったようです。 その他に「戦後の大手出版社のシリーズ物」『出版状況クロニクルⅧ』総集編、『近代出版史探索Ⅷ』『古本屋散策Ⅱ』「出版人に聞く」シリーズの再開など、貪欲に出版を夢見ておりました。これらを書き続けていたら、どんなものになっただろうかと思いを巡らせています。 『近代出版史探索外伝Ⅱ』は小田光雄が50年前に購入し、愛してやまなかった絵画を表紙に |
|
Copyright (c) 2025東京都古書籍商業協同組合 |