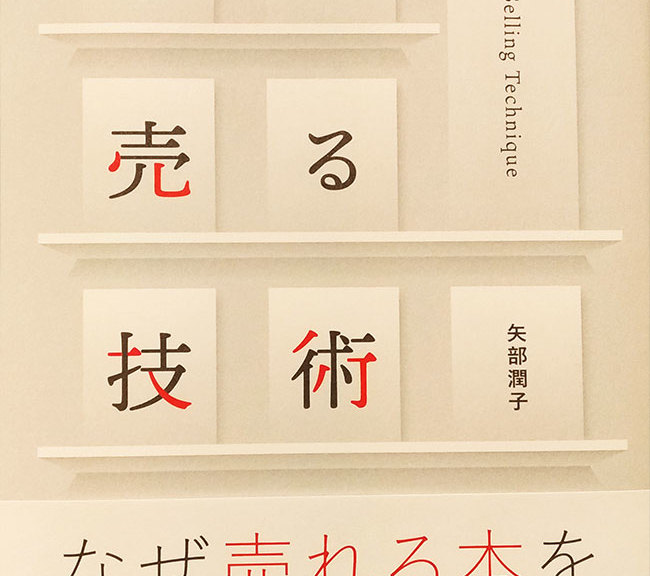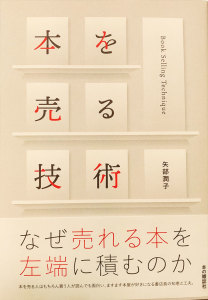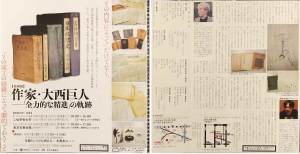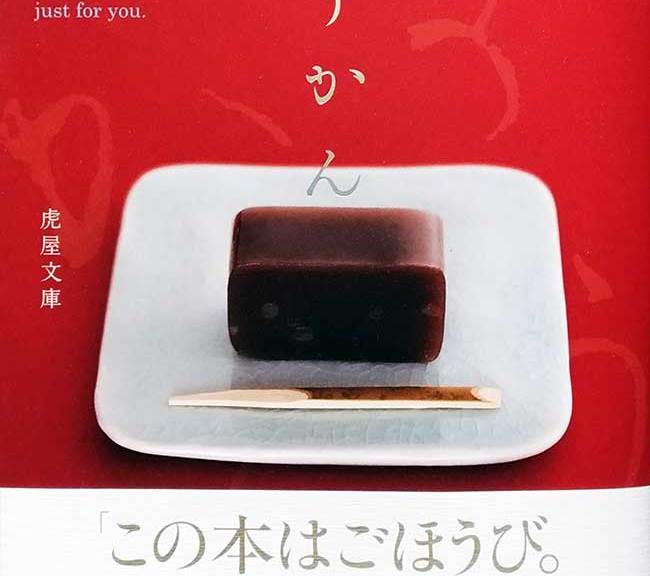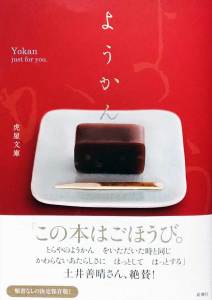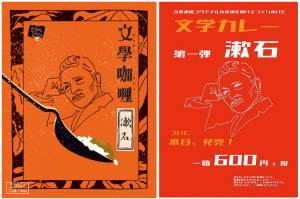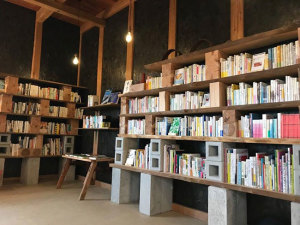■■■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■■■
。*..*.:☆.:*・日本の古本屋メールマガジン・*:.☆.:*..*。
古書市&古本まつり 第86号
。.☆.:* 通巻294・3月10日号 *:.☆. 。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メールマガジンは、毎月2回(10日号と25日号)配信しています。
初旬に(10日前後)全国で開催されている古本展示即売会など、
イベント情報をお送りします。お近くで開催される際は、ぜひ
お出掛け下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━【シリーズ 古書の世界】━━━━━━━━
北陸古本案内 その3
オヨヨ書林 山崎 有邦
前々回の石川県、前回の富山県に続き、今回は福井の古本屋を紹
介させていただきます。
福井駅前の好文堂。街の本屋としては広めの店内に、文庫・漫画・
文芸書・趣味本・郷土史・全集・美術書・アダルトとないジャンル
はないくらいまんべんなく網羅された品揃えです。古い雑誌や戦前
の本もしっかりと置かれています。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5619
オヨヨ書林
https://oyoyoshorin.jp/
━━━━━━━━━【シリーズ 古本マニア採集帖】━━━━━━
第14回 倉敷から遠いでさん ぼやきながら集めるひと
南陀楼綾繁
昨年の3月、岡山大学のキャンパス内のスペースで「小さな春の
本めぐり」というイベントが開催された。「瀬戸内ブッククルーズ」
というグループの主催で、中四国の個性的な本屋が出店した(この
イベントは今年も開催予定だったが、新型コロナウィルスの影響で
中止となったのは残念だった)。
続きはこちら
/wppost/plg_WpPost_post.php?postid=5617
南陀楼綾繁(なんだろう・あやしげ)
1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一
文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、
図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年
から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」
の代表。各地で開催される多くのブックイベントにも関わる。
「一箱本送り隊」呼びかけ人として、石巻市で本のコミュニティ
・スペース「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。本と町と人を
つなぐ雑誌『ヒトハコ』(書肆ヒトハコ)編集発行人。著書に
『ナンダロウアヤシゲな日々』(無明舎出版)、『一箱古本市
の歩きかた』(光文社新書)、『町を歩いて本のなかへ』(原書房)、
『編む人』(ビレッジプレス)、『本好き女子のお悩み相談室』
(ちくま文庫)などがある。
ツイッター
https://twitter.com/kawasusu
『蒐める人 情熱と執着のゆくえ』 南陀楼綾繁 著
皓星社刊 価格:1,600円(+税) 好評発売中!
http://www.libro-koseisha.co.jp/publishing/atsumeruhito/
━━━━━【3月10日~4月15日までの全国即売展情報】━━━━━
⇒ https://www.kosho.or.jp/event/list.php?mode=init
※新型コロナウイルスの影響により、今後、各地で予定されている
即売展も、中止になる可能性がございます。
お客様のご理解、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
--------------------------
第10回 戸田書店 古本・古書フェア(群馬県)
期間:2020/01/27~2020/03/15
場所:戸田書店 高崎店 高崎市下小鳥町438-1
--------------------------
イービーンズ古本まつり(レコード・CD市 併催/宮城県)
期間:2020/01/30~2020/03/14
場所:宮城県仙台市青葉区中央4-1-1 9階 杜のイベントホール
http://www.e-bf.jp/e_beans/news/index.html
--------------------------
フジサワ古書フェア(神奈川県)
期間:2020/02/27~2020/03/11
場所:有隣堂藤沢店4階ミニ催事場
神奈川県藤沢市南藤沢2-1-1フジサワ名店ビル
--------------------------
第14回 カジル横川古本市(広島県)
期間:2020/03/01~2020/03/15
場所:JR横川駅前フレスタモール カジル横川 1階通路
広島市西区横川町3-2-36 JR横川駅隣接
--------------------------
第93回 彩の国 所沢古本まつり(埼玉県)
期間:2020/03/04~2020/03/10
場所:くすのきホール
(西武線所沢駅東口前 西武第二ビル8階 総合大会場)
https://tokorozawahuruhon.com/
--------------------------
第22回フジサワ湘南古書まつり(神奈川県)
期間:2020/03/12~2020/03/15
場所:有隣堂藤沢店イベントホール (フジサワ名店ビル6階)
神奈川県藤沢市南藤沢2-1-1 フジサワ名店ビル
--------------------------
BOOK & A(ブック&エー)
期間:2020/03/12~2020/03/15
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
--------------------------
紙魚之會
期間:2020/03/13~2020/03/14
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
--------------------------
第178回神戸古書即売会(兵庫県)
期間:2020/03/13~2020/03/15
場所:兵庫古書会館 神戸市中央区北長狭通6-4-5
--------------------------
たにまち月一古書即売会(大阪府)
期間:2020/03/20~2020/03/22
場所:大阪古書会館 大阪府大阪市中央区粉川町4-1
http://www.osaka-kosho.net/
--------------------------
趣味の古書展
期間:2020/03/20~2020/03/21
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
--------------------------
国際稀覯本フェア-日本の古書 世界の古書-
期間:2020/03/20~2020/03/22
場所:東京交通会館 展示会場12F カトレアサロン A・B
千代田区有楽町2-10-1
http://abaj.gr.jp/
--------------------------
浦和宿古本いち
期間:2020/03/26~2020/03/29
場所:JR浦和駅西口下車 さくら草通り徒歩5分 マツモトキヨシ前
https://twitter.com/urawajuku
--------------------------
和洋会古書展
期間:2020/03/27~2020/03/28
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
--------------------------
五反田遊古会
期間:2020/03/27~2020/03/28
場所:南部古書会館 品川区東五反田1-4-4
--------------------------
中央線古書展
期間:2020/03/28~2020/03/29
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
--------------------------
第7回 小倉駅ナカ本の市(福岡県)
期間:2020/03/28~2020/04/05
場所:小倉駅ビル内・JAM広場 (JR小倉駅 3階 改札前)
--------------------------
第39回 古本浪漫洲 Part1~Part5
期間:2020/04/01~2020/04/17
場所:新宿サブナード2丁目広場(催事場) 新宿区歌舞伎町1-2-2
--------------------------
青札古本市
期間:2020/04/02~2020/04/05
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
--------------------------
下町書友会
期間:2020/04/03~2020/04/04
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
--------------------------
第12回横浜めっけもん古書展(神奈川県)
期間:2020/04/04~2020/04/05
場所:神奈川古書会館1階特設会場
--------------------------
第15回 上野広小路古本まつり
期間:2020/04/06~2020/04/12
場所:永谷お江戸上野広小路 ギャラリー+スペース36
台東区上野1-20-10 お江戸上野広小路亭1階
--------------------------
立川フロム古書市
期間:2020/04/10~2020/04/24
場所:フロム中武(ビッグカメラ隣) 3階バッシュルーム(北階段際)
立川駅北口徒歩5分
--------------------------
書窓展(マド展)
期間:2020/04/10~2020/04/11
場所:東京古書会館 千代田区神田小川町3-22
--------------------------
大均一祭
期間:2020/04/11~2020/04/13
場所:西部古書会館 杉並区高円寺北2-19-9
--------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次回メールマガジンは3月下旬に発行です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このメールは「日本の古本屋会員」の方で、メールマガジンの配信
を希望された方にお送りしています。
ご不要な方の解除方法はメール下部をご覧下さい。
【日本の古本屋】は全国950書店参加、データ約600万点掲載
の古書籍データベースです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
見逃したメールマガジンはここからチェック!
【バックナンバーコーナー】
https://www.kosho.or.jp/wppost/plg_WpPost_category.php?catid=33
┌─────────────────────────┐
次回は2020年3月下旬頃発行です。お楽しみに!
└─────────────────────────┘
*゜*.:*☆ 本を売るときは、全古書連加盟の古書店で ☆*.:*゜*
全古書連は全国古書籍商組合連合会(2,200店加盟)の略称です
https://www.kosho.or.jp/buyer/list.php?mode=from_banner
==============================
日本の古本屋メールマガジンその294 2020.3.10
【発行】
東京都古書籍商業協同組合:広報部・「日本の古本屋事業部」
東京都千代田区神田小川町3-22 東京古書会館
URL http://www.kosho.or.jp/
【発行者】
広報部:二見彰
編集長:藤原栄志郎
==============================